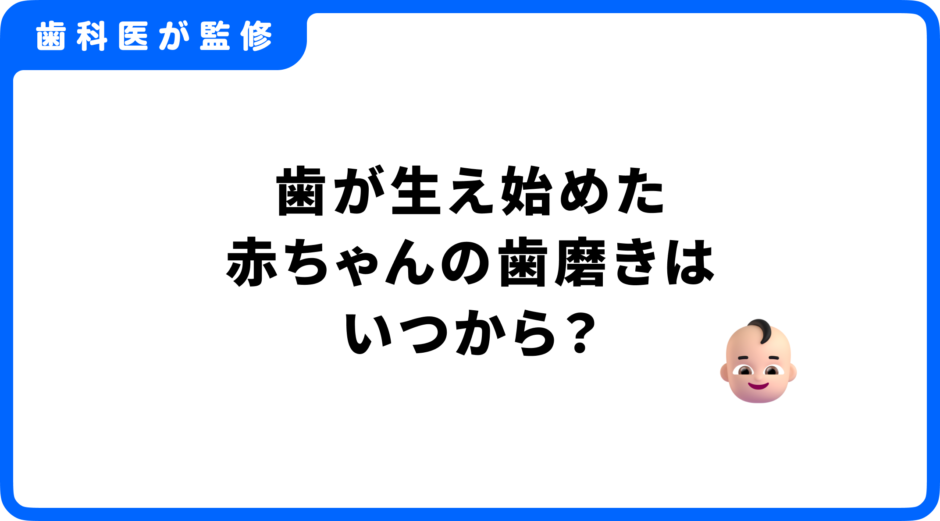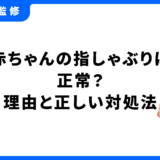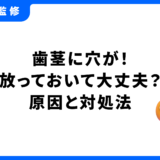赤ちゃんの歯が生えてきたとき、「歯磨きはいつから始めるべき?」「どうやって磨けばいいの?」と悩む保護者の方は多いものです。乳歯は、むし歯予防だけでなく、将来生えてくる永久歯の土台として非常に重要な役割を担っています。
本記事では、歯が生え始めた赤ちゃんにいつからどのように歯磨きを始めるべきかを、歯科の専門的視点からやさしく解説します。赤ちゃんが歯磨きを嫌がらないための工夫や、正しい歯ブラシ・歯みがき剤の選び方、よくある質問にもお答えしています。
- 赤ちゃんの歯磨きを始める適切なタイミング
- 成長段階別の歯磨き方法と親の対応
- 歯磨きを嫌がるときの対処法
- 歯ブラシ・歯みがき剤の正しい選び方と使い方
歯磨きはいつから?赤ちゃんのケア開始タイミング

歯磨きのスタートは、最初の乳歯が顔を出したタイミングが目安です。一般的には生後6〜9か月ごろ、下の前歯(乳中切歯)が生えてきますが、個人差があるため、多少前後しても問題ありません。
生える前から「お口に触れる習慣」を始めておくのがポイントです。ガーゼで歯ぐきを優しく拭くことで、お口を触られることに慣れていき、スムーズに歯磨きへ移行できます。
歯磨きはむし歯予防だけじゃない!習慣化の本当の意味
赤ちゃんの乳歯は、大人の永久歯に比べてエナメル質が薄く、むし歯になりやすいという特徴があります。そのため、生え始めの段階から適切なケアを取り入れることが大切です。
しかし、歯磨きの目的はむし歯予防だけではありません。赤ちゃんの健やかな成長や、将来の歯の健康にも深く関わっています。
- 乳歯は永久歯の「道しるべ」
乳歯がむし歯になると、後から生える永久歯の位置や質に悪影響を及ぼす恐れがあります。 - 感覚の発達にも影響
口の中を触られる経験が少ないと、将来偏食や過敏反応の原因になる可能性もあります。 - ポジティブ体験が習慣化の第一歩
「歯磨きって気持ちいい」と感じる体験は、将来自分から歯を磨く意欲につながります。
赤ちゃんの健やかな成長と将来の健康を守るためにも、この時期から丁寧なケアを心がけることが大切です。
赤ちゃんの成長段階に合わせた歯磨きの進め方
赤ちゃんは日々成長し、発達段階によって口腔ケアの必要性や方法も変化していきます。そのため、歯磨きも赤ちゃんの成長に合わせて少しずつステップアップさせていくことが大切です。
歯が生える前(生後6~9カ月頃まで)
この時期はまだ歯が生えていませんが、お口のケアの準備期間として非常に重要です。
授乳やミルクの後に、清潔なガーゼを指に巻いて、赤ちゃんの歯ぐきや口内をやさしく拭いてあげましょう。これにより、口の中を清潔に保てるだけでなく、将来の歯磨きに備えてお口への刺激に慣れる練習にもなります。
また、頬や唇に触れながら行うスキンシップは、赤ちゃんとの信頼関係を育むことにもつながります。無理をせず、赤ちゃんが嫌がらない範囲で楽しい雰囲気をつくることがポイントです。
乳歯の生え始め(〜1歳頃)
下の前歯(乳中切歯)が生えてきたら、本格的な歯のケアを始めるタイミングです。
まずは、ガーゼやシリコン製の指ブラシで前歯を軽く拭くことからスタートしましょう。この部位は最初に生えてくることが多いため、特に丁寧なケアが求められます。
赤ちゃんが少しずつ慣れてきたら、ヘッドが小さく、毛先が柔らかい乳児用の歯ブラシへ移行します。最初は毛先を当てる程度から始め、慣れてきたら1本ずつ優しく磨いていきましょう。
この時期は唾液の分泌も活発で、汚れもつきにくいため、「楽しい」と感じられる経験を優先して、歯磨きに対する良い印象を育てていくことが大切です。
乳歯が生えそろうまで(1歳〜3歳頃)
1歳を過ぎると、奥歯(乳臼歯)が生え始め、食事も離乳食から幼児食へと進みます。この時期は、むし歯のリスクが高まるため、毎日の歯磨きを習慣化させましょう。
この頃からは、赤ちゃんに歯ブラシを持たせて「自分で磨く練習」を始めるのもおすすめです。大人と一緒に鏡の前で歯磨きをすることで、楽しい時間として習慣にしやすくなります。
ただし、赤ちゃんが自分だけで磨くとどうしても汚れが残りがちです。大人による仕上げ磨きはこの時期のむし歯予防に欠かせません。特に奥歯や噛み合わせの部分は食べカスがたまりやすいので、丁寧に磨いてあげましょう。
歯磨きは生活リズムに組み込むのがコツ
赤ちゃんは、決まったリズムで生活することで安心感を得られます。歯磨きも「食後」や「就寝前」など、毎日同じタイミングで行うことで自然と習慣になります。
また、赤ちゃんの機嫌が良い時間帯を選ぶと、スムーズにケアを進めやすくなります。歌を歌ったり、遊びを交えたりして、歯磨きの時間を楽しく演出することも効果的です。
生活リズムに合わせた歯磨き習慣は、無理なく続けられるだけでなく、将来的に赤ちゃん自身が自立してオーラルケアを行う力にもつながります。
赤ちゃんが歯磨きを嫌がるときの5つの対処法
赤ちゃんが歯磨きを嫌がるのは、決して珍しいことではありません。
大切なのは、無理に押し付けるのではなく、赤ちゃんの気持ちに寄り添いながら、少しずつ歯磨きを受け入れられるよう工夫することです。ここでは、実践しやすい5つの対処法をご紹介します。
1. 軽い力で手早く磨く
赤ちゃんは長時間口を開けていることに慣れていないため、歯磨きはできるだけ短時間で優しく行うことが大切です。
目安としては、歯ブラシの毛先が広がらない程度の軽い力で磨くのが理想です。嫌がる様子がある場合は、まず見えやすい前歯から磨き始め、徐々に奥歯へ移るとスムーズです。
短時間で済ませつつも丁寧にケアすることで、赤ちゃんも安心し、歯磨きを受け入れやすくなります。
2. 歯ブラシはこまめに新しいものに交換する
毛先が広がった歯ブラシは、赤ちゃんの敏感な口内を傷つけてしまう恐れがあります。毛羽立ったブラシは、歯ぐきや粘膜を刺激して痛みの原因になることも。
一般的に、歯ブラシは1か月ごとの交換が目安です。毛先の傷みや広がりが見られた場合は、早めに新しいものに替えましょう。
快適なブラシを使うことで、赤ちゃんのストレスを減らし、歯磨きを続けやすくなります。
3. 上唇小帯に歯ブラシを当てない
仕上げ磨きをするときに注意したいのが「上唇小帯(じょうしんしょうたい)」です。これは、上唇の裏側と歯ぐきをつなぐ筋のような部分で、ここに歯ブラシが当たると赤ちゃんは強い痛みや違和感を感じます。
その結果、歯磨きへの拒否反応が強くなることも。
上唇を軽く持ち上げ、視認しながら磨くことで接触を防げます。また、毛先が柔らかい歯ブラシを選ぶことで、不意の刺激を軽減できます。
4. 無理に押さえつけず、赤ちゃんのペースに合わせる
歯磨きの時間に、赤ちゃんを強く押さえつけたり、無理に口を開けさせたりすると、恐怖心を植えつけてしまう恐れがあります。
「歯磨き=怖いもの」と感じさせてしまうと、将来的にも歯磨きを嫌がるようになってしまいます。
嫌がったときは、一度時間を置いて機嫌のよいタイミングに再チャレンジするのがコツ。赤ちゃんの様子を見ながら、無理なく進めることを心がけましょう。
5. 歯磨きを“遊び”に変える工夫をする
赤ちゃんにとって「楽しいこと」は積極的に取り組みたくなるもの。歯磨きも、遊びの要素を取り入れることで前向きな習慣になります。
たとえば、以下のような工夫がおすすめです。
- 歯磨きの歌を歌いながらケアする
- 歯磨きがテーマの絵本を一緒に読む
- 大人が鏡の前で楽しそうに磨く姿を見せる
「〇〇ちゃんもやってみよう!」と声をかければ、赤ちゃんの“真似っこしたい気持ち”を引き出せるかもしれません。
こうしたポジティブな体験を積み重ねることで、歯磨きは自然と習慣化しやすくなります。
歯が生えはじめの赤ちゃんの歯みがきに関するよくある疑問

歯磨きについて、もっと詳しく知りたいと感じているママやパパのために、赤ちゃんの歯磨きに関する代表的な疑問とその答えをわかりやすくまとめました。
Q. 赤ちゃんの歯ブラシはどう選べばいい?
赤ちゃんの歯ブラシは、成長段階に応じた適切なタイプを選ぶことが大切です。
-
生え始めの時期(生後6カ月頃〜)
歯ぐきへの刺激が少ない、シリコン製の指歯ブラシやガーゼタイプがおすすめです。お口のケアに慣れる“練習用”として最適です。 -
1歳頃〜奥歯が生えてきたら
ヘッドが小さく毛先がやわらかい、赤ちゃん専用の歯ブラシを使いましょう。持ち手が太く、握りやすいものや、喉突き防止のストッパー付きの製品を選ぶとより安心です。 -
仕上げ磨き用の歯ブラシ
前歯2本分ほどの小さめヘッドで、毛が短くやわらかいタイプがおすすめ。細かい部分まで丁寧に磨けます。
※赤ちゃん用の歯ブラシは毛先が広がりやすいため、1か月ごとを目安に交換しましょう。毛先に広がりや傷みが見られた場合は、早めの交換が必要です。
Q. 歯みがき剤はいつから使える?
乳歯が生え始めたタイミングから、赤ちゃん専用の歯みがき剤を使い始めることができます。とくに、いちごやぶどうなどの味付きタイプは、赤ちゃんが歯みがきを「楽しいもの」として受け入れやすくなるため、はじめての歯みがきにはおすすめです。
成分に関しては、食品用原料で作られているものを選ぶと、万が一飲み込んでしまった場合でも安心です。使用量を守りながら、安全な成分のものを選ぶことがポイントです。
また、2~3歳頃になり、「ぶくぶくうがい」ができるようになったら、低刺激の大人用歯みがき剤への切り替えを検討することも可能です。
その際は、以下に注意しましょう。
舌や口内が敏感な時期のため、研磨剤・発泡剤を含まないやさしい処方を選ぶ
フッ素濃度は2歳未満なら500ppm以下が推奨されています
正しい濃度と成分の歯みがき剤を使うことで、効果的にむし歯予防ができます。
Q. 歯みがき剤を飲み込んでしまっても大丈夫?
赤ちゃん専用の歯みがき剤の多くは、食品用の安全な成分で作られているため、少量であれば飲み込んでも問題はありません。
ただし、適量を守ることが大切です。使用量の目安は、歯ブラシの先に米粒程度。甘味料や香料が強すぎない製品を選ぶと、赤ちゃんが歯みがき剤を過剰に好んでしまうリスクを減らせます。
親御さんがしっかり見守りながら使うことで、安全に歯みがき習慣を身につけることができます。
Q. 仕上げみがきはいつまで必要?
仕上げみがきは、小学校高学年ごろまで続けることが望ましいとされています。
特に、小学校低学年(1~3年生)の間は、手先の器用さや注意力がまだ未熟なため、どうしても磨き残しが多くなりがちです。保護者による仕上げみがきが、むし歯予防の重要なポイントになります。
もっとも効果的なタイミングは就寝前。この時間帯は唾液の分泌が減少し、むし歯菌が活発になるため、寝る前のケアはとても重要です。
仕上げみがきを習慣にすることで、子どもが成長してからもオーラルケアへの意識が育ち、一生役立つ習慣として定着しやすくなります。
赤ちゃんの歯磨きは生え始めからやさしくスタート
赤ちゃんの歯磨きは、乳歯が生える前の段階からの“やさしい準備”がポイントです。お口の中に触れることに慣れさせながら、成長に合わせてケアの方法をステップアップしていくことで、むし歯予防だけでなく、歯ぐきの健康維持や将来の歯科健診へのスムーズな移行にもつながります。
赤ちゃんが歯磨きを嫌がるときは、無理に押しつけるのではなく、歌や絵本などの遊びの要素を取り入れながら、楽しい雰囲気づくりを心がけましょう。「歯磨き=いやなもの」とならない工夫が、自然な習慣化の第一歩になります。
また、歯ブラシの選び方や歯みがき剤の使い始めのタイミングなど、迷うことがあれば、かかりつけの歯科医に相談するのが安心です。ママやパパが日々のケアを通して赤ちゃんのお口の健康を守ることは、健やかな成長を支える大切なサポートになります。
赤ちゃんの歯磨きに不安がある方へ|歯科の専門家に相談できる「mamoru」
「歯が生え始めたけど、このタイミングでのケアは合ってる?」
「仕上げ磨きやフッ素の使い方、誰かに確認したい…」
そんな不安を感じているママ・パパにおすすめなのが、無料で歯科医師に相談できるオンラインサービス「mamoru」です。赤ちゃんのお口に関する悩みを、専門の歯科医師がわかりやすくアドバイス。
- 歯の生え始めのケア方法
- 歯みがき剤の選び方や使用時期
- 歯ブラシの種類や交換頻度
- 仕上げ磨きのコツ など
初めての歯磨きに迷う保護者の方にとって、確かな専門家のアドバイスがあるだけで、安心感がぐっと増します。
赤ちゃんの大切な乳歯を守るために、正しいケアを自信を持って続けるために、ぜひ「mamoru」を活用してみてください。