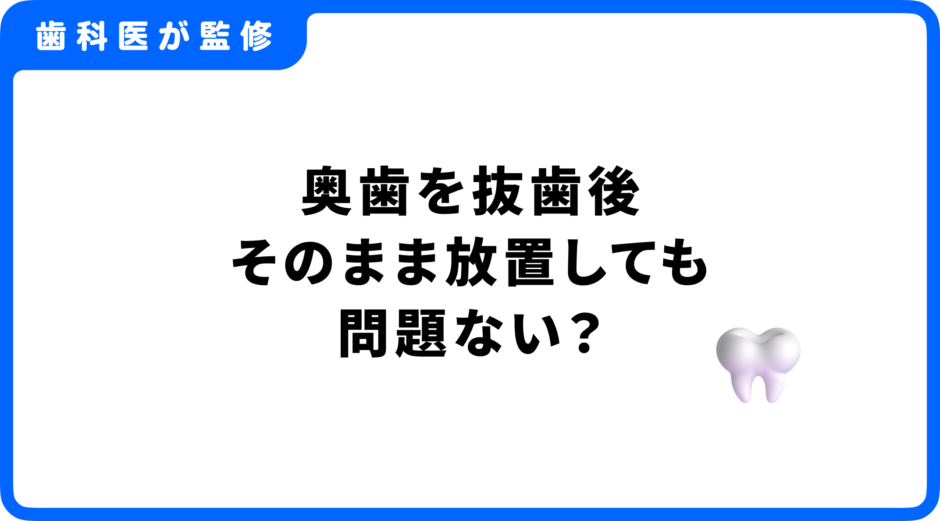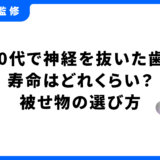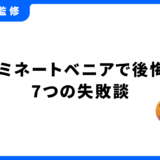「奥歯を抜いたけれど、痛みもなくなったし、このまま放っておいて問題ないかな…」
そう思って、奥歯を抜歯後に放置してしまう方は少なくありません。
しかし、奥歯の抜歯をそのままにしておくと噛み合わせの崩れや歯並びの乱れを引き起こし、全身の健康にまで悪影響を及ぼすリスクがあります。
本記事では、「奥歯の抜歯後にそのままにしても問題ない?」という疑問に、歯科医師の視点から回答します。
- 奥歯を抜歯したままにして放置することによる具体的な悪影響
- 奥歯を抜歯後の治療法(インプラント・ブリッジ・入れ歯)
などをわかりやすく解説します。後悔しないためには抜歯後の影響について正しく理解し、自分に合った対応を考えていきましょう。
奥歯を抜歯後そのまま放置しても問題ない?
結論から言えば、奥歯を抜いたまま放置するのは望ましくありません。
抜歯後に痛みがなくなったとしても、奥歯が果たしていた重要な役割を失うことで、口の中や全身の健康にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。
奥歯は「噛むための歯」という役割にとどまらず、歯並び全体のバランスを保ち、顔貌・顎関節の安定にも深く関わっているのです。
たとえば、大臼歯(6番・7番)を失うと、噛み合わせが乱れて前歯が出てきたり、隣接する歯が倒れてきたり、二次的な問題が起こります。
さらに、咀嚼機能が低下することで、食事から摂取できる栄養バランスにも影響を及ぼすケースがあります。
奥歯がないことによる悪影響を放置すればするほど、治療は複雑かつ高額になる傾向があります。早めに補綴(ほてつ)治療を行うことが重要です。
「時間がない」「今は違和感がないから大丈夫」と思わず、なるべく早く歯科医師の診療を受けましょう。
奥歯の役割とは
人間の奥歯(小臼歯、大臼歯)は上下左右に4本ずつ、計16本(親知らずを含めると最大20本)あります。奥歯(大臼歯)の役割は前歯とは異なり、「食べ物をすり潰す」という重要な機能を担っています。
中でも、6番の歯(第一大臼歯)と7番の歯(第二大臼歯)は、咀嚼において最も重要です。
これらの奥歯は食事に必要な噛む力の大部分を担っているため、1本抜けてなくなるだけでも、残りの歯に大きな負担がかかってしまうのです。
奥歯には他にも、以下のような複数の役割があります。
- 咀嚼機能の中心を担う:
食べ物を細かくすり潰し、消化を助ける - 噛み合わせを安定させる:
上下左右の歯のバランスを保つ - 歯の周りの組織を保持する:
噛む力が歯に伝わることにより歯を囲む骨の吸収を抑制する - 隣接歯の位置を保つ:
歯が倒れたり移動したりするのを防ぐ
奥歯は、口の中全体の構造と機能を支える土台とも言える存在です。1本でも抜けたままにしておくと、全体のバランスが崩れ、治療がより複雑になるおそれがあります。
奥歯について詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。
奥歯を抜歯後そのままにすると起こる7つの悪影響
本章では、奥歯を抜歯後にそのまま放置した場合に起こり得る、7つの悪影響について解説します。
噛む力が弱まり、咀嚼機能が低下する
奥歯を失うと、食べ物を十分に噛めなくなり、咀嚼機能が著しく低下します。
奥歯は、上下のバランスをとりながら硬いものをすり潰します。そのため、抜歯後に奥歯がないまま放置すると、噛む力が衰え、消化器官にも負担がかかる可能性も。
とくに高齢者は、咀嚼力の低下が栄養不良を引き起こし、全身の健康状態が悪化することが懸念されます。また、噛みにくいため柔らかい食べ物ばかり選ぶようになり、食事が偏るのもデメリットの一つです。
歯並びが悪くなる
奥歯を抜いたまま放置すると、隣接する歯や噛み合う歯が動き出し、歯並び全体が崩れる可能性があります。
歯は互いに支え合うことで正しい位置を保っています。奥歯が抜けて空いたスペースがあると、空間に向かって隣の歯が倒れたり、対合する歯がせり出してきたりする(挺出する)ことで、噛み合わせがズレてくるのです。
歯並びの乱れを放置すると、見た目に影響が出るのはもちろん、ブリッジやインプラントなどの治療の難易度は上がっていきます。歯並びが乱れると歯磨きがしにくくなり、虫歯や歯周病リスクも高まります。
顔の形がゆがむ
多数の奥歯を失うことで、頬がこけたり顎のラインが変化したり、顔貌に影響が及ぶ可能性もあります。
奥歯は、顔の筋肉や骨格の位置を維持する役割も担っています。抜歯後に長期間放置すると、顎骨の吸収(骨がやせる現象)が進み、顔の左右に差が出て老けた印象になるかもしれません。
とくに上下の奥歯が同時に抜けた場合、噛み合わせの高さ(咬合高径)が低下し、口元がすぼんで見えることもあります。
美しさや若々しさを保つ審美面でも、奥歯の喪失による悪影響は軽視できません。奥歯を失った後は、補綴(ほてつ)治療を行うことで自然な見た目を保てます。
口臭が悪化する
歯を失った部分は、長期間放置すると隣接する歯の位置が変わったり歯茎が陥没したりして、歯ブラシが届きにくくなります。
その結果、プラーク(歯垢)や食べかすがたまりやすくなり、口臭や炎症を引き起こす可能性があります。
噛む回数が減って唾液分泌が低下し、口の中の自浄作用が弱まることも、口臭が悪化する一因です。
口臭はエチケットとしても気になる問題。抜歯後はそのままにせず、入れ歯やインプラント、ブリッジなどの治療を行うことが推奨されます。
顎関節へ悪影響を及ぼす
奥歯がないことで噛み合わせのバランスが崩れ、顎関節に負担が集中します。
咀嚼時に力をうまく分散できないため、下顎の動きに無理が生じ、顎関節症(顎の痛み・音・開閉口の異常など)を引き起こす可能性があります。
顔の一方だけで噛む「偏咀嚼」の癖がつくと、左右の筋肉のアンバランスや、首・肩のこりなど全身の不調にも波及することも。
「奥歯1本なくなっただけ」と捉えず、顎関節や全身の健康まで視野に入れて考えなければなりません。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
歯を失った部分の周囲は歯磨きなどのケアがしにくいため、細菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
奥歯が抜けると、隣接する歯が傾くなど歯並びの影響もあり、歯と歯の間に隙間ができてブラッシングが難しくなります。その結果プラークがたまりやすくなり、虫歯や歯周病の温床になるのです。
さらに、噛む力の偏りが残存歯に過剰な負担をかけることで、他の歯の根にひびが入ったり、知覚過敏を招いたりするリスクもあるでしょう。
生活習慣病や認知症リスクが高まる
近年の研究では、奥歯の喪失と全身疾患との関連が指摘されるようになってきました。
食べ物を十分に噛めないことで、食生活が糖質に偏るなど栄養バランスの乱れが起こりやすくなり、生活習慣病(糖尿病・高血圧など)のリスクが上昇します。
また、咀嚼刺激の減少は脳への血流低下につながり、認知症の進行リスクを高める可能性も報告されています。
これは高齢者だけの問題ではありません。中年層にも十分にリスクがあり、無視できない問題です。全身の健康管理として、奥歯の治療を検討すべきでしょう。
奥歯を抜歯後の治療
奥歯を抜いた後はそのままにしておくのではなく、早期に補綴(ほてつ)治療を受け、抜けた奥歯を補うことが重要です。治療方法としては、「インプラント」「ブリッジ」「部分入れ歯」の3つが代表的です。
それぞれの治療法にはメリットやデメリット、費用、治療期間など違いがあります。本章では、代表的な補綴治療の特徴について一つずつ解説します。
インプラント
インプラントは、人工の歯根(チタン製)を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。
他の歯に負担をかけず、機能と見た目を回復できるのが最大の特長と言えるでしょう。天然歯に近い噛み心地と審美性を備え、咀嚼力も回復しやすいため、「第二の永久歯」と呼ばれることがあります。
インプラントの主なメリットは以下の通りです。
一方で、治療期間が長い点や、保険適用外のため費用が高額になる点はデメリットです。また、顎の骨の量が不足している場合や、全身疾患を抱える方は治療の適応外となることもあります。
インプラントを希望する場合は、CT診断を含む精密検査が必要です。歯科医院へ早めの診療予約をおすすめします。
ブリッジ
ブリッジは、抜けた歯の両隣の歯を削って支台にし、連結した人工歯を橋のようにかける治療方法です。
保険適用で実施できるケースが多く、治療期間が比較的短く済むのが特長です。また、固定式であるため違和感が少なく、咀嚼もしやすいというメリットがあります。
ただし、ブリッジのデメリットとしては以下の点が挙げられます。
また、歯の欠損部分に食べ物が詰まりやすいため、歯磨きなど丁寧なデンタルケアが必要です。定期的に歯科医院でメンテナンスを行うことで、長期使用が可能になります。
部分入れ歯(義歯)
部分入れ歯は、金属や樹脂で人工歯と歯茎を模した床(しょう)を作り、残存歯にバネ(クラスプ)で固定する治療法です。
多くの場合保険診療が可能であり、治療期間が短く、手術の必要がない点が大きな利点です。高齢者や全身疾患がある人など、外科処置が難しい場合でも有力な選択肢となります。
一方で、以下のような注意点もあります。
最近では目立ちにくいノンクラスプデンチャー(歯茎に近い色合いの義歯)など、審美性に優れた義歯も選べます。ただし保険適用外です。
奥歯を抜歯した後の注意点
奥歯を抜いた直後は、回復スピードや予後に関わる重要なタイミング。術後の過ごし方やケア方法を誤ると、感染やドライソケット(痛みが続く状態)などのトラブルを招くおそれがあります。
ここでは、奥歯を抜歯後の基本的な注意点について解説します。
うがいや歯磨きは優しく行う
抜歯直後に強いうがいや激しい歯磨きをすると、治癒を妨げる原因になるため注意しましょう。
奥歯を抜いた後は、傷口に「血餅(けっぺい)」と呼ばれる血の塊ができ、かさぶたのように患部を守ってくれます。
しかし、ブクブクと強くうがいをしたり歯ブラシで直接触れたりすると、血餅が剥がれてしまい、治癒の遅れやドライソケット(抜歯した穴の骨が露出し強い痛みを伴う)になるリスクがあります。
術後24時間のデンタルケアは、以下の点を心がけて行います。
抜歯後の患部は非常にデリケートです。とにかく優しく扱うことが、傷の早期回復に直結します。
安静に過ごす
奥歯を抜歯した当日から数日間は、無理をせず安静に過ごしましょう。
とくに抜歯直後は、血行や免疫の変化が、出血・腫れ・感染の原因となります。過ごし方に注意が必要です。
抜歯直後に控えるべき行動として、以下のようなものがあります。
とくに飲酒は、血管を拡張させるため止血が困難になり、再出血のリスクを高めます。
喫煙も、血流を悪化させることで、治癒を著しく遅らせるでしょう。喫煙者は、ドライソケット(強い痛みと治癒遅延を伴う状態)を発症するリスクが非喫煙者よりも有意に高いと報告されています。
最低でも抜歯後2〜3日は禁煙・禁酒が推奨されており、可能であれば傷が完全に治るまでは控えるべきです。「少しぐらいなら大丈夫」と油断せず慎重に過ごすことが、感染や合併症を防ぐ最善策です。
処方薬を正しく服用する
術後に処方された薬は、自己判断で中断せず、指示どおりに服用してください。
歯科医院では一般的に、抜歯後の炎症や感染を防ぐため、抗生物質や鎮痛剤を処方します。奥歯の場合、治癒に時間がかかる傾向があるため、薬の効果を最大限活かして治癒を待つことが重要です。
処方薬の服用について注意すべきポイントは以下のとおりです。
また、処方薬の服用と並行して患部の清潔を保つことも、回復の促進につながります。
医師の指導の通りに過ごすことで、苦しいトラブルを回避しましょう。
奥歯の抜歯後に関するよくある質問
奥歯を抜歯したあと、「いつ治療を始めればいいのか?」「放置していても大丈夫か?」などの疑問を持つ方は少なくありません。
ここでは、奥歯の抜歯後に関する3つの質問に対して、歯科医師の視点から回答します。
抜歯後の治療はいつから始めるべき?
結論として、抜歯後の治療(インプラント・ブリッジ・義歯など)は、歯茎と骨の回復を確認したうえで、おおよそ1か月以内に始めるのが理想的です。
すぐに治療を始めない理由は、抜歯後の傷口が完全に治るまでには時間がかかるためです
一方で、治療開始が遅れすぎると、骨が痩せたり歯並びが崩れたりして治療が難しくなる場合があります。
一般的に、理想的な治療開始までの流れは、以下のようになります。
- 抜歯から1〜2週間で消毒・経過観察
- 1か月後に歯茎と骨の状態をレントゲンや触診で確認
- 問題がなければ、補綴治療の選択と設計に進む
歯科医師と共に経過を見ながら、治療計画を組んでもらいましょう。
インプラント治療を希望する場合、骨量や全身状態の評価が必要となるため、早めに相談しておくと安心です。
抜歯後長期間が経過してから治療を始めても大丈夫?
抜歯から時間が経っていても治療は可能ですが、「しばらくそのままにしても問題ない」わけではありません。
たとえ痛みや違和感がなくとも、見えないところで顎の骨が吸収され、歯並びや噛み合わせが変化している可能性があります。
とくに奥歯(大臼歯)のように咀嚼力がかかる部位を放置すると、噛む力の偏りが他の歯にダメージを与え、将来的に大きなトラブルを引き起こすことも。
放置していた期間が長いほど、治療の難易度は高くなり、治療期間や費用もかさみます。
まずは現状を正確に評価するため、CT撮影や口腔内スキャンなどによる精密診査から始めてみましょう。
「6番」や「7番」の奥歯はいらないって本当?
いいえ、6番・7番の奥歯は「いらない歯」とは言えません。非常に重要な役割を担っており、なくては困る歯です。
特に6番(第一大臼歯)は、6歳頃に最初に生える永久歯であり、噛み合わせの軸となる極めて大切な歯です。これが失われると、噛み合わせ全体が不安定になり、左右のバランスや顎関節にも悪影響が及ぶ可能性があります。
また、7番(第二大臼歯)は、6番と協力して硬い食べ物をすり潰す重要な咀嚼機能を担う存在です。「親知らず(8番)があれば大丈夫」と思うかもしれませんが、親知らずは正常な位置に生えていない場合も多く、6番や7番の代替にはなりません。
| 歯の番号 | 役割・特徴 | 重要性 |
| 6番(第一大臼歯) | 噛み合わせの軸・噛む力の支点 | 極めて高い |
| 7番(第二大臼歯) | 咀嚼の補助・左右バランスの安定 | 極めて高い |
| 8番(親知らず) | 生え方に個人差あり・予後不良も | 低い(歯の状態によっては移植などに使える場合があります) |
つまり、6番や7番を抜歯した後、歯がないまま放置してしまうことは、長期的に大きな問題を引き起こす可能性があります。
どの歯にもそれぞれの「役割」があるため、歯を失った際は必ず歯科医師と治療方針を相談しましょう。
親知らずについて詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。
まとめ|奥歯を抜いたままは危険。早めの対応を
奥歯を抜歯したまま放置すると、噛み合わせの乱れや咀嚼機能の低下、顎関節や全身への悪影響につながるおそれがあります。
とくに6番・7番の大臼歯は重要な役割を持つため、歯がなくなったままにせず、早期にインプラントやブリッジ、義歯などの治療法を検討することが大切です。
治療にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、歯科医師と相談しながら自分に合った方法を決めましょう。
不安なまま放置せず、まずは歯科医院での診察やカウンセリングを受けてみてください。