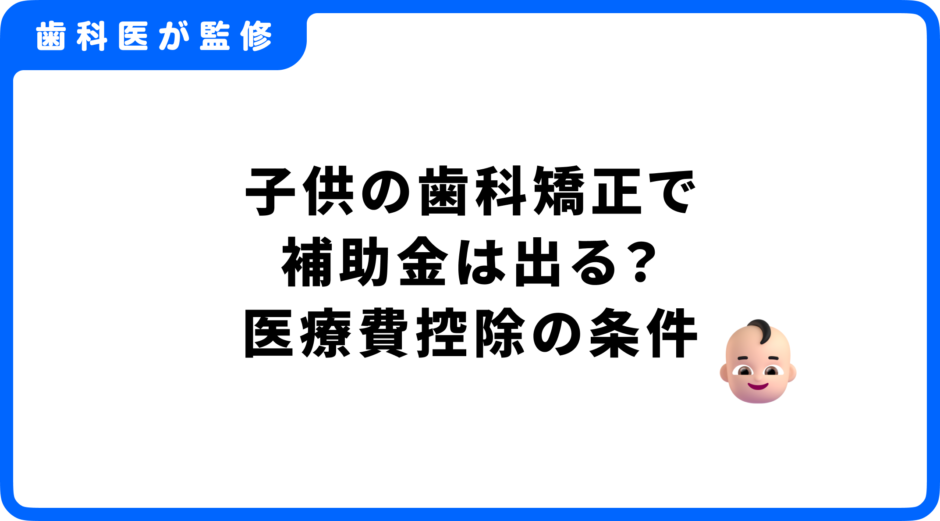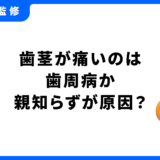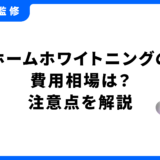お子様の歯並び、成長とともに気になってきますよね。
「早めに矯正治療を受けさせてあげたいけれど、やっぱり費用が心配…」
「子供の歯科矯正に補助金や助成制度って使えないの?」
そんなお悩みをお持ちの保護者の方へ。
残念ながら、現在、国が主体となる子供の歯科矯正に特化した「補助金」制度は原則として存在しません。
しかし、「医療費控除」という制度を利用でき、治療費の負担を軽減できる可能性が高いのです。
さらに、お住まいの自治体独自の助成制度や、治療内容によっては保険適用となるケースもあります。
この記事では、子供の歯科矯正における費用の不安を解消するため、
- 医療費控除の対象となる条件や申請方法
- 保険適用となる具体的な症例
- 知っておきたい費用を抑えるポイント
などを、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
▶関連記事:ワイヤー矯正の値段はいくら?種類別・装置別の費用相場と内訳を徹底解説
▶関連記事:【歯科医監修】マウスピースによる歯列矯正の効果は?適用症例や費用、注意点を徹底解説
【結論】子供の歯科矯正に使える「補助金」は原則ない!でも、費用負担を軽くする方法はあります
まず結論からお伝えすると、お子様の歯科矯正を対象とした国からの直接的な「補助金」制度は、残念ながらありません。
「やっぱり高額な費用は自己負担か…」とがっかりされるかもしれませんが、どうかご安心ください。
費用負担を大きく軽減できる、もっと身近で重要な制度があります。それが「医療費控除」です。
これは、支払った医療費の一部が税金の還付という形で手元に戻ってくる制度で、お子様の矯正治療のうち、咬合機能の改善など医療的目的がある場合は、医療費控除の対象となる可能性が高いです。
他にも、お住まいの自治体独自の助成や、治療内容によっては保険適用となるケースも。諦める前に、これらの制度を一つずつ確認していきましょう。
【重要】補助金よりメリット大!ある条件を満たせば小児矯正で使える「医療費控除」とは?
医療費控除は、お子様の矯正治療を考える上で、補助金以上に重要で、多くの方が利用できる制度です。
これは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税が軽減される仕組みです。
なぜ小児矯正が対象になるかというと、大人の美容目的の矯正とは異なり、「発育段階にある子供の、健やかな成長を促すために必要な治療」と認められるためです。
例えば、以下のような機能的な問題を改善する治療が該当します。
- 噛み合わせが悪く、しっかり噛めない(咀嚼機能の改善)
- 発音がしづらい(発音障害の改善)
- 顎の健全な成長のサポート
生計を同じくするご家族の医療費も合算でき、デンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払った費用も対象になります。
申請には領収書が必須ですので、必ず大切に保管しておきましょう。
お住まいの地域をチェック!自治体独自の「助成制度」が存在する場合も
国の制度とは別に、お住まいの自治体(都道府県や市区町村)が、独自に子育て支援の一環として助成制度を設けている場合があります。
よく知られているのが「乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)」です。
これは、保険診療の医療費における自己負担分を助成する制度です。
そのため、顎変形症などで保険適用の矯正治療を受ける場合には、この制度を利用できる可能性があります。
ただし、注意点がいくつかあります。
- 対象となる年齢や保護者の所得制限は、自治体ごとに異なります。
- 審美目的の自由診療となる矯正治療は、原則として対象外です。
全ての自治体で矯正治療への助成があるわけではありませんが、一度確認してみる価値はあります。
お住まいの市区町村のホームページで調べるか、役所の担当窓口(子育て支援課など)に「子どもの歯科矯正で使える助成制度はありますか?」と問い合わせてみましょう。
うちの子は対象?医療費控除が認められる矯正治療・認められない治療
「うちの子の矯正は、医療費控除の対象になるの?」これは、保護者の方が最も知りたいポイントですよね。
結論から言うと、判断の基準は「治療の目的」にあります。
国税庁の指針でも、「発育段階にある子供の健全な成長を阻害しないようにするために行う、不正咬合の歯列矯正」は対象になると明記されています。
一方で、純粋に容姿を美しく見せるための審美目的の矯正は対象外です。
言葉だけでは少し分かりにくいかもしれません。
具体的にどのようなケースが「治療」と見なされ、どのようなケースが「審美」と判断されるのか、詳しく見ていきましょう。
【対象になる】発育・機能改善を目的とした小児矯正
お子様の矯正治療が、以下の「機能的な問題を改善」することを目的としている場合、それは医療行為と見なされ、医療費控除の対象となります。
なぜなら、それらの問題を放置すると、お子様の健やかな成長や将来の健康に悪影響を及ぼす可能性があるからです。
<医療費控除の対象となる症例の例>
- しっかり噛めない・食べにくい(咀嚼機能の障害)
- 特定の音が発音しにくい(発音機能の障害)
- 顎の成長に悪影響が出ている
- 将来の虫歯・歯周病リスクが高い
歯並びが悪く、食べ物をうまく噛み砕けない状態。消化不良や顎の発達不全につながる恐れがあります。
「サ行」や「タ行」などが、歯の隙間から息が漏れることで正しく発音できない状態。
例えば、受け口(反対咬合)や出っ歯(上顎前突)などを放置することで、上下の顎の骨格バランスが崩れてしまうケース。
歯が複雑に重なり合っていることで歯磨きが難しく、歯科医師が将来的に口腔疾患のリスクが高いと判断した場合。
これらの治療は、お子様の成長に必要な医療行為です。
診断書の提出は必須ではありませんが、歯科医院からの領収書に「歯列矯正(不正咬合治療)のため」といった記載があると、よりスムーズでしょう。
【対象にならない】見た目をきれいにする審美目的の矯正
一方で、機能的な問題がなく、純粋に「見た目を良くしたい」という審美(美容)目的の矯正治療は、残念ながら医療費控除の対象外となります。
例えば、「噛み合わせや発音に問題はないけれど、わずかにねじれている前歯をまっすぐにしたい」といったケースがこれに該当します。
これは病気を治す「治療」ではなく、容姿を整えるための「美容」と判断されるためです。
ただし、これは非常に重要なポイントですが、子供の矯正(小児矯正)が「純粋な審美目的」と判断されることは、実際にはほとんどありません。
なぜなら、子供の矯正は見た目を整えるだけでなく、顎の骨格の成長を正しい方向へ導くという、極めて機能的な側面を併せ持つからです。
そのため、大人の矯正と比べて、医療費控除の対象として認められやすい傾向にあります。
それでも心配な場合は、カウンセリングの際に歯科医師へ「この治療は医療費控除の対象になりますか?」と一言確認しておくと、安心して治療と手続きを進められます。
【保険適用】になる子供の歯科矯正とは?先天性の疾患などが対象
原則として全額自己負担の自由診療となる歯科矯正ですが、ごく例外的に健康保険が適用されるケースがあります。
これは、お子様が生まれつき特定の疾患を抱えており、それが原因で噛み合わせに異常が生じている場合です。
具体的には、厚生労働省が定める先天性の疾患などがこれに該当します。
ただし、保険を使って治療を受けるためには、どの歯科医院でも良いわけではありません。
都道府県から認可を受けた「指定自立支援医療機関」や「顎口腔機能診断施設」といった、専門の医療機関で診療を受ける必要があります。
対象となる厚生労働省指定の疾患(顎変形症など)
保険適用となる矯正治療の代表的な症例が、「顎変形症(がくへんけいしょう)」です。
これは、上下の顎の骨格が大きくずれていることで、受け口や出っ歯、顔の非対称などが生じている状態を指します。
歯を動かすだけの矯正治療では改善が難しく、顎の骨を切る外科的な手術を併用する必要があると医師に判断された場合に、保険診療の対象となります。
その他にも、保険が適用される疾患として、厚生労働省は以下のようなものを定めています。
▼保険適用となる疾患の例
- 唇顎口蓋裂
- ダウン症候群
- クルーゾン症候群
- ターナー症候群
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- (その他、日本矯正歯科学会が定める約60の先天性疾患)
これらの診断は、専門の歯科医師でなければできません。
お子様の歯並びが単なる歯列の問題ではなく、「顎の骨格に原因があるのかもしれない」と感じたら、まずは矯正歯科や大学病院の口腔外科で一度相談してみることを強くお勧めします。
高額療養費制度も利用できる可能性
もし、お子様の矯正治療が保険適用となった場合、もう一つ知っておくべき心強い制度があります。
それが「高額療養費制度」です。
これは、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。
医療費控除が、年末調整や確定申告によって「税金が安くなる」制度であるのに対し、高額療養費制度は、加入している健康保険(健康保険組合や協会けんぽなど)から直接的にお金が払い戻されるという違いがあります。
自己負担の上限額は、ご家庭の所得や年齢によって異なりますが、顎変形症の手術などで高額な医療費がかかった場合でも、家計の負担を大きく軽減することができます。
保険適用の治療を受ける際には、この制度も併せて利用できることを覚えておきましょう。
詳しくは、ご自身が加入されている健康保険の窓口へ問い合わせてみてください。
【実践編】医療費控除の申請方法と流れを分かりやすく解説
「医療費控除」で費用の負担を軽くできると分かったら、次は具体的な申請手続きです。
医療費控除を受けるには、年に一度の「確定申告」が必要になります。会社員で年末調整をしている方でも、ご自身で申告手続きを行う必要があります。
「確定申告なんてやったことないし、手続きが難しそう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。
今は国税庁の便利なシステムもあり、ポイントさえ押さえれば、誰でもスムーズに申請できます。
ここでは、必要書類から申請の流れ、注意点まで、順を追って分かりやすく解説します。
計算方法は?「支払った医療費 – 10万円」が基本
まずは、ご自身の医療費控除額がいくらになるのか、把握しておきましょう。計算方法はとてもシンプルです。
医療費控除額(最高200万円)=(1年間に支払った医療費の合計)-(保険金などで補てんされた金額)- 10万円
(注)その年の総所得金額が200万円未満の人は、「10万円」の部分が「総所得金額の5%」になります。
例えば、お子様の矯正治療費として1年間に80万円を支払い、他に医療保険などからの給付金がなかったとします。その場合の医療費控除額は、
80万円(医療費) - 0円(補てん額) - 10万円 = 70万円
となります。
ここで注意したいのは、「70万円」がそのまま戻ってくるわけではない、という点です。 実際に還付される税金の額は、この医療費控除額に、ご自身の所得税率を掛けた金額が目安となります。
還付金額の目安(年収に対する所得税率と還付金のシミュレーション) |
| 課税所得金額 | 所得税率 | 還付金の目安 |
| 195万円以下 | 5% | 35,000円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 70,000円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 140,000円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 161,000円 |
このように、所得が高い方ほど、還付される金額は大きくなります。
【5ステップで完了】確定申告の必要書類と申請の流れ
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に、前年1年間の所得と税金を計算し、税務署に申告します。
医療費控除申請の5ステップ
- 必要書類を揃える
- 「医療費控除の明細書」を作成する
- 確定申告書を作成する
- 税務署に提出する
- 還付金の入金を待つ
まずは手元に以下のものを準備しましょう。
医療費の領収書原本:
歯科医院の領収書は必須です。1年間分をまとめて保管しておきましょう。
通院にかかった交通費のメモ:
電車やバスなど、公共交通機関の交通費も対象です。日付、交通手段、運賃を記録しておきましょう(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)。
源泉徴収票:
会社員の方は、年末に勤務先から受け取ります。
マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
還付金を受け取る銀行口座の情報
(デンタルローンを利用した場合)ローンの契約書の写し
国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードし、領収書を見ながら支払った医療費を転記していきます。
現在は領収書の提出は不要ですが、5年間の自宅保管義務があります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最も簡単でおすすめです。
画面の指示に従って源泉徴収票の内容や医療費控除額などを入力するだけで、自動で税金を計算し、申告書を作成してくれます。
作成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
e-Tax(電子申告):マイナンバーカードと対応スマートフォン(またはICカードリーダライタ)があれば、自宅からオンラインで完結でき、最も便利です。
郵送:管轄の税務署へ郵送します。
持参:管轄の税務署の窓口へ直接提出します。
申告手続き完了後、約1ヶ月~1ヶ月半ほどで、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
e-Taxで提出した方が、早く入金される傾向にあります。
子供の歯並びが気になったら、まずは信頼できる歯科医院に相談しよう
ここまで、お子様の歯科矯正に関わる費用の制度について詳しく解説してきました。
医療費控除などを利用すれば、負担を大きく軽減できるとご理解いただけたかと思います。
しかし、これらの制度以上に最も大切なことがあります。
それは、「お子様に本当に矯正治療が必要か、いつ始めるのが最適か」を、専門家である歯科医師に正しく判断してもらうことです。
小児矯正は、大人の矯正にはない多くのメリットがあります。費用への不安が少しでも軽くなった今、ぜひ次の一歩として、信頼できる矯正歯科のカウンセリングを受けてみましょう。
なぜ早期の相談が大切?知っておきたい小児矯正のメリット
小児矯正の最大のメリットは、お子様の顎の「成長」を利用しながら治療を進められる点にあります。
特に、乳歯と永久歯が混在する時期に行う「一期治療」には、以下のような大きな利点があります。
小児矯正(一期治療)の主なメリット
- 顎の成長をコントロールできる
- 将来的な抜歯の可能性を減らせる
- 指しゃぶりなどの癖を改善できる
- 心理的な負担を軽くする
- 治療期間や費用の負担を軽減できる
顎の骨格のバランスを整え、永久歯が正しく生え揃うためのスペースを確保しやすくなります。
小児矯正により、将来的に抜歯を避けられる可能性があると示唆する研究もあります。
歯並びに悪影響を与える指しゃぶりや舌の癖などを、装置を使って改善に導くことができます。
見た目のコンプレックスが解消されることで、お子様の自信につながります。
一期治療で土台を整えておくことで、本格的な矯正(二期治療)が不要になったり、期間が短縮されたりするケースがあり、結果的に総額の費用を抑えられる可能性があります。
矯正治療を始めるのに最適な時期は、お子様の歯並びや顎の状態によって一人ひとり異なります。
早期に相談することで、最も効果的なタイミングで治療を始めることができます。
不安なことは専門家に聞くのが一番! mamoruで気軽に相談してみませんか?
「費用のことは分かったけど、いきなり歯科医院に予約して行くのはまだハードルが高い…」
「もっと気軽に、うちの子のケースについて専門家の意見を聞いてみたい」
そのようにお考えの方には、オンラインで歯科医師に相談できるサービス「mamoru」がおすすめです。
「mamoru」を使えば、ご自宅にいながら、 「うちの子の歯並びは、本当に矯正が必要?」 「もし治療するなら、費用は総額でどれくらいかかりそう?」 といった、保護者の方が抱える具体的な悩みや不安を、専門の歯科医師に直接相談することができます。
まずはオンラインで相談し、費用や治療に関する不安を解消したうえで、納得して歯科医院選びに進む。そんな新しいステップを踏んでみませんか。
お子様の大切な歯の健康を守る、信頼できる第一歩として。ぜひ「mamoru」をご活用ください。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。
子供の歯科矯正と費用に関するよくある質問
ここでは、お子様の歯科矯正と医療費控除に関して、保護者の方が抱きがちな、より具体的で細かい疑問についてQ&A形式でお答えします。
Q. 医療費控除は、所得が多い方の家族(夫か妻かなど)が申請した方がお得ですか?
A. はい、その通りです。
一般的に、ご家族の中で最も所得金額が高い(=所得税率が高い)方が申請するのが最もお得になります。
医療費控除によって実際に戻ってくる還付金の額は、「医療費控除額 × 所得税率」で計算されます。
所得税率は、所得が高いほど高くなる累進課税ですので、所得税率が高い方が申請した方が、手元に戻ってくる金額は大きくなります。
例えば、医療費控除額が70万円の場合、
- 所得税率10%の方なら、還付金は7万円
- 所得税率20%の方なら、還付金は14万円
となり、大きな差が生まれます。生計を同じくする家族であれば、どなたが申請しても問題ありませんので、ご家庭内で最も所得の高い方がまとめて申告するのが賢い方法です。
Q. デンタルローンやクレジットカードで支払った費用も対象になりますか?
A. はい、どちらも医療費控除の対象となります。ただし、計上するタイミングに注意が必要です。
- デンタルローンを利用した場合
- クレジットカードで支払った場合
信販会社が治療費を歯科医院に立て替えて支払った年(=ローン契約が成立した年)の医療費として、その全額を申告します。
毎月の分割返済額を、その都度申告するわけではないのでご注意ください。手元に信販会社の契約書の控えを保管しておきましょう。
クレジットカードで支払いをした日(=歯科医院で決済をした日)が基準となります。引き落とし日ではありません。
その年に支払った金額を、その年の医療費として申告します。
Q. 矯正治療のための、通院交通費も医療費控除の対象ですか?
A. はい、電車やバスなどの公共交通機関を利用した交通費は、医療費控除の対象となります。
対象となるのは、治療を受けるお子様本人の交通費です。
ただし、お子様が小さく、一人での通院が危険なために保護者が付き添った場合は、保護者1名分の交通費も対象に含めることができます。
領収書が出ない場合がほとんどですので、日付、氏名、交通機関、利用区間、運賃などを記録したメモを残しておきましょう。
エクセルなどで一覧にしておくと、確定申告の際にスムーズです。
なお、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、残念ながら対象外となりますのでご注意ください。
Q. 矯正前の虫歯治療や抜歯の費用も、まとめて医療費控除に含められますか?
A. はい、矯正治療の一環として必要と判断された治療の費用は、すべて合算して医療費控除に含めることができます。
歯科矯正を始める前には、口腔内を健康な状態に整える必要があります。そのため、
- 矯正装置を付ける前の虫歯治療
- 歯を並べるスペースを作るための抜歯
- 歯周病の治療
- 精密検査や診断にかかった費用
これらの費用はすべて、「矯正治療を受けるために必要不可欠な医療行為」と見なされるため、矯正装置の費用とまとめて申告することが可能です。
忘れずに領収書を保管しておきましょう。
Q. 治療が年をまたぐ場合、医療費控除はいつ申請すればいいですか?
A. その年に支払った金額を、その年ごとに分けて申請します。
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費を対象として計算します。
そのため、治療が複数年にわたる場合は、それぞれの年に支払った金額を、翌年の確定申告でそれぞれ申請する必要があります。
- 例:2024年に50万円、2025年に30万円支払った場合
→ 2025年の確定申告で、2024年分の50万円について申請
→ 2026年の確定申告で、2025年分の30万円について申請
もし、治療開始時に全額を一括で支払った場合は、支払ったその年の医療費として全額を一度に申告します。
まとめ
今回は、お子様の歯科矯正と費用に関する制度について詳しく解説しました。
子供の歯科矯正に、国が設けた直接的な「補助金」制度はありません。しかし、この記事でお伝えしたように、費用の負担を軽減する方法は確かに存在します。
その最も代表的なものが、機能改善を目的とする多くの小児矯正で利用できる「医療費控除」です。
さらに、顎変形症などの特定の疾患と診断された場合は、保険適用となり、「高額療養費制度」も利用できる道が開かれています。
これらの制度を活用するためには、確定申告が必要です。歯科医院から受け取る領収書は、必ず大切に保管しておきましょう。
様々な制度を知り、費用への不安が少しでも解消されたなら、次はお子様の健やかな未来のために、最も大切な一歩を踏み出すときです。
まずは信頼できる専門の歯科医師に相談することから、すべてが始まります。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。