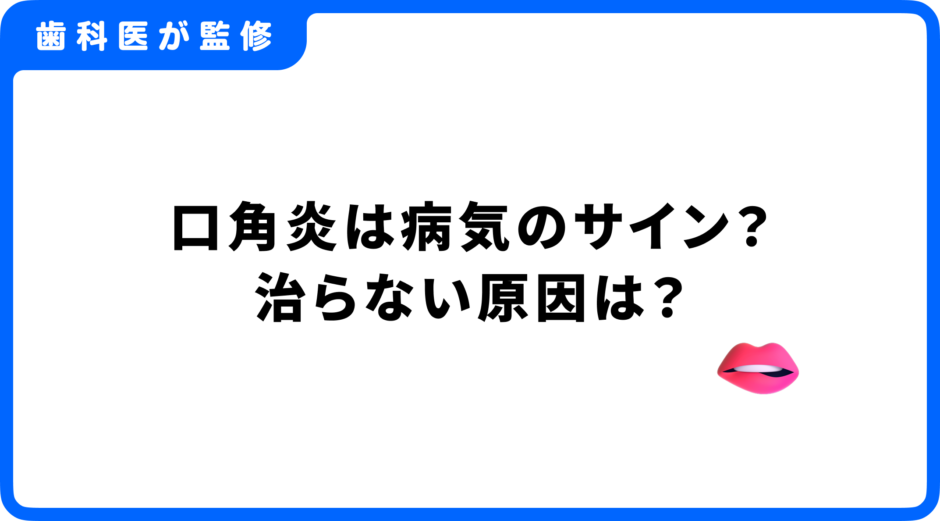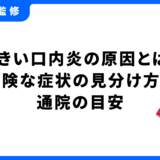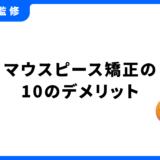「リップクリームを塗っても、薬を塗っても、口角の切れが全然治らない…」
「何度も繰り返すこの口角炎、もしかして、ただの肌荒れじゃないのかも?」
治らない口角炎に不安を感じていませんか。
多くの口角炎は乾燥や一時的な不調が原因ですが、中には体の中に病気が隠れているケースもあります。
この記事では、単なる口角炎と「病気のサイン」である危険な口角炎との見分け方や、口角炎を引き起こす可能性のある具体的な病気について、専門家の視点から詳しく解説していきます。
「たかが口角炎」と放置して重大な病気の発見が遅れることのないよう、ぜひ参考にしてください。
- 口角炎と危険な病気の前兆の見分け方
- 口角炎を引き起こす可能性のある病気
- 口角炎ができた場合に受診すべき病院(診療科)
▶関連記事:唇にできものができて痛い!痛みの原因と対処法、予防策まで解説
治らない口角炎はビタミン不足や内臓の病気のサインかも
唇の両端(口角)が切れて痛む口角炎。
多くの場合は乾燥や疲れが原因ですが、市販薬を塗っても2週間以上治らなかったり、あるいは何度も繰り返したりする場合、単なる肌荒れではなく病気のサインである可能性を疑うべきです。
口角炎の放置は危険
「口角が切れただけ」と軽く考え、口角炎を放置してしまうのは非常に危険です。
栄養状態や免疫状態の異常が皮膚や粘膜に現れることもあるとも言われるように、口角は体内の健康状態が最初に現れやすい場所なのです。
口角炎が治りにくい場合、
- 体に必要な栄養素が足りていない
- 免疫力が落ちて、菌と戦う力が弱っている
- 内臓のどこかで、なにか問題が起きている
という、体からの重要なSOSサインである可能性があります。
食生活の乱れによるビタミン不足や、貧血、糖尿病といった内臓の病気が、体の抵抗力を落とし、口角炎という形でSOSを発している場合も。
さらなる体調不良に陥る前に、不調のサインを見逃さずに正しく対処することが重要です。
病院の受診を検討すべきサイン【セルフチェック】
悩みの種である口角炎が、セルフケアで様子を見てよいものか、それとも医療機関を受診すべきか。以下の項目でセルフチェックをしてみましょう。
1つでも当てはまる項目があれば、自己判断でケアを続けるのではなく、皮膚科や内科などの専門医に一度相談することを強くおすすめします。
口角炎を発症する代表的な病気5選
長引く口角炎は、特定の栄養素の不足や内臓の不調が原因となっていることがあります。
ここでは、口角炎という症状がサインとなって現れる可能性のある、代表的な5つの病気について解説します。
ビタミンB群の欠乏
治らない口角炎の原因として最も多いのが、ビタミンB群、特にビタミンB2とビタミンB6の欠乏です。
ビタミンB群は皮膚や粘膜の健康を維持し、ターンオーバー(細胞の生まれ変わり)を正常に保つために不可欠な栄養素です。
偏った食事や無理なダイエット、過剰な飲酒などによってビタミンB群が不足すると、皮膚や粘膜が弱くなり、口角のような刺激を受けやすい部分に炎症が起きてしまうのです。
この場合は、皮膚科などでビタミン剤を処方してもらうと共に、レバー、うなぎ、卵、納豆といったビタミンB群を多く含む食品を日々の食事に積極的に取り入れてください。
鉄欠乏性貧血
「口角炎が治らない」「疲れやすい」「めまいや立ちくらみがする」といった症状が同時に現れている場合、鉄欠乏性貧血の可能性があります。
鉄欠乏性貧血になると、体の隅々まで酸素を運ぶヘモグロビンが不足し、皮膚や粘膜の細胞に十分な酸素が供給されなくなります。
その結果、皮膚の再生能力が落ち、口角などのデリケートな部分が荒れやすくなってしまうのです。
特に女性は月経によって鉄分が失われやすいため、注意が必要です。
鉄欠乏性貧血が疑われる場合は内科などを受診し、血液検査を受けることが重要です。
鉄剤の処方を受けるとともに、赤身の肉や魚、ほうれん草、あさりなど、鉄分を多く含む食品を意識して摂取しましょう。
糖尿病
糖尿病を一要因としてかかる感染症の一つが、口腔内の常在菌である「カンジダ菌」の異常増殖による口角炎です。
カンジダ菌はカビの一種で、健康な状態では問題を起こしません。
しかし、糖尿病によって免疫力が低下したり唾液の分泌が減って口の中が乾燥したりすると、カンジダ菌が異常に増殖し、口角に白い苔のようなものが付着する口角炎を引き起こすことがあります。
糖尿病によって血糖値が高い状態が続くと、体全体の免疫力が低下し、様々な感染症にかかりやすくなるのです。
口角炎のほかに以下の症状がある場合、糖尿病が疑われます。速やかに内科を受診してください。
胃腸障害
胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などの胃腸障害があると、口角炎ができやすくなることがあります。これらは主に栄養素の吸収阻害が原因であると考えられます。
胃腸の機能が低下すると、食事から摂ったビタミンやミネラルなどの栄養素が体内にうまく吸収されなくなります。その結果、ビタミンB群などが欠乏し、口角炎を引き起こします。
口角炎とともに、胃もたれや胸やけ、食欲不振などの症状が続く場合は、消化器内科に一度相談してみることをお勧めします。
免疫不全を引き起こすHIVなどの病気
非常に稀ですが、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症など、免疫機能そのものが著しく低下する病気の初期症状として、口角炎や口腔カンジダ症が現れることがあります。
HIVに感染すると、体を感染症から守る免疫細胞が破壊され、健康な人ではかからないような様々な感染症(日和見感染症)にかかりやすくなります。
その一つとして、口腔内のカンジダ菌が異常増殖し、口角炎や口の中に白い苔のようなものが広がる症状が出ることが報告されています。
原因不明の口角炎に加え、以下のような症状が複数ある場合は、ためらわずに専門の医療機関を受診し、検査を受けることが重要です。
すべてが病気ではない。口角炎の一般的な原因
口角炎には病気のサインである可能性がある一方、多くの場合はより身近な原因によって引き起こされます。
内臓の病気などを心配する前に、まずはご自身の生活習慣や環境に、口角炎を招く要因がないか確認してみましょう。
カンジダ菌などの感染
口角炎の直接的な引き金として多いのが、カビの一種であるカンジダ菌や、黄色ブドウ球菌などの細菌感染です。
これらの菌は、健康な人の皮膚や口の中にも常に存在している常在菌ですが、普段は体の免疫力によってその活動が抑えられています。
しかし、免疫力の低下などが原因でこれらの菌が異常に増殖すると、皮膚に炎症を起こし、口角炎を発症します。
カンジダ菌が原因である場合、口角に白い苔のようなものが付着したり、皮膚が赤くただれたりする特徴が見られます。
この場合は、抗真菌薬の塗り薬などによる治療が有効です。
唾液や乾燥、マスクの擦れによる物理的な刺激
日常的に些細な「物理的な刺激」が積み重なり、炎症が起きている可能性があります。
口角は皮膚が薄く、常に刺激にさらされている非常にデリケートな部分です。
以下のような刺激から口角を守るため、ワセリンやリップクリームなどでこまめに保湿することが大切です。
唇をなめる癖があると、唾液の消化酵素が口角を刺激し、さらに唾液が蒸発する際に唇の水分を奪って乾燥を招きます。
空気が乾燥する冬場や、エアコンの効いた室内では、唇や口角の水分が失われ、バリア機能が低下して切れやすくなります。
長時間のマスク着用は、マスク内の湿度で皮膚がふやけたり、着脱時の摩擦で口角が擦れたりすることで、大きな負担となります。
サイズが合っていない入れ歯や矯正装置が、口角に慢性的な刺激を与えているケースもあります。
ストレスや疲労による免疫力の低下
過度なストレスや身体的な疲労は体の「免疫力」を低下させ、口角炎の引き金となります。
私たちの体は免疫システムによって、外部からの細菌やウイルス、体内の常在菌の活動から守られています。
しかし、強いストレスを受けたり睡眠不足が続いたりすると、この免疫システムが正常に機能しなくなり、体の抵抗力が落ちてしまいます。
その結果、普段なら問題にならないようなカンジダ菌が増殖したり、些細な刺激からでも炎症が起きやすくなったりして、口角炎を発症するのです。
「大きな仕事が終わってホッとした時」や「季節の変わり目で体調を崩しやすい時」などに口角炎ができやすいのは、この免疫力の低下が大きく関係しています。
口角炎が治らない場合、病院は何科を受診すればいい?
「口角炎が治らない場合、一体どこで診てもらえばいいの?」と、受診先に迷う人は少なくありません。
口角炎の原因は多岐にわたるため、自身の症状や、他に気になる体の不調があるかによって、相談すべき診療科が異なります。
ここでは、症状に合わせた適切な受診先を解説します。
迷ったら・体の不調が他になければ「皮膚科」へ
口角炎の症状だけで、他に体の不調がない場合は、まず「皮膚科」を受診するのが基本です。
口角炎は、皮膚に起きる炎症(皮膚炎)の一種です。
皮膚科の専門医は患部の状態を診て、それがカンジダ菌などの感染によるものか、あるいは単純な刺激や乾燥によるものかを的確に診断し、症状に合った塗り薬(抗真菌薬、ステロイド、保湿剤など)を処方してくれます。
何科に行けばよいか迷ったら、まずは皮膚科で相談してみると良いでしょう。内科的な病気が疑われると判断されれば、適切な医療機関を紹介してもらえます。
入れ歯の不具合などが考えられる場合は「歯科」や「口腔外科」へ
「入れ歯を使い始めてから、口角炎が起きるようになった」「歯の矯正装置が当たって痛い」など、口の中に原因があると考えられる場合は、「歯科」や「口腔外科」への相談が適しています。
特に、サイズの合っていない入れ歯を使用していると口角が下がり、唾液が溜まりやすい環境が作られます。唾液の刺激によってカンジダ菌が増殖し、口角炎を引き起こすケースは多く見られます。
歯科医院では、入れ歯の調整や、口腔内の清掃指導、カンジダ菌に対する薬の処方など、口腔環境全体にアプローチする治療を行います。
全身の倦怠感や他の症状があるなら「内科」へ
長引く口角炎に加えて「疲れがとれない」「めまいや立ちくらみがする」「喉が異常に渇く」などの全身症状がある場合、「内科」の受診を検討してください。
これらの症状は、鉄欠乏性貧血や糖尿病、胃腸障害といった、内臓の病気が隠れているサインかもしれません。
内科では、血液検査などによって、口角炎の背景にある全身疾患の有無を調べることができます。
皮膚科で治療をしているが口角炎がなかなか改善しないという場合も、一度内科的な観点から体をチェックしてもらうと、思わぬ原因が見つかるかもしれません。
口角炎を予防するために今日からできること
つらい口角炎を繰り返さないためには、日々の生活の中で予防を意識することが何よりも大切です。
今日から始められる、具体的な予防策は以下の通りです。
バランスの取れた食事を心がける
皮膚や粘膜の健康を保つビタミンB群(レバー、卵、納豆など)や、鉄分(赤身肉、ほうれん草など)を意識的に食事に取り入れましょう。
唇と口角の保湿を徹底する
リップクリームやワセリンをこまめに塗り、唇の乾燥を防ぎましょう。唇をなめる癖は、乾燥を助長するため、意識してやめるようにします。
十分な睡眠とストレス管理
体の免疫力を高く保つため、質の良い睡眠をとり、自分なりのストレス解消法を見つけることが改善につながります。
口腔内を清潔に保つ
毎日の丁寧な歯磨きはもちろん、入れ歯を使用している方は、入れ歯自体も清潔に保つことを心がけましょう。
口角炎と病気のサインに関するよくある質問
ここでは、口角炎とそれが示す可能性のある病気のサインについて、多くの方が抱くさらに細かい疑問にQ&A形式でお答えします。
Q. 口角炎と口唇ヘルペスの違いは何ですか?
A. 口角炎と口唇ヘルペスの最も大きな違いは原因と症状の出方です。口唇ヘルペスはウイルスが原因で、小さな水ぶくれができるのが特徴です。
口角炎と口唇ヘルペスは、できる場所が近いため混同されやすいですが、全く異なる病気です。
| 項目 | 口角炎 | 口唇ヘルペス |
| 原因 | 細菌・カンジダ菌、乾燥、栄養不足など | ヘルペスウイルスの感染 |
| 主な症状 | 亀裂、赤み、かさぶた(水ぶくれはできない) | 小さな水ぶくれの集まり、チクチク・ピリピリとした痛み |
| できる場所 | 口角 | 唇とその周り(口角にできることも) |
| 感染性 | 細菌感染以外はうつらない | ウイルスが含まれる水ぶくれに触れるとうつる |
ヘルペスに口角炎の薬を塗っても効果がないばかりか、悪化させる可能性もあります。
水ぶくれができている場合は自己判断せず、必ず皮膚科を受診してください。
▶関連記事:唇の水泡=ヘルペスじゃない?考えられる病気と対処法を専門家が徹底解説
Q. 市販のリップクリームを塗っても口角炎が治らないのはなぜですか?
A. リップクリームの目的は保湿であり、治療ではないためです。また、乾燥以外に原因がある可能性が考えられます。
一般的なリップクリームの役割は、唇に油分の膜を張って水分の蒸発を防ぎ、乾燥から保護することです。
すでに起きてしまった炎症を抑えたり、原因となっている細菌やカンジダ菌を殺菌したりする効果は含まれていません。
もし保湿をしても一向に改善しない場合、カンジダ菌などの細菌感染や、ビタミン不足など体の内側の問題が原因として疑われます。
炎症を抑える成分が含まれた医薬品の軟膏に切り替えるか、医療機関を受診することをおすすめします。
Q. 亜鉛不足も口角炎の原因になりますか?
A. はい、亜鉛不足も口角炎の引き金になる可能性があります。
亜鉛は、タンパク質の合成や細胞の生まれ変わり(ターンオーバー)に不可欠なミネラルです。
亜鉛が不足すると、皮膚や粘膜の新陳代謝が滞って傷が治りにくくなったり、肌荒れや口角炎が起きやすくなったりします。
また、亜鉛は免疫機能の維持にも重要な役割を果たしているため、不足すると免疫力が低下して感染症にかかりやすくなります。
口角炎が長引く場合は、ビタミンB群と合わせて、牡蠣やレバー、牛肉などの亜鉛を多く含む食品を意識して摂取するのも良いでしょう。
Q. 口角炎は何日くらいで治るのが普通ですか?
A. 適切なケアを行えば、通常は数日~2週間程度で改善に向かいます。
原因や症状の重さにもよりますが、一般的な口角炎であれば、保湿や市販薬の使用、生活習慣の見直しなど、適切なセルフケアを行うことで、1週間程度で快方に向かうことがほとんどです。
もし、セルフケアを続けても2週間以上全く改善しない、あるいは悪化している場合は、何か他の原因(病気のサインなど)が隠れている可能性があります。
その場合は、様子を見続けるのではなく、医療機関を受診する明確な目安と考えてください。
Q. 子どもの口角炎も、何か病気のサインなのでしょうか?
A. 子どもの口角炎の多くは、よだれや食べこぼしによる刺激が原因ですが、栄養不足のサインであることも考えられます。
子ども、特に乳幼児はよだれの量が多く、食事の際に食べこぼしも多いため、口の周りが常に湿った状態になりがちです。
この唾液の刺激によって皮膚のバリア機能が低下し、口角炎が起きやすくなります。
こまめに口周りを拭き、ワセリンなどで保湿してあげるのがケアの基本です。
ただし、好き嫌いが多く、食事が偏りがちな子どもの場合、ビタミンB群などの栄養不足が原因となっているケースもあります。
子どもの口角炎が長引く場合や何度も繰り返す場合は、かかりつけの小児科や皮膚科で相談してみましょう。
まとめ|長引く口角炎は体からのメッセージ
治らない口角炎がサインとなる可能性のある病気や、その原因、そして受診すべき診療科について解説してきました。
口角炎は唇の端が切れるというささいな症状ですが、その背景には「栄養が足りていないよ」「免疫が落ちているよ」といった、体からの重要なメッセージが隠れていることがあります。
「たかが口角炎」と軽視せず、自分の体と向き合うきっかけにしてください。少しでも不安があれば、病院に罹りましょう。
まずは専門家にオンラインで相談してみませんか?
「いろいろ原因があるのはわかったけど、結局自分の場合はどれなんだろう…」
「皮膚科、歯科、内科…どこに行けばいいか、まだ迷ってしまう」
そのようにお考えの方には、ご自宅からオンラインで気軽に専門家に相談できるサービス「mamoru」がおすすめです。
「mamoru」を使えば、
- この治らない口角炎、何が原因だと思いますか?
- 私の症状の場合、どの診療科を受診するのが一番良さそう?
- 食生活で気をつけるべきことを、もっと具体的に教えてほしい
といった、あなたが抱える具体的な悩みや不安を、チャット形式で専門家(医師や薬剤師など)に直接相談することができます。
どの病院に行くべきか、まずは専門家の意見を聞いてから判断したい。そんなあなたの不安な気持ちに寄り添う、信頼できる第一歩として。ぜひ「mamoru」の活用をご検討ください。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。