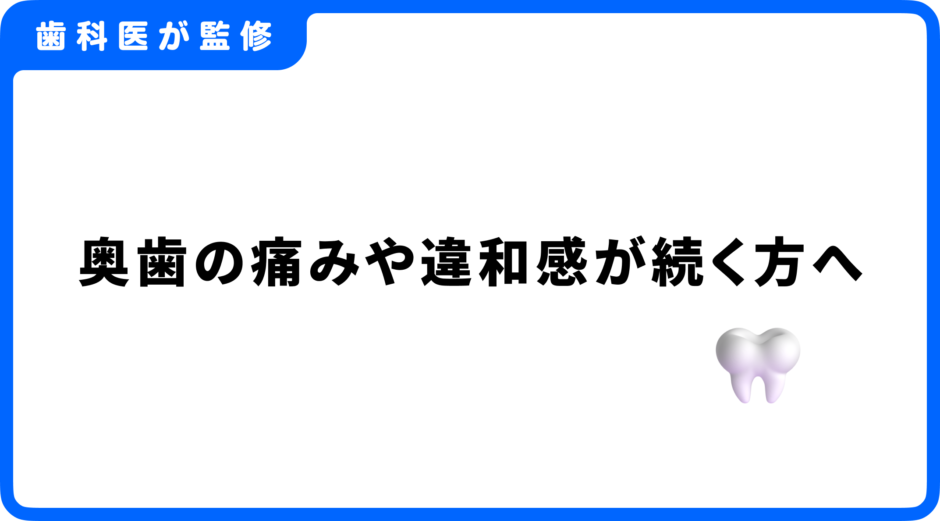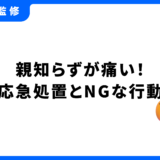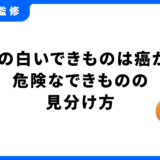「奥歯が痛い」
「奥歯の詰め物が取れた」
「親知らずが気になる」
そんな奥歯の悩みを放置していませんか?
奥歯は普段意識されにくい存在ですが、食事はもちろん、健康維持において非常に重要な役割を担っています。多数の歯を無くした場合には、顔の見た目にも影響すると言われます。
しかし奥歯は奥まった位置にあるため磨き残しが起きやすく、虫歯や歯周病などのトラブルが進行しやすい部位でもあります。
本記事では、奥歯の種類と役割から、よくあるトラブルとその原因、抜歯後の治療法まで、歯科医療の視点からわかりやすく解説します。
- 奥歯の種類と役割
- 奥歯の正しい磨き方
- 奥歯によくあるトラブルとその原因
- 奥歯を抜歯後の治療法
奥歯の役割と重要性
奥歯は「噛む」「支える」などの重要な働きを担っており、私たちの食生活や健康を支える重要な歯です。
本章では、奥歯の範囲や役割など、奥歯についての基本的な知識を紹介します。
奥歯とは「小臼歯」と「大臼歯」のこと
奥歯とは、前歯から数えて4番目以降に位置する「小臼歯」と「大臼歯」を指します。
とくに「大臼歯」は、食事の際に強い力で食べ物をすり潰す役割を持っており、歯の中でも最も大きく複雑な構造をしています。
以下に、大臼歯の種類と特徴を解説します。
第三大臼歯(親知らず)
第三大臼歯はいわゆる「親知らず」です。多くの場合、20歳前後で生えてきますが、現代人はあごが小さくなった影響から、正しく生えずに炎症や痛みを引き起こすことがあります。
親知らずはトラブルを起こしやすいため、抜歯を勧められるケースも多く、歯科医の診察による個別判断が必要です。
第二大臼歯
第二大臼歯は前から7番目の歯で、奥歯の中核を担う存在です。
第一大臼歯とともに噛む力の大部分を担っており、補綴治療(ブリッジ、入れ歯など)を支える歯(支台歯)としても重要なポジションにあります。
磨きにくさから、虫歯や歯周病が進行しやすい歯でもあります。
第一大臼歯
第一大臼歯は、最も早く生えてくる大人の奥歯で、6歳臼歯とも呼ばれます。永久歯の中で最も大きく、噛み合わせの基準となる重要な歯です。
虫歯になる可能性が高く、銀歯やセラミックなどのインレー(詰め物)・被せ物による治療も頻繁に行われます。
奥歯が持つ4つの役割
奥歯には、健康な生活を支えるために不可欠な4つの役割があります。
- 咀嚼(食べ物をすり潰す)
硬い食材を砕き、消化を助けます。 - 噛み合わせを安定させる
上下の歯のバランスを保ち、顎関節や全体の歯並びの維持に寄与します。 - 顔の輪郭・見た目を支える
奥歯が失われると頬がこけ、老けた印象になる可能性があります。 - 力の分散とバランス維持
噛む力を分散し、前歯や他の歯への過剰な負担を防ぎます。
奥歯はただの「奥の歯」ではなく、全身の健康を支える重要な存在なのです。
奥歯の寿命は約50〜60年
奥歯は非常に重要な歯でありながら、最もダメージを受けやすい歯でもあります。
厚生労働省の調査によると、日本人の第一大臼歯の平均寿命は約50〜60年とされ、前歯よりも早く失われやすいと考えられています(参照)。
その理由として以下のことが挙げられます。
- 噛む力による負担が大きい
- 奥にあるため磨き残しが多くなりやすい
- 虫歯・歯周病の進行に気づきにくい
銀歯や古い詰め物の下で虫歯が進行していたというケースも多々。定期的な診察とメンテナンスが、奥歯を長持ちさせるカギと言えます。
奥歯がなくなる悪影響は噛めなくなるだけじゃない
奥歯を失った状態で放置すると、口腔内と全身の健康にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。
奥歯は咀嚼機能の中心を担っているため、失ったまま放置すると食べ物をしっかり噛めなくなります。結果、栄養バランスが乱れたり、胃腸への負担が増したりする懸念があります。
前歯に過剰な力がかかるため、他の歯の寿命が縮まったり、噛み合わせが崩れて歯並びが悪化するリスクも。
奥歯がなくなった空間に周囲の歯が傾いて移動してしまうことにより、噛み合わせのバランスが崩れる場合もあるでしょう。
顎関節や顔貌、全身の姿勢にまで影響が及ぶこともあります。
奥歯がなくなって噛む力が変化すれば、頬がこけて老けた印象を与える外見になるなど、社会的な自信を損ねてしまうかもしれません。
奥歯がなくなる影響は甚大です。1本でも奥歯を失った場合は、補綴治療(入れ歯、ブリッジ、インプラント)などの治療を行い、他の歯に悪影響を与えないよう補綴物を装着することをおすすめします。
奥歯に多いトラブル5選
奥歯は噛む力の負担が集中するうえ、位置的にケアが難しいため、口腔内トラブルが最も発生しやすい部位です。奥歯のトラブルを放置すれば、咀嚼へ影響を及ぼすリスクがあります。
ここでは、頻繁にみられる奥歯のトラブルとその特徴を解説します。
1. 虫歯や歯周病
奥歯は口の中の一番奥にあるため、歯磨きが不十分になりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高い部位です。
とくに第一大臼歯や第二大臼歯には噛み合わせの力が強くかかるため、歯のかみ合わせの溝(裂溝)や歯と歯の間にプラークが溜まりやすくなります。
奥歯の虫歯では、詰め物や銀歯の下で進行する「二次カリエス」(過去に治療した部位に発生する二次的な虫歯)が見つかることも多く、痛みを感じたときには虫歯が神経に達しているケースも少なくありません。
同様に歯周病も自覚症状がないまま進行し、歯を支える骨が吸収されていくため、最終的に歯を失ってしまうリスクもあります。
虫歯や歯周病の症状が軽いうちに発見・治療するには、定期的な歯科検診が不可欠です。
2. 親知らずの炎症(智歯周囲炎)
親知らず(第三大臼歯)は、あごのスペース不足により斜めや横向きに生えてしまうことが多く、歯茎に炎症を起こしやすくなります。
歯茎の腫れや出血、口が開けにくくなる開口障害や、噛んだときの鋭い痛みなどの症状が出る可能性があり、ひどい場合には頬の腫れや発熱、リンパの腫れを伴います。
親知らずのこのようなトラブルは「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」と呼ばれ、放置すれば炎症が顎の骨や喉の奥にまで波及する危険性も。
親知らずの炎症が再発を繰り返す場合は、抜歯の選択肢も検討すべきです。
親知らずについては、以下の関連記事も参考にしてください。
▶関連記事:親知らずは抜くべき?抜かなきゃよかったと後悔しないための判断基準
▶関連記事:親知らず抜歯後の過ごし方とタブー|正しい経過や注意点を徹底解説【歯科監修】
3. 知覚過敏
冷たいものや熱いものを口にしたときに奥歯が「キーン」としみるように痛む場合、知覚過敏の可能性があります。
知覚過敏で歯がしみるメカニズムは、歯の表面を覆うエナメル質が削れたり、歯茎が下がって象牙質が露出したりすることで、刺激が神経に直接伝わるのです。
知覚過敏は、歯ぎしりや強すぎる歯磨き、ホワイトニングの副作用、加齢による歯茎の退縮によっても引き起こされます。
症状が軽度であれば、専用の歯磨き粉やフッ素塗布で改善する場合もあります。
奥歯だけがしみる場合は、奥歯の神経の異常や破折(歯の折れやひび)の可能性もあるため、早めに歯科医院で診察を受けましょう。
4. 歯ぎしりや食いしばり
歯ぎしり(ブラキシズム)や無意識の食いしばりは、奥歯にとって大きな負担です。
食いしばる力はときに100kgを超えると言われ、歯のすり減りやひび割れ、詰め物の脱離などの悪影響を引き起こします。
歯ぎしりや食いしばりの影響が顎関節や咬筋にまで及ぶと、頭痛や肩こり、睡眠の質の低下の原因になることも。
歯ぎしりや食いしばりのクセに対して、歯科では次のように対処します。
- ナイトガード(マウスピース)の装着
- 咬合調整(噛み合わせのバランス修正)
- ストレス管理や生活習慣の見直し
- ボトックス注射
奥歯に違和感がある方は、日中や就寝中の食いしばり癖にも注意が必要です。
5. 噛み合わせの悪化
噛み合わせが悪いと奥歯に加わる力が偏るため、局所的に摩耗や破損が起きる可能性があります。
また、上下の歯がうまく接触しない「咬合不全」の状態になると、十分に噛めないだけでなく、発音のしづらさや顎関節の違和感も引き起こされます。
歯の噛み合わせに問題が生じるきっかけは、成長期の歯並びのズレや、親知らずの影響、虫歯や抜歯後の放置など。
一見しても、噛み合わせに乱れがあるという判断は難しいため、定期的に歯科に通い、噛み合わせをチェックしてもらうことが重要です。
奥歯が痛むのは歯のせいじゃないかも。考えられる原因と対処法
奥歯に痛みがある場合、虫歯や歯周病が原因だと考えがちですが、実際には「歯に異常がないのに痛い」ケースもあります。
こうした痛みは、「非歯原性歯痛」と呼ばれ、歯以外の筋肉や神経、全身疾患が原因である可能性が考えられます。
ここでは、歯以外が原因となる奥歯の痛みと対処法について解説します。
咀嚼筋の炎症
奥歯を動かす筋肉が炎症を起こすと、歯そのものは健康でも「奥歯が痛い」と感じることがあります。
これは「筋・筋膜性歯痛」と呼ばれるもので、代表的なのが咬筋(こうきん)や側頭筋などの咀嚼筋の過緊張・疲労です。
咀嚼筋に炎症が起きた場合、痛みの特徴は以下の通りです。
- 噛んだときだけ痛みを感じる
- レントゲン検査などでは異常が見つからない
- 頬やこめかみを押すと痛みが再現される
原因として、ストレスによる食いしばりや睡眠中の歯ぎしりが多いとされます。処置としては、ナイトガードの装着やストレッチ、生活習慣の見直しが効果的です。
神経痛・片頭痛
三叉神経痛や偏頭痛によって、奥歯に痛みを感じることがあります。
とくに三叉神経は顔面や上下の歯を広範囲に支配しているため、電撃的な鋭い痛みが一瞬走るような痛みは、神経性が疑われます。
| 痛みの性質 | 一瞬の強い痛み、ピリッとする電気が走るような感覚 |
| 持続時間 | 数秒〜数分と短く、繰り返し起こる |
| 歯科検査での異常有無 | 原因となる歯の病変は見当たらない |
このようなケースでは、歯科ではなく神経内科やペインクリニックでの診断・治療が必要になります。
一方、片頭痛が原因である場合、鈍くズーンとした奥歯の痛みが特徴です。発作時には光や音に過敏になったり、吐き気を伴ったりするかもしれません。
ストレス
精神的ストレスによって、歯が痛くなったり、歯の痛みが悪化したりすることがあります。
自律神経の乱れによって交感神経が優位になると、血管の収縮や筋肉の緊張が引き起こされます。歯の噛みしめや顎のこわばりが強まり、奥歯の違和感や痛みにつながる可能性があるのです。
また、ストレスによって無意識に歯ぎしりをする習慣がつき、筋肉や顎関節に負担がかかるという悪循環も。
ストレス性の歯痛があるケースでは、以下のようなアプローチが有効です。
- 睡眠や食生活の見直し
- 日中のリラクゼーション・深呼吸の習慣化
- ナイトガードや噛み合わせ調整による物理的負担の軽減
ストレスと奥歯の痛みは一見無関係に思えますが、実は密接につながっているのです。
心臓病
あまり知られていませんが、狭心症や心筋梗塞などの心臓疾患の前兆として、左側の奥歯に違和感や痛みを覚えることがあります。
これは「放散痛(ほうさんつう)」と呼ばれる現象で、心臓に由来する痛みが肩や腕、歯に現れるのが特徴です。
とくに以下のような症状が併発する場合には、すぐに医療機関を受診してください。
- 左の奥歯から顎、首、肩にかけて広がる重苦しい痛み
- 安静時にも痛みが持続する
- 動悸・息切れ・吐き気などを伴う
心臓病の既往歴がある方はとくに慎重な判断が求められます。歯科での診断は難しい領域だと言えます。
副鼻腔炎
副鼻腔炎(蓄膿症)も、奥歯の痛みと誤認されやすい病気のひとつです。
とくに上顎洞(じょうがくどう)という副鼻腔は、上の奥歯の根と非常に近いため、炎症が起きると周囲の神経に影響して歯の痛みとして現れることがあります。
副鼻腔炎の代表的な症状は以下の通りです。
- 鼻づまり・黄色や緑色の鼻水
- 頬や目の下の鈍い痛み
- 顔を下に向けると圧迫感が増す
このような場合、耳鼻咽喉科での画像診断や抗生物質治療が必要です。
歯科で異常が見つからず、風邪のような症状を伴っている場合は、副鼻腔の炎症を疑い、他科の受診も検討しましょう。
奥歯を失った場合の3つの治療法
奥歯を失った状態を放置していると、噛み合わせの乱れや周囲の歯の移動、食事や発音の支障など、さまざまな悪影響が生じます。
これを防ぐには、ブリッジ・入れ歯・インプラントなどによる補綴(ほてつ)治療によって、歯の機能を補う必要があります。
見た目や費用、治療期間などのバランスを踏まえ、自分に適した治療法を選択しましょう。3つの治療法について、以下で詳しく解説します。
ブリッジ
ブリッジは、失った歯の両隣の歯を削り、橋渡しする形で人工歯を固定する治療法です。
| 特徴 | 固定式の人工歯を装着するため、違和感が少ない両隣の健康な歯を支台として使用する |
| メリット | 見た目が自然で審美的治療期間が比較的短い保険適用も可能 |
| デメリット | 健康な歯を削る必要がある支える歯に負担がかかる歯間清掃がやや難しい |
費用は保険適用で数万円程度。自費診療のセラミックやジルコニアのブリッジでは、25〜40万円ほどが目安です。
入れ歯(部分義歯)
入れ歯は、失われた歯を人工歯で補い、金属や樹脂のバネで残存歯に引っかけて装着する取り外し式の装置です。
| 特徴 | 複数の歯を一度に補える取り外し可能で清掃しやすい比較的安価 |
| メリット | 健康な歯を削る必要がない保険適用可能で経済的高齢者にも適応しやすい |
| デメリット | 装着時に違和感を覚えやすい食べ物を粉砕する効率が悪い見た目や安定性に課題がある入れ歯の洗浄などの管理が必要 |
費用は保険診療で5,000〜15,000円程度です。ノンクラスプデンチャー(歯茎に似た色の目立たない入れ歯)や金属床義歯の場合、自費診療で10万〜30万円程度が相場となります。
インプラント
インプラントは、顎の骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける治療法です。
| 特徴 | 顎の骨と結合し、天然歯に近い機能性を実現する見た目が自然で高い審美性を持つ |
| メリット | 周囲の歯を削らずに済む食べ物を粉砕する効率が天然の歯に近い長期的に安定しやすい |
| デメリット | 外科手術が必要治療期間が長い(3〜6ヶ月)自費診療で費用が高額 |
費用は1本あたり30万〜50万円程度かかるのが一般的です。骨造成や上部構造を含めると、全体で40万〜70万円ほどかかる場合があります。
奥歯の正しい磨き方・ケア方法
奥歯は磨きにくい位置にあるため、虫歯や歯周病のリスクが高い部位です。「毎日磨いているのに奥歯ばかり虫歯になる」という方は、歯磨きが上手にできていないかもしれません。
まず意識すべきは、歯ブラシの当て方と動かし方です。奥歯は以下の3方向から、毛先をしっかり当てて小刻みに動かすことが重要です。
- 噛み合わせ面(食べ物をすり潰す面)
- 頬側(外側)
- 舌側(内側)
第一大臼歯と第二大臼歯の間や奥側は磨き残しが起きやすいため、時間をかけて丁寧にブラッシングする必要があります。
歯ブラシだけで落としきれない汚れには、デンタルフロスなど、補助的な清掃用具の活用が有効です。以下に代表的な器具とその役割を示します。
| 補助用具 | 役割・適した使い方 |
| デンタルフロス | 歯と歯の間のプラークを除去する。歯間部の虫歯・歯周病予防に効果的。 |
| 歯間ブラシ | 歯茎との境目やブリッジ周囲など、広めの歯間に適する。 |
| タフトブラシ | 奥歯の裏側や凹凸部の細かい仕上げ磨きに最適。 |
とくに就寝前の歯磨き時には、日中にたまった汚れや細菌をしっかり除去しましょう。
奥歯の健康を守るためには、セルフケアに加え、歯科医院で定期診療を受けることが大切です。プロによる次のようなケアを受けることで、早期発見や早期対応が可能になります。
- PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)による歯石や汚れの除去
- 歯周ポケットの検査
- インレー(詰め物)や銀歯の不適合・再治療の必要性の評価
- 歯周病や虫歯の進行状況のチェック
奥歯は、自分でケアしているつもりでも意外と見落としが多い領域です。
正しいケアを習慣化して歯科医院にも通いながら、奥歯の健康寿命を延ばしましょう。
奥歯に関するよくある質問
奥歯に関する悩みや疑問は多岐に渡ります。
ここでは、奥歯に関するよくある質問に対して、歯科医療の視点から回答します。
Q. 奥歯が痛い原因は?
A. 奥歯が痛む主な原因として、虫歯・歯周病・歯ぎしり・噛み合わせの異常などが挙げられます。ただし場合によっては、神経痛や副鼻腔炎など歯以外の要因が関与していることもあります。
まず、最も一般的なのは虫歯の進行です。奥歯は歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすいため、知らないうちに深部まで進行してしまうことがあります。
また、銀歯やインレー(詰め物)の下で二次的に虫歯が再発する「二次カリエス」も見落とされやすい原因の一つです。
歯周病の場合、歯茎の腫れや出血に加え、奥歯がぐらつく・重だるく痛むという症状が出ることがあります。
さらに、噛み合わせの不調整や就寝時の歯ぎしりが原因で咀嚼筋や顎関節が緊張し、痛みとして現れるケースも。
奥歯の見た目に異常がなくても痛い場合、非歯原性の原因が疑われます。
Q. 奥歯を入れ歯にするメリットやデメリットは?
A. 入れ歯の最大のメリットは、歯を削らずに補綴(ほてつ)できることと、比較的経済的な費用で治療できることです。
高齢者や、持病があってインプラントが難しい方にも適応しやすいのが特徴です。
入れ歯は「取り外し式」であることから、メンテナンスの自由度は高いと言えます。快適性や機能性を重視する場合は、ブリッジやインプラントとの比較検討が必要です。
一方で部分入れ歯は、バネ(クラスプ)を使って周囲の歯に引っかける構造になっており、バネがかかる歯に力が加わるため悪影響を及ぼすデメリットがあります。
他にも、歯の違和感や審美性、噛む力の弱さなどがデメリットとして挙げられます。装着時に異物感がある、噛む力が天然歯の半分以下になる、金属バネが目立つなどの点は不便かもしれません。
また、長期間使用するとバネをかけた歯がぐらついたり、支台歯の寿命を縮めたりする可能性もあるでしょう。
Q. 奥歯や親知らずを抜くデメリットは?
A. 奥歯や親知らずの抜歯は、必要性が高いケースもありますが、抜いた後の影響を理解した上で判断することが重要です。
奥歯(とくに第一・第二大臼歯)は、噛む力の中心を担っているため、抜歯によって咀嚼力が著しく低下します。
その結果、食べにくさや消化不良、他の歯への負担増加など、多数の問題が生じる可能性があります。
また、奥歯が抜けたままになると、隣の歯が傾いたり、対合歯(噛み合っていた歯)がペースを埋めるように生えたりして、歯並びや噛み合わせが乱れるリスクがあることも知っておきましょう。
一方、親知らずについては、痛みや炎症を繰り返す場合や、歯列に悪影響を与える場合は抜歯が望ましいとされています。
ただし、抜歯後の腫れ・麻痺などの合併症リスクについては十分に理解しておいてください。
抜歯は慎重な判断が求められる治療です。信頼できる歯科医とともに方針を決めましょう。
まとめ
奥歯は咀嚼や、見た目、噛み合わせに関わる非常に重要な歯です。
しかしその位置ゆえに、虫歯や歯周病、噛み合わせなどの問題が起きやすく、放置すると周囲の歯や顎関節にまで影響が及ぶことがあります。
奥歯のトラブルを未然に防ぐには、毎日の正しいケアと歯科医院での定期的な検診が欠かせません。
奥歯を失った場合は、ブリッジ・入れ歯・インプラントなどの補綴(ほてつ)治療によって早期に機能回復を図ることが望ましく、歯科医と相談しながら自分に合った治療法を選ぶことが大切です。
違和感や痛みを感じたら、早めに歯科医院を受診しましょう。
「どこに相談すればいいかわからない」「これを機に、信頼できるかかりつけの歯医者さんを見つけたい」という方には、予防歯科サービス「歯科まもる予約」 の活用がおすすめです。
「mamoru」は、あなたに合った歯科医院探しをサポートし、お口の健康を守るパートナーを見つけるお手伝いをします。
お口の小さな異変を見逃さず、健康な毎日を送るために、ぜひご活用ください。