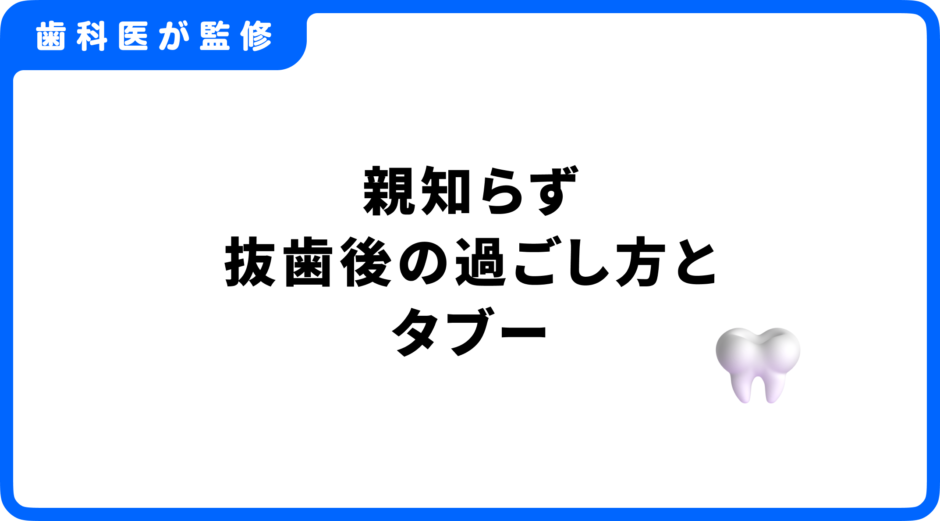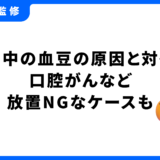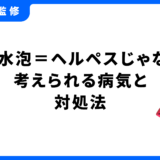「親知らずを抜いたけど、これって普通?」
「痛みが続いて不安…」
親知らずの抜歯後には、腫れや強い痛み、出血や違和感があります。誰もが不安を感じますよね。
とくに、どれくらいで治るのか?何に気をつけるべきか?異常のサインはどこで見分けるのか?……など、正しい情報を知っておきたいものです。
本記事では、抜歯後の患部の経過を時系列で解説しながら、やってはいけない行動や再受診すべき症状の見極め方まで解説します。
術後の不安を安心に変えるため、ぜひ参考にしてください。
▶関連記事:親知らずは抜くべき?抜かなきゃよかったと後悔しないための判断基準
親知らず抜歯後の患部の経過
親知らずの抜歯後、患部は時間の経過とともに段階的に治癒していきます。
腫れや痛みのピークがいつなのか、どれくらいで食事ができるようになるのかなどを知っておき、術後の不安を解消しましょう。
ここでは、術後から完治までの患部の変化をわかりやすく時系列で解説します。
抜歯後1〜3日|腫れ・痛み・炎症のピーク
抜歯後の最初の3日間は、患部に最も強い炎症が生じます。
歯を抜いた直後にできる「血餅(けっぺい)」という血のかたまりが患部を保護し、治癒を促す重要な役割を担っていきます。
この時期は、頬や顎が大きく腫れ、ズキズキするような痛みを感じることがあります。
腫れは、抜歯の翌日から3日目にピークを迎えるのが一般的です。
熱っぽさや、軽い発熱を伴うこともありますが、これは免疫による自然な反応なので安心してください。
処方された鎮痛薬は、痛みが出る前に服用しておくと効果的です。
また、無理に口を開けたり、少量の出血が気になって頻繁にうがいをしたりすると症状が悪化する可能性があるため、できる限り安静に過ごしましょう。
抜歯後4〜7日|組織再生が進行
抜歯から4〜7日が経過すると、腫れや痛みは次第に落ち着き、組織の修復が本格的に進み始めます。
患部では、血餅の下に肉芽組織(にくがそしき)と呼ばれる新しい組織が形成され、傷口が内側から埋まっていきます。
この頃になると、患部が白っぽく見えることがありますが、それは膿ではなく治癒に必要な再生組織なので心配ありません。
違和感はまだ残るものの、痛みは軽減し、徐々に食事もしやすくなっていきます。
ただし、強くうがいをしたり、食べかすが患部に詰まることで感染を引き起こすケースもあります。
口腔内は清潔に保ち、抜歯した場所には歯ブラシを当てないようにしながら、やさしくケアしましょう。
また、刺激物の摂取や喫煙は避け、感染リスクを下げましょう。
抜歯後2週間|患部粘膜の上皮化が進む
術後2週間が経過すると、傷口の表面は新しい粘膜で覆われる(上皮化)段階に入ります。
歯茎がなめらかになり、見た目にも傷が落ち着いたように見えるため、完治したと誤解されやすい時期でもあります。
実際には、表面はふさがっていても内部の骨や歯槽部では再生が続いているため、引き続き丁寧なケアが必要です。
この時期には、医院からの指示で抜糸を行うこともあります。指定された抜糸のスケジュールは必ず守ってください。
抜歯後3〜4週間|患部の収縮と粘膜の安定化
3週間を過ぎる頃には、患部の穴が小さくなり、歯茎の表面の状態も安定してきます。
周囲の歯肉と色や質感がなじみ始め、舌で触れたときの違和感もかなり減少します。
見た目にはほとんど治っているように感じられますが、内部の骨の再生はこの時点でも進行中です。
油断せずに、引き続き口の中を優しくケアしながら過ごしましょう。
この時期からは、無理のない範囲で通常の食事へ移行していけるでしょう。
ただし、食べ物が詰まりやすいと感じる場合は、食後のうがいやケアを丁寧に行ってください。
抜歯後1〜2ヶ月|患部の最終的な治癒と安定
術後1ヶ月以上が経過すると、歯を抜いた穴は完全にふさがり、患部は周囲の歯肉とほとんど変わらない状態になります。
舌で触れても違和感はなくなり、出血や腫れ、痛みなどの症状も完全に解消していれば理想的な状態です。
ただし、抜いた場所には歯がないため、食べ物が溜まりやすくない状態は残ります。
以後も定期的に歯科医院で検診を受け、状態を確認してもらうことが望ましいです。
親知らず抜歯後の注意点
親知らずの抜歯後は、患部を清潔に保ちつつ、刺激を避けることが回復を早めるカギとなります。
ここでは、抜歯後に意識したい具体的な注意点を、時系列に沿ってわかりやすく解説します。
直後はガーゼを30分〜1時間しっかり噛む
抜歯直後は出血を抑えるため、ガーゼをしっかり噛んで圧迫止血を行うことが基本です。
血が止まる前にガーゼを外したり、うがいしたりすると、傷口の治癒に必要な血餅が流れてしまいます。
治癒が遅れるだけでなく、ドライソケットという合併症のリスクが高まります。
ガーゼは医師の指示がない限り、30分〜1時間を目安にしっかり噛んでおきましょう。
その後は、傷口をそっと保護する意識で過ごしてください。
麻酔が切れる前に痛み止めを服用する
抜歯後数時間は麻酔の効果で痛みを感じにくいですが、追って強い痛みがきます。
麻酔が切れる前に鎮痛薬を服用しておくことで、痛みのピークを軽減できるのです。
多くの人は、麻酔が切れた後の急な痛みに悩まされます。
処方された痛み止めは、あらかじめ指示されたタイミングで服用し、症状の悪化を防ぎましょう。
当日は安静に過ごす
親知らずの抜歯は小手術にあたる処置であるため、術後の身体は予想以上にダメージを受けています。
当日は、激しい運動はもちろん、外出もできるだけ控えましょう。
血流が促進されると再出血する可能性があるため、長時間の入浴や飲酒・喫煙も避け、できるだけ身体を休めることが大切です。
食事は麻酔が切れてからやわらかい物を摂る
麻酔が効いている間は、唇や舌の感覚が鈍く、誤って噛んだりやけどしたりするリスクがあります。
食事は麻酔が完全に切れた後に、刺激の少ない食品を摂りましょう。
おかゆ
豆腐
ヨーグルト
スープ類(熱すぎないもの)
ゼリー状の栄養食品
逆に、固いものや辛いもの、熱い飲食物は、患部に刺激を与えるため避けてください。
歯磨き・うがいは優しく
親知らずの抜歯後も、基本的な口腔ケアは重要ですが、患部を強く刺激するような歯磨きやうがいは厳禁です。
当日は軽くうがいをする程度にとどめましょう。
翌日以降もしばらくは、患部を避けながら周囲を丁寧に磨くことを意識しましょう。
可能であれば、マウスウォッシュは医師に相談したうえで使用することが望ましいです。
マウスウォッシュを使う場合、抜歯後24時間以内は避けてください。
抜歯後2日以降から、ノンアルコールタイプのマウスウォッシュを用法・用量を守って使用しましょう。
ただし、ぶくぶくと強いうがいはしないでください。
処方薬を決められた通り服用する
感染や炎症の予防のため、多くの場合は抗生物質や鎮痛薬が処方されます。
症状が落ち着いていても、自己判断で薬を中断したり飲む回数を減らしたりすると、再感染のリスクや治りの遅れにつながります。
薬は医師の指示通りに最後まで服用することが大前提です。
気になる痛みや腫れには患部を軽く冷やして対応
腫れや痛みが気になる場合は、保冷剤や冷やしたタオルを使って患部を外側から軽く冷やすことで症状を和らげることができます。
ただし、長時間の冷やしすぎは逆効果となるため、15〜20分を目安に冷やすようにしましょう。
また、氷や保冷剤を肌に直接当てるのは避けてください。布やタオルで包むと良いでしょう。
抜糸予定がある場合は必ず指示通りに受診
傷口を縫合した場合、多くのケースでは1週間前後で抜糸を行います。
痛みや腫れが落ち着いていると「もう行かなくていい」と思ってしまう人もいますが、糸の放置は厳禁です。
傷のトラブルや感染の原因になります。
医院の指示に従い、予定された通りに抜糸を行い、経過観察の診察を受けましょう。
親知らず抜歯後にしてはいけないこと
親知らずを抜いた後は、患部を守るための重要な「禁止事項」があります。
術後、痛みが引いてくると気が緩んでしまいますが、何気ない行動が傷の悪化や感染を引き起こす原因にもなるため注意してください。
ここでは、回復を妨げる代表的なNG行動とその理由を、医療的根拠に基づいて詳しく解説します。
強いうがい・患部の歯磨き
抜歯後にやってしまいがちな行動のひとつが、強くうがいをすることです。抜歯直後の強いうがいは厳禁です。
抜歯直後の傷口には血餅(けっぺい)という血の塊ができており、傷口を覆って保護する重要な役割を果たしています。
しかし、強くうがいすることで血餅を洗い流してしまい、ドライソケット(乾燥性抜歯窩)という合併症のリスクを高めます。
また、歯磨きの際に患部を直接こするのも厳禁です。
特に術後1週間程度は、傷口の周囲をやわらかい歯ブラシで丁寧に磨くにとどめ、患部への直接接触は避けましょう。
口腔内の清潔は重要ですが、患部を刺激しすぎると逆効果になる点に注意が必要です。
傷口を舌や指で触る
抜歯後は、口の中に違和感があるため、舌や指で患部を触ってしまうことがあります。
しかし、この行為は非常に危険です。血餅が剥がれてしまうだけでなく、指や舌を介して細菌が患部に入り込み、感染や炎症を引き起こすリスクがあります。
特に、手指は清潔とは限らないため、つい気になっても「触らない」が鉄則です。
どうしても違和感がある場合は、歯科医院に相談し、状況を確認してもらってください。
飲酒
術後の飲酒は、出血や痛みの悪化、治癒の遅延につながるため避けるべきです。
アルコールは血管を拡張し、血液の循環を促進する作用があるため、一度止まった出血が再開してしまう可能性があります。また、処方されている薬(鎮痛薬や抗生物質)とアルコールが相互作用を起こすと、薬の効果が弱まったり、副作用が強く出たりするリスクがあります。
少なくとも術後2〜3日は禁酒を徹底し、腫れや痛みが引いてから医師の判断を仰ぐようにしましょう。自己判断での飲酒は、回復を妨げます。
喫煙
喫煙は、親知らずの抜歯後に最も避けたい行為のひとつです。
タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、患部への酸素と栄養の供給を妨げるため、傷の治癒が遅れやすくなります。
また、喫煙によって口腔内が乾燥し、血餅が崩れてドライソケットが発生するリスクも大幅に上昇します。
喫煙者の治癒期間は非喫煙者に比べて長くなる傾向があり、再感染や再出血の確率も高まります。
理想は抜歯前後数日〜1週間は禁煙すること。親知らずの抜歯を機に、禁煙にチャレンジする人も少なくありません。
熱いお風呂やサウナ
抜歯当日は、血行を良くする行為全般を避ける必要があります。
中でも熱いお風呂やサウナは体温を上げすぎてしまい、出血を促進する原因になります。
また、湯あたりによって血圧が変動し、頭痛やふらつきなどの全身症状が出る可能性もあるため、安全面から見ても避けるべきです。
抜歯の当日はシャワー程度で済ませ、2〜3日はぬるめの湯で短時間の入浴に留めることが推奨されます。
医師から特に指示がある場合はそれに従いましょう。
激しい運動
ジョギングや筋トレなどの運動も、術後すぐには控えるべき行動のひとつです。
身体を動かすことで血流が促進され、止まったはずの出血が再開したり、腫れがひどくなったりすることがあります。
発汗によって脱水状態になるかもしれません。鎮痛薬を飲んだ状態での運動は、ふらつきや転倒などのリスクもあります。
原則、抜歯後2〜3日は安静に過ごし、その後は体調に応じて段階的に運動を再開していきましょう。
硬い食べ物や刺激の強い食べ物を食べる
抜歯後の患部はとてもデリケートな状態にあります。硬いもの(せんべい、ナッツ類など)を食べると、物理的に傷口を刺激し、再出血や血餅の剥がれの原因になります。
また、辛味・酸味・熱い食べ物も、化学的な刺激によって炎症を引き起こす恐れがあります。
術後1週間程度は、以下のような刺激の少ない柔らかい食品を摂りましょう。
- おかゆ、やわらかく煮たうどん
- 卵料理(卵とじなど)
- 常温のスープ、ヨーグルト、ゼリー
患部の経過を見ながら少しずつ通常の食事に戻していきましょう。
薬の服用を無断で中断・変更
痛みが引いたからといって、処方された薬を自己判断でやめてはいけません。
とくに抗生物質は最後まで飲み切らないと、口の中の細菌が再増殖し、感染症の発生に繋がります。
痛み止めも、定められたタイミングで服用することで、痛みをコントロールし、精神的な負担を軽減できるため重要です。
処方薬について、気になる副作用がある場合は、医師や薬剤師に相談してください。
親知らず抜歯後に再度病院へ行くべきケース
親知らずの抜歯後は、多少の腫れや痛みが出るものです。
しかし、予想以上の痛みや腫れに、「このまま様子を見ていいのか」「何か異常が起きているのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、理想的な経過とは異なる症状や、病院の再受診が必要とされるケースを具体的に紹介します。
ズキズキと強い痛みや腫れが3日以上続く
通常、術後の痛みや腫れは1〜3日がピークであり、その後徐々に落ち着いていきます。
にもかかわらず、4日目になってもズキズキと激しい痛みが続く場合は、ドライソケットや感染症が懸念されます。
ドライソケットは、傷口を保護する血餅が剥がれて骨が露出した状態。市販の痛み止めが効かないほどの痛みを伴うこともあります。
4日目以降にも強い痛みがある場合は、早めに歯科医院で処置を受けることが重要です。放置しても自然に治ることはないと考えられます。
口臭がきつい
抜歯後に口臭が強くなることは通常ありません。口の中に嫌なにおいがこもる、話す時に気になるほど臭いが強烈な場合は、感染症のサインと考えられます。
特に、抜歯部位から膿が出ているような感覚や、ドブのようなきついにおいがする場合は要注意です。
この場合、傷口に細菌が侵入し、膿のかたまり(膿瘍)や化膿性炎症を引き起こしている可能性があります。
新たな抗生物質や洗浄処置が必要となるため、速やかに歯科医院を受診してください。
白や黄色の膿が出る・膿のような味がする
抜歯部位から白や黄色のどろっとした液体が出る、または口の中に苦い・生臭い味が広がるといった症状も、細菌感染の代表的なサインです。
回復の過程で粘膜が白く見えることはありますが、液体状の分泌物が継続的に出るのは異常です。
溜まった膿を放置すると、歯茎の腫れや発熱・全身症状に発展するリスクも。早めの洗浄や抗菌薬の投与が必要です。
発熱(38℃前後)や寒気、全身のだるさがある
局所の腫れだけでなく、全身の症状が出た場合は要注意です。
特に38℃以上の発熱、寒気、倦怠感(体のだるさ)などがある場合、傷口の感染が全身に広がる兆候である可能性があります。
このような状態になると、口の中での感染にとどまらず、骨髄炎(こつずいえん)や蜂窩織炎(ほうかしきえん)などの重篤な感染症に進展することもあります。
少しでも体調に異変を感じたら、我慢せずすぐに医療機関を受診しましょう。
下唇や顎などに麻痺・しびれが続く
下の親知らずは、下歯槽神経と舌神経などの大事な神経に近い位置にある場合があります。
抜歯手術中にこの神経が刺激を受けると、下唇や顎、舌先のしびれや、皮膚・歯茎の麻痺、味覚障害が生じることがあります。
一時的なしびれであれば、数日〜数週間で自然に回復しますが、数日経っても麻痺や痺れが続く場合は神経損傷の可能性があります。早期の診断と対応が必要です。
神経の状態を確認するためには、レントゲンやCT撮影を行います。
麻痺や痺れの症状が続くときは、自己判断せず、必ず病院にかかってください。
まとめ
親知らずの抜歯後は不安になりやすいものです。
しかし、回復の経過や注意点を正しく知っておくことで、不要な心配をせずに落ち着いて対応できます。
抜歯後のトラブルを防ぐためには、患部を労わりながら安静に過ごすことも重要です。
予後の経過に少しでも不安があるときは、早めに歯科医院に相談することが何より安心です。
迷いや不安の相談には、歯科相談サービス【mamoru(マモル)】が便利です。
mamoruは、現役の歯科医師にオンラインで無料相談ができるサービスです。
スマホから気軽に相談できるので、忙しい方や歯科医院に行く前に話を聞きたい方にもぴったりです。
親知らずの抜歯は終わりではなく、口腔健康を見直すきっかけです。
口の中を正しくケアし、健康な口内環境を作っていきましょう。
新しく歯科医院を探したい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。