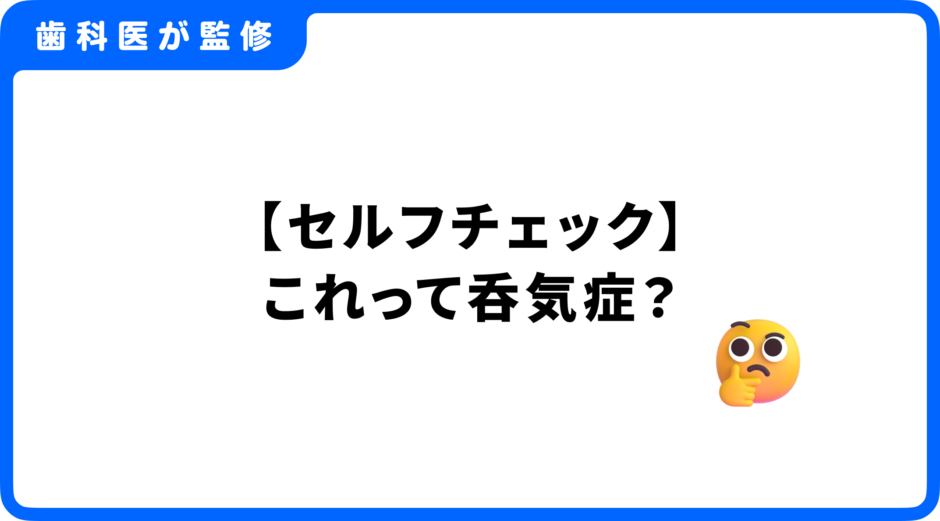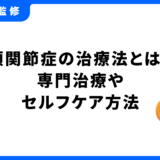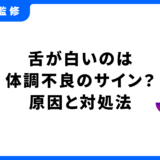「げっぷが止まらない」
「お腹が張って苦しい」
「おならの回数が気になる」
こんな症状に心当たりはありませんか?
実はそれ、呑気症(どんきしょう)と呼ばれる状態かもしれません。
呑気症は、無意識に空気を飲み込んでしまうことで起こります。
ストレスや早食いなどが原因です。消化器に異常がなくても、不快感がありますし、日常生活に支障をきたします。
本記事では、呑気症かを診断できるセルフチェック項目を紹介します。
さらに、呑気症の原因や症状、おならやげっぷを最小限にするセルフケアの具体例まで、わかりやすく解説します。
呑気症とは?
呑気症(どんきしょう)は、空気を飲み込むクセによる症状です。
日常的なげっぷやおなら、お腹のガス張りなど、誰にでも起こる不調の背景には、呑気症があるかもしれません。
呑気症は多くの場合、ストレスや無意識の行動が引き金となっています。
軽視すると、自分も周りも不快な思いをしてしまうなど、日常生活に支障をきたすかもしれません。
以下では、呑気症の定義や症状、他疾患との違いを紹介します。
呑気症(空気嚥下症)とは
呑気症とは、無意識に空気を飲み込んでしまう「空気嚥下症(くうきえんげしょう)」のことです。
食事や会話、緊張状態のときに空気を多く飲み込むことで、胃や腸にガスが溜まりやすくなり、発症します。
呑気症は、以下のような行動や状況で起こりやすいとされます。
- 早食いや、よく噛まずに飲み込む食習慣
- ストレスや緊張で唾液を頻繁に飲み込む癖
- 口呼吸
- 鼻炎などで鼻からの呼吸がしづらい場合
空気の飲み込みが常習化すると、さまざまなガス症状が引き起こされるのです。
呑気症による主な症状|げっぷ・おなら・お腹の張りなど
呑気症の代表的な症状は「げっぷ」や「おなら」、そして「お腹の張り(膨満感)」です。
これらは、胃腸に空気がたまることで引き起こされるガス症状です。
・げっぷの回数増加
・腸内ガスによるおならの増加
・お腹の張り・不快感・腹鳴(おなかが鳴る)
・胸のつかえ感や喉の違和感(空気が上がってくる感覚)
・ストレス・緊張による呼吸の浅さや食欲不振
頻繁なガス症状が続く場合、呑気症の可能性が疑われます。
症状が継続する場合は、医療機関に相談するのが望ましいでしょう。
呑気症と他の病気(消化器疾患など)の違い
消化器系の病気(胃腸炎・逆流性食道炎など)との大きな違いは「検査で異常が見つからないこと」です。
つまり、胃カメラや超音波検査などを受けても、呑気症の場合は器質的異常(目に見える病変)がありません。
呑気症と似たような症状が現れる病気には、以下があります。
| 症状 | 疑われる病気 |
| 胸焼け・げっぷが続く | 逆流性食道炎 |
| 腹痛・下痢・便秘が続く | 過敏性腸症候群(IBS) |
| 胃の痛みやムカつき | 胃炎・胃潰瘍・胃がん など |
これらの病気と呑気症は症状が似ているため、医師による診断が必要です。
「呑気症かも?」と思ったら、まずはセルフチェックを行い、必要に応じて内科や消化器科、または歯科に相談しましょう。
呑気症のセルフチェック|こんな症状がある人は要注意
呑気症は、無意識に空気を飲み込んでしまうことが原因で起こるため、自覚がないまま進行します。
そのため、まずはセルフチェックによって自身の状態を確認してみましょう。
呑気症セルフチェック項目
以下のチェックリストに当てはまる方は、呑気症の可能性があると考えられます。
- げっぷが1日に何度も出る
- おならの回数が増えたと感じる
- 食後にお腹が張ることが多い
- お腹の中でガスがたまっているような不快感がある
- 会話中や食事中、空気を多く飲み込んでいる気がする
- 唾液を頻繁に飲み込んでしまう癖がある
- ストレスや緊張の場面で症状が悪化する
- 鼻づまりなどにより口呼吸になっている
- 検査をしても明確な異常が見つからない
病院の受診目安
セルフチェックに該当した場合、または症状が日常生活に支障をきたすようであれば、医療機関の受診を検討してください。
特に以下の場合は受診をおすすめします。
- げっぷやおならが1日に何十回も出る
- お腹の張りが慢性的に続いている
- 食欲不振や眠りにくさなど、生活全体に影響が出ている
- ストレスを減らしても症状が改善しない
- 内科・消化器内科で検査しても異常が見つからない
- 口呼吸など、歯科的な問題が疑われる
基本的には内科・消化器内科を受診し、必要に応じて歯科にも相談すると良いでしょう。
特に食いしばりなど、口の中の構造が空気の飲み込みに影響している場合は、歯科からのアプローチが有効です。
呑気症の原因
呑気症は単なる癖や体質ではなく、複数の原因が重なって生じます。
主な要因には以下のようなものがあります。
- 心理的なストレス
- 食事の習慣
- 口腔の問題
- 鼻の病気など
ここでは、呑気症の代表的な原因と、原因別の対処法について解説します。
ストレスや緊張などの心理的な原因
呑気症の発症には、ストレスや緊張といった心理的要因が深く関係しています。
特に、仕事や対人関係などでストレスを感じる場面では、無意識に唾液を何度も飲み込んだり、呼吸が浅くなったりすることがあります。
このとき一緒に空気を飲み込む(空気嚥下)ことで、胃腸にガスが溜まりやすくなるのです。
また、不安障害や自律神経の乱れがある方は、げっぷやお腹の張りを訴えることが多く、呑気症の診断に至るケースも少なくありません。
ポイントは、「本人の気づかないうちに起こっている」ことです。
症状が慢性化している場合は、心理的な問題の解消も重要となります。
食事の早食いや唾液の飲み込み癖
早食いや、よく噛まずに飲み込む食事中の習慣も、呑気症の原因です。
早く食べようとすると、食べ物と一緒に大量の空気を飲み込んでしまいます。
また、緊張しているときに唾液を頻繁に飲み込む癖があると、そのたびに空気も少量ずつ体内に入り込み、蓄積されていきます。
以下のような食習慣がある方は注意が必要です。
- 5分〜10分以内に食事を終える
- 一口の量が多く、ほとんど噛まない
- 会話しながら早口で食べる
- 炭酸飲料やガムを頻繁に摂取する
食事中に空気を多く飲み込むことで、げっぷや腹部の張りが出やすくなります。
食べ方を変えることが、呑気症治療の第一歩になるという意識が重要です。
鼻炎
鼻の通りが悪く、口呼吸が増えると、空気を飲み込む回数が増加することがあります。
慢性的な鼻炎やアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などがあると、鼻からの呼吸がしづらくなり、代わりに口呼吸が増える傾向に。
口で呼吸をする際、舌や喉の筋肉の動きによって空気が食道に入り込みやすくなるため、呑気症を引き起こす原因になることがあります。
呑気症の診断と治療法|何科を受診すればいい?
呑気症が疑われる場合、何科を受診すべきか悩みますよね。
気になる症状によって、内科・消化器内科・歯科・耳鼻科など、かかるべき病院は異なります。
ここでは、自分の症状に合った医療機関を選ぶポイントを紹介します。
何科を受診すべきか
呑気症は、身体的・心理的・口腔的な要素が複合的に絡む症状です。
以下のように、最も気になる症状がどれかによって、かかる病院を判断してみてください。
| 気になる症状 | 相談すべき病院 |
| 胃の不快感・げっぷ・腹部の張り | 消化器内科または内科 |
| 鼻づまり・口呼吸 | 耳鼻咽喉科 |
| 噛み合わせや歯の問題 | 歯科・口腔外科 |
| ストレス・不安が強い | 心療内科・精神科 |
悩ましい場合は、一般内科で総合的に相談し、医師の判断で専門科に紹介してもらうと良いでしょう。
医師による診断方法と検査内容
呑気症は、問診と視診、必要に応じて行う検査によって総合的に判断されます。
診断の流れは以下の通りです。
- 問診・自覚症状の確認:
どのようなタイミングでげっぷやおならが出るのか、腹部の張り具合、食事の状況、ストレスの有無などを詳しくヒアリング。 - 身体検査・触診:
腹部の膨満感や圧痛の有無を確認し、ガスのたまり具合を観察。 - 内視鏡・エコー・血液検査:
他の消化器疾患(胃炎・逆流性食道炎・腫瘍など)との鑑別のために実施。 - 心理的評価:
ストレスや不安などの心理的背景が明らかな場合、心療内科との連携が図られる場合も。
呑気症が疑われる際には、日中の様子を記録したメモ(日誌)などが診断の参考になる場合もあります。
可能であれば、げっぷやおなら、腹部の不快感があったタイミングや状況を記録しておくと良いでしょう。
治療方法|生活指導・認知行動療法・薬物療法など
呑気症の治療は、原因に応じて多面的に行われます。
医師がすすめる治療法には、以下のようなものがあります。
- 生活指導:
食事の改善(よく噛む、早食いの防止)、会話のペース、姿勢の見直しなど。口呼吸を避けるための指導も含む。 - 認知行動療法(CBT):
ストレスや緊張が空気嚥下につながっている場合、考え方や行動のパターンを修正する心理療法が効果的。 - 薬物療法:
ガスの発生を抑える消泡剤、腸の動きを整える整腸剤、ストレスに対する軽い抗不安薬などが使われる。 - 歯科的アプローチ:
噛み合わせの調整やマウスピースの装着、食いしばりの改善によって空気の誤嚥を減らす。
症状が軽度であれば、生活習慣の見直しだけで改善するケースも多々あります。
一方で、ストレスや口腔機能の影響が大きい場合は、複数の診療科による連携が重要です。
呑気症に対するセルフケア・改善方法
呑気症は、日常のちょっとした習慣の見直しによって改善できる可能性が高いと言えます。
特に、食事や姿勢の改善、ストレス対策、口の中のケアを意識すること。空気の飲み込みが減り、症状の緩和が期待できるでしょう。
ただし、効果には個人差があり、全てのケースに当てはまるわけではありません。
ここでは、セルフケアの方法を具体的に紹介します。
食事の仕方や内容を見直す
呑気症の改善には、食事時に空気を飲み込みにくくする工夫が欠かせません。
具体的には、以下の点を意識しましょう。
- ひと口を小さくし、30回以上よく噛んでから飲み込む
- 食事には15分以上かけるようにし、ゆっくり食べる
- 会話しながらの早食いやながら食べを避ける
- 炭酸飲料やガムの摂取を控える
- 食後すぐに横にならないようにする(胃の中のガスが逆流するのを防ぐため)
これらの習慣を取り入れるだけでも、空気を飲み込む量は大きく減少します。
「よく噛むこと」が最も基本的かつ効果的な予防策であることを意識しましょう。
姿勢を改善する
日常の姿勢も、呑気症の予防・改善に関係しています。
猫背や前かがみの姿勢では、胃腸に空気がたまりやすくなり、げっぷや腹部の張りを助長します。
以下のポイントをおさえ、姿勢を改善しましょう。
- 食事中は背筋を伸ばして座る
- デスクワーク中は1時間ごとに立ち上がる
- 寝るときは横向きや上体を少し起こすなど、胃への圧迫を減らす
- スマートフォン使用中のうつむき姿勢を避ける
特に在宅勤務などで長時間座る方は、姿勢を意識的に正すことが、症状緩和に直結します。
正しい姿勢は胃腸の働きを助け、消化やガス排出にも好影響を与えます。
ストレスを管理する
心理的ストレスも呑気症の根本原因の一つであるため、ストレスマネジメントも改善に効果的です。
ストレスをケアすることで、自律神経を整えられ、呑気症以外の側面でも体調の改善が見込めます。
おすすめしたいストレスケア方法は、以下の通りです。
- 深呼吸や腹式呼吸を取り入れる
- 軽いストレッチやウォーキングなどの運動を習慣化する
- 趣味やリラックスできる時間を意識的に確保する
- 睡眠時間を十分に取る
「げっぷやおならが出る」「お腹が張る」という症状に過度に意識を向けすぎると、かえってストレスを強く感じることになり、悪循環になります。
認知行動療法の考え方を取り入れ、症状を柔軟に受け流すことも回復のカギとなるでしょう。
必要に応じて心療内科などを利用し、専門医へ相談してみてください。
歯の噛み合わせや食いしばりを改善する
口腔内の構造が呑気症に影響している可能性も一部で指摘されています。
とくに以下のような自覚がある場合は、歯科で相談してみるのがよいかもしれません。
- 噛み合わせがズレていると感じる
- 食いしばりや歯ぎしりを指摘されたことがある
- 口を閉じづらく、無意識に口が開いている
- 会話中に舌や顎が疲れやすい
歯科では、噛み合わせの調整や、ナイトガード(マウスピース)による食いしばりの緩和処置が行われます。
なお、噛み合わせの異常や歯ぎしりが空気の飲み込みに影響を与える可能性については一部で報告がありますが、呑気症との明確な因果関係を示す科学的な証拠は限定的です。
そのため、根本的な治療法としての有効性はまだ確立されていませんが、症状の背景に歯科的な問題が関与している場合もあるため、必要に応じて専門機関に相談することが勧められます。
鼻炎を治療する
慢性的な鼻づまりがあると口呼吸が習慣化しやすく、無意識の空気の飲み込み(空気嚥下)につながる可能性があります。
その結果、げっぷや腹部の膨満感といった症状が悪化することもあるため、口呼吸の背景に鼻の不調がある場合は、耳鼻咽喉科への相談してみてはいかがでしょうか。
以下のような症状に心当たりがある方は、一度医療機関での相談を検討してみましょう。
- 季節を問わず鼻が詰まりやすい
- 鼻水・くしゃみが続く
- 寝ている間に口呼吸になっていると指摘される
- 口が乾きやすく喉がイガイガする
耳鼻咽喉科では、薬物療法(抗アレルギー薬・点鼻薬)やアレルゲン除去の指導などが行われ、呼吸の通りが改善されることで、口呼吸の抑制に役立つ可能性があります。
ただし、鼻炎治療が呑気症そのものを直接改善するという明確な科学的根拠は現時点では確立されていません。
あくまで空気の過剰な飲み込みにつながるリスク要因(口呼吸)を減らす一手段として、必要に応じて治療を検討するとよいでしょう。
まとめ|「呑気症かも」と思ったら、今すぐチェック&行動を
呑気症は、誰にでも起こり得る身近な症状です。しかし、「げっぷが止まらない」「お腹の張りがつらい」「ガスがたまりやすい」などの悩みは、早めに解消したいですよね。
まずはセルフチェックで状態を確認し、必要に応じて医療機関を受診しましょう。
また、呑気症が歯科的な要因と関係している場合は、歯科治療が改善に貢献できるかもしれません。
歯の噛み合わせや食いしばりが気になる方は、オンラインで気軽に相談できる「mamoru」などのサービスを活用し、自分に合った医療機関を見つけてみてください。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。