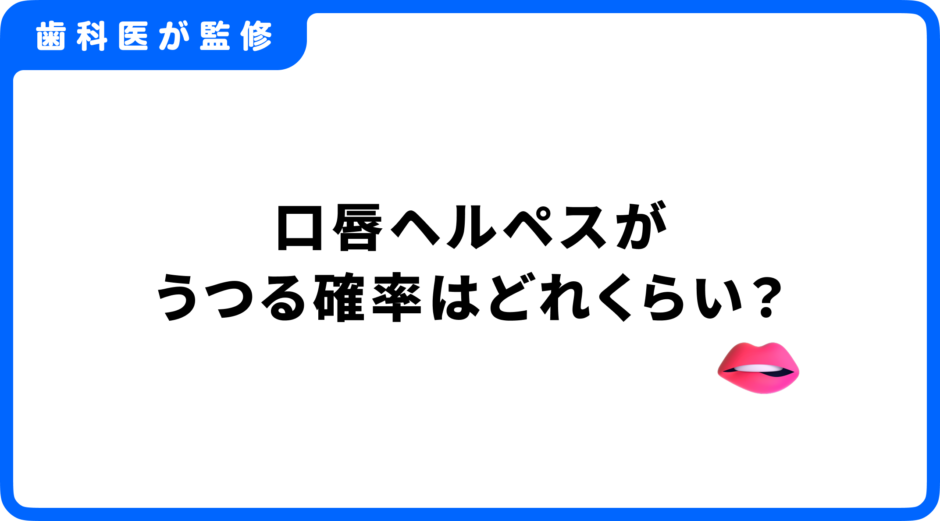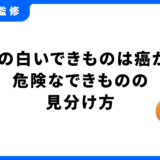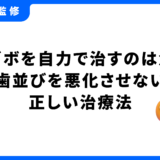「口唇ヘルペスがうつる確率は?」
「本当に感染するの?」
口唇ヘルペスを家族や周りの人にうつしそうで、不安を感じている方も多いでしょう。
口唇ヘルペスなどの唇のまわりにできる水ぶくれは、見た目が良くないだけでなく、他人へうつすリスクのある症状です。正しい知識に基づいて、感染を予防する必要があります。
本記事では、
- 口唇ヘルペスの原因
- 口唇ヘルペスがうつる確率
- 口唇ヘルペスの予防法・治療法
まで、歯科医療の観点で解説します。
「人にうつさない」「自分も感染を繰り返さない」ために、今日から対策を行いましょう。
口唇ヘルペスとはどんな病気?
唇のまわりに繰り返しできる水ぶくれ。それは「口唇ヘルペス」かもしれません。
口唇ヘルペスは、多くの人が一般的に保有する「ヘルペスウイルス」によって引き起こされる、感染力の強い病気です。
まずは口唇ヘルペスという病気について正しく理解しましょう。
ヘルペスウイルスの種類
口唇ヘルペスは、「単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)」というウイルスが原因で起こる感染症です。
一度感染するとウイルスは体内から完全に消えることはありません。
三叉神経節(さんさしんけいせつ)という神経の中に潜伏し、体調不良やストレス、紫外線の影響、免疫力の低下などをきっかけに病気を再発させます。
ヘルペスウイルスには複数の種類があり、代表的なものは以下のとおりです。
| ウイルスの種類 | 主な症状・病気 |
| HSV-1(単純ヘルペスウイルス1型) | 口唇ヘルペス、角膜ヘルペス |
| HSV-2(単純ヘルペスウイルス2型) | 性器ヘルペス |
| VZV(水痘・帯状疱疹ウイルス) | 水ぼうそう、帯状疱疹 |
特にHSV-1は、日本人の成人の7〜8割以上が保有しているとされ、非常に身近なウイルスです。感染しても無症状のまま経過するケースも少なくありません。
HSV-1による病気を発症した場合、「初感染」か「再発」かによって症状の出方が異なります。
このように、ヘルペスウイルスは多くの人が保有するごく一般的なウイルスであり、症状の有無はその人の抵抗力や生活習慣に大きく左右されるのです。
口唇ヘルペスの症状
口唇ヘルペスの最も特徴的な症状は、唇のまわりや口の端に現れる「水ぶくれ」です。
口唇ヘルペスの初期症状として「ピリピリ」「チクチク」とした違和感やかゆみを感じることが多く、この段階で治療を開始すれば、水ぶくれの重症化を防げる可能性が高くなります。
一般的に、口唇ヘルペスの症状は以下のように進行します。
- 前兆期:ピリピリ、ムズムズ、違和感
- 炎症期:赤み、腫れ、熱感
- 水疱期:小さな水ぶくれが集まって出現り
- 潰瘍期:水ぶくれが破れ、びらん化
- 痂皮期(かさぶた):乾燥し、治癒へ向かう
上記の段階のうち、水ぶくれができてから潰れるまでの期間が最も感染力が高く、他人にうつしやすいとされます。
水疱の中には大量のウイルスが存在しているため、家族やパートナーとの接触に注意が必要です。
また、初めて感染する場合(初感染時)には、発熱や全身倦怠感、口内炎のような粘膜のただれが広範囲に出ることもあり、より重症化しやすい傾向があります。
一方、再発時は軽症で済むケースが多く、症状も数日〜10日前後で自然に治まるのが一般的です。
唇のできものについて詳しく知りたい人は以下の関連記事も参考にしてください。
▶関連記事:唇にできものができて痛い!痛みの原因と対処法、予防策まで解説
▶関連記事:唇のしこりは危険?原因と見分け方、受診の目安を徹底解説
性器ヘルペスとの違い
口唇ヘルペスと性器ヘルペスは、どちらも「単純ヘルペスウイルス(HSV)」による感染症ですが、原因となるウイルスの型や感染部位、感染経路などに違いがあります。
| 比較項目 | 口唇ヘルペス(HSV-1) | 性器ヘルペス(HSV-2) |
| 主な感染部位 | 唇・口周辺 | 性器・肛門周辺 |
| 主な感染経路 | 接触・キス・共有物 | 性交渉・オーラルセックス |
| 初感染の重症度 | 軽症〜中等度 | 強い痛みや発熱を伴うことも |
| 再発の頻度 | 少なめ | 多め(再発しやすい) |
最近では、オーラルセックスを通じてHSV-1が性器に感染するケースも増えており、部位とウイルス型の関係が逆転することもあります。
また、口唇ヘルペスを持つ人がパートナーに性器ヘルペスをうつすリスクもあるため、口唇ヘルペスの症状が出ている間の性交渉は避けるべきです。
どちらのタイプも感染力が強く、症状のあるときは注意が必要な病気であることには変わりありません。
口唇ヘルペスの原因
口唇ヘルペスの原因は、「単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)」の感染によるものです。
HSV-1は非常に感染力が高く、HSV-1の感染経路は、以下のように多岐にわたります。
子ども同士のスキンシップや家族内の接触を通じて、幼少期に感染しているケースも多く見られます。
重要なのは、一度体内に入ったウイルスは神経の奥深く(神経節)に潜伏し、完全には排除されないという点です。そのため、治癒=完治ではなく、体調を崩したりストレスがかかったりした際に、再びウイルスが活性化して症状が再発する可能性があります。
これが、口唇ヘルペスが「繰り返しできる」病気である理由です。
ウイルスを持っていても発症しない「不顕性感染者」が一定数存在し、自覚のないまま他人にうつしてしまうリスクがあります。
さらに、紫外線や月経、睡眠不足、発熱なども引き金となることがあるため、予防においては免疫力の維持が極めて重要です。
つまり口唇ヘルペスは、ウイルスとの共存を前提とした再発型の感染症なのです。
口唇ヘルペスがうつる確率
「口唇ヘルペスはどのくらいの確率で人にうつるの?」と心配になるのも当然です。
ここでは、ヘルペスがうつりやすい時期や、感染経路と予防法まで、わかりやすく解説します。
口唇ヘルペスがうつりやすい時期・季節
口唇ヘルペスは、冬から春にかけての寒暖差が大きい時期や、免疫力が落ちやすい梅雨や年末年始などに再発リスクが高まると言われています。とくに風邪やインフルエンザなどで体力が落ちているときは要注意です。
口唇ヘルペスの症状経過とうつりやすさ
口唇ヘルペスの感染力は、症状の進行段階によって大きく変化します。
発症から治癒までにはいくつかのステージがあり、それぞれの段階でうつる確率(感染リスク)に違いがあります。
| 症状の段階 | 状態 | 感染リスク |
| 前兆期 | ピリピリ・かゆみ・違和感 | 低〜中 |
| 水疱期 | 小さな水ぶくれができる | 非常に高い |
| 潰瘍期 | 水疱が破れてただれる | 高い |
| 痂皮期 | かさぶたができて乾燥 | 中〜低 |
| 治癒期 | 完全に乾燥・再発なし | ほぼなし |
特に感染力が強いのは水疱期と潰瘍期で、キスや皮膚との直接接触、タオルの共用、誤って患部に触れた手からの間接接触などで感染する可能性が高まります。
一方、症状のない潜伏期やかさぶたが取れたあとの時期には、2~8%の確率でウイルスが排出されていることがあり、感染力はかなり低下します。それでも油断は禁物です。
再発前の「前兆期」でも微量なウイルスが分泌されている可能性があるため、日常の接触に注意を払う必要があります。
口唇ヘルペスの感染経路
口唇ヘルペスは、主に「接触感染」によって広がります。具体的には、ウイルスを含んだ体液や水疱の内容物が、相手の皮膚や粘膜に触れることで感染が起こります。以下に代表的な感染経路を詳しく解説します。
キスや性行為による感染
もっとも感染リスクが高いのが「キス」です。
とくに水疱が出ている状態でのキスは、直接的な粘膜接触となるため、うつる確率は極めて高いと考えられています。
恋人や配偶者だけでなく、小さなお子さんへのスキンシップにも注意が必要です。
また、オーラルセックスを通じてHSV-1が性器に感染し、性器ヘルペスを引き起こすケースも増えています。
キスや性的接触などの粘膜接触によるHSV-1の感染確率は、おおよそ30〜50%とする研究報告があります。
性器ヘルペスの原因はHSV-2が多いとされていますが、近年ではHSV-1による性器感染も増加傾向にあり、部位と型が一致しないことがあるのです。
パートナーのためには、発症中の性交渉やオーラルセックスは避けることが思いやりであり、感染予防においても非常に重要です。
食器やタオルの共有による感染
家庭内でよくあるのが、食器やタオルの共有による間接的な感染です。ウイルスは唾液や水疱内に存在するため、コップや箸、スプーンなどの共有によっても感染するリスクがあります。
口唇ヘルペスの発症中はウイルスが活性化しているため、乾燥していない患部が物に触れることで、他人の粘膜へうつる可能性も。
同様に、フェイスタオルや枕カバーの共有にも注意が必要です。家族や同居人がいる場合は、タオルや食器は自分専用にし、共有物の衛生管理を徹底することが大切です。
口唇ヘルペスに感染しないための予防方法
感染力の強い口唇ヘルペスですが、正しい知識に基づいて行動すれば十分に予防は可能です。予防のポイントは「接触を避けること」と「免疫力を保つこと」の2点に集約されます。
口唇ヘルペスを予防するための具体的な対策は以下のとおりです。
口唇ヘルペスの発症を繰り返す人には、「PIT(予防的インターミッテント療法)」と呼ばれる再発抑制の内服治療が検討される場合もあります。
市販薬による治療や対策では限界があるため、定期的に再発する場合は病院に相談してみてください。
口唇ヘルペスの治療方法
口唇ヘルペスは数週間で自然治癒することもありますが、適切に治療すれば再発の抑制も期待できます。
口唇ヘルペスの基本的な治療法は、「抗ウイルス薬」の使用です。抗ウイルス薬にはウイルスの増殖を抑える作用があり、症状の出始め(前兆期や初期)に使うことで、水ぶくれの発生や悪化を防ぎ、症状の軽減・治癒の早期化を期待できます。
口唇ヘルペスの治療薬には、以下のように種類があります。
| 治療薬の分類 | 用法 | 特徴 |
| 内服薬(飲み薬) | 水などと一緒に服用 | 再発を繰り返す場合や重症な場合に使われる。処方薬が中心。 |
| 外用薬(塗り薬) | 患部に直接塗布 | 感染初期の違和感や水疱に有効。市販薬もある。 |
| PIT療法(再発抑制療法) | 再発前に予防的に服用 | 発症を繰り返す人に対し、医師が使用を提案する場合がある。 |
有効成分として代表的なのは、アシクロビル・バラシクロビル・ファムシクロビルなどで、ウイルスのDNA複製を阻害する働きがあります。
いずれも早期使用で効果を発揮するため、「口唇ヘルペスの前兆かも」と思ったらできるだけ早く服用・塗布すると良いでしょう。
ヘルペスの症状が軽いからと放置すると、患部を無意識に触ったり掻いたりしてしまい、角膜ヘルペスや別の部位への自己感染を引き起こす場合もあります。
市販薬でもある程度の対処は可能ですが、医療機関を受診して速やかに治療することが推奨されます。
口唇ヘルペスの治し方について詳しく知りたい人は、以下の関連記事も参考にしてください。
▶関連記事:口唇ヘルペスを最短で治す方法は?跡を残さないための治療法と市販薬との違い
口唇ヘルペスの症状が出た時の対処法や注意点
口唇ヘルペスは、軽い皮膚トラブルとして軽視しがちですが、油断すると他人へうつしたり、自分の別の部位への再感染を招いたりするおそれがあります。
「ただの水ぶくれ」と侮ってはいけません。感染症であることを理解し、日常生活での接触やケアに注意を払いましょう。本章では、具体的な注意点を紹介します。
人にうつさないように接触に配慮する
口唇ヘルペスは、発症中に周囲にうつすリスクが非常に高い病気です。
とくに水疱や潰瘍のある期間はウイルス量が多く、直接的な接触だけでなく間接的な接触でも感染させることがあります。
そのため、以下のような行動は避けましょう。
- キスやオーラルセックスなど、唇や粘膜を介した接触行為
- タオル・枕カバー・コップ・箸・口紅などの共有
- 乳幼児との頬ずりやスキンシップ(免疫が未熟な子は重症化のリスクも)
また、ウイルスは手や指にも付着する可能性があるため、患部を触ったあとは必ず石けんと流水で手を洗ってください。
アルコール消毒では完全に除去できないこともあるため、石けんによる手洗いを徹底しましょう。
同居している家族やパートナーへの思いやりとして、発症中は「ヘルペスをうつしてしまうかも」という危機意識を持つことが大切です。
自分が角膜ヘルペスにならないよう注意する
口唇ヘルペスにかかった際、注意すべきなのは「自己感染」です。とくに危険なのは「角膜ヘルペス(ヘルペス性角膜炎)」で、これはウイルスが目に入ることで起こる深刻な合併症の一つです。
角膜ヘルペスを発症すると、以下のような症状が現れることがあります。
角膜ヘルペスを放置すると、角膜が濁って視力障害や失明の原因になることもあるため、症状が現れた場合は速やかに眼科を受診してください。
口唇ヘルペスの水疱に触れた手で目をこする行為は非常に危険です。
患部に触ったあとは目や鼻には絶対に触れないようにし、よく手洗いをした上で、メガネの着脱や化粧、コンタクトの装着なども注意して行います。
また、コンタクトレンズの装着によって目に傷がつくと、ヘルペスウイルスが侵入しやすくなります。
ヘルペスの発症中はメガネに切り替えることも検討すると良いでしょう。
口唇ヘルペスがうつる確率についてのよくある質問
ここでは、口唇ヘルペスの感染に関するよくある質問に回答します。
口唇ヘルペスが「うつらない人」はいる?
はい、実際に「ウイルスに感染しても発症しない人」は存在します。
これは「不顕性感染」と呼ばれ、ヘルペスウイルスが体内に存在していても、免疫の働きによって症状が現れない状態を指します。
そのため、ヘルペスが「うつらない」のではなく、「うつっていても気づかない」という状態です。
また、すでにHSV-1に感染している人は、同じウイルスへの再感染リスクは低いため、症状としては現れにくい傾向があります。
しかし、体調不良や免疫力の低下によって再発する可能性はあるため、完全に無関係ではありません。
口唇ヘルペスがあると性行為ができない?
口唇ヘルペスの発症中はオーラルセックスを含む性行為は避けるべきです。
口唇ヘルペスの水ぶくれには活性化したウイルスが含まれており、粘膜との接触を通じてHSV-1が性器に感染し、性器ヘルペスを引き起こすことがあります。
とくに、性器にHSV-1が感染した場合は再発しやすく、パートナー間でウイルスを行き来させてしまうおそれがあります。症状が出ている期間は性行為全般を控えましょう。
見た目からは治ったように見えても、ウイルスの活動が完全に収まるまでは感染リスクがゼロにはなりません。医師の指導を受けながら経過を見つつ行動しましょう。
口唇ヘルペスは空気感染する?
いいえ、口唇ヘルペスは空気感染しません。
感染経路はあくまで接触感染であり、くしゃみや咳で空中に漂ったヘルペスウイルスが他人に感染することは基本的にありません。
水疱が破れた際の体液や唾液が直接皮膚や粘膜に触れた場合、感染する可能性があるため、会話中の飛沫や咳が口元に飛ぶような距離での接触は避ける方が安心です。
また、マスクの内側にウイルスが付着し、それを手で触ったあとに目や口に触れると、間接的に感染するリスクはあるでしょう。
口唇ヘルペスの感染ルートは、空気ではなく「手や物を介した接触」であることを知っておいてください。
口唇ヘルペスはいつまでうつる?
口唇ヘルペスの感染力が最も高いのは「水疱が出現してからかさぶたになるまで」の期間です。個人差はありますが、通常は発症から7〜10日程度がこの期間に該当します。
以下が感染力の目安です。
| 症状の段階 | 期間の目安 | 感染力 |
| 前兆期 | 0〜1日目 | 低い |
| 水疱期 | 2〜5日目 | 非常に高い |
| 潰瘍期 | 5〜7日目 | 高い |
| 痂皮期 | 7〜10日目 | 中〜低 |
| 完全治癒 | 10日目以降 | ほぼゼロ |
症状が完全におさまっていても、ウイルスが放出されているため感染リスクはあります。目安として、2週間程度は接触や共有物への配慮を続けましょう。
乳幼児や高齢者、免疫力が低下している方が身近にいる場合は、より慎重な行動を心がけてください。
まとめ
口唇ヘルペスは、単純ヘルペスウイルス(HSV-1)による再発性の感染症で、多くの人が保有するウイルスです。
水ぶくれが出ている時期はとくに感染力が高く、キスやタオルの共用などでうつる可能性があります。
口唇ヘルペスがうつるケースを正しく理解し、手洗いや接触に配慮するなど、予防と対策を行ってください。
口唇ヘルペスの症状に気づいたら、安易に自己判断せず、皮膚科や内科などの医療機関を受診すると安心です。
「どこに相談すればいいかわからない」「これを機に、信頼できるかかりつけの歯医者さんを見つけたい」という方には、予防歯科サービス「歯科まもる予約」 の活用がおすすめです。
「mamoru」は、あなたに合った歯科医院探しをサポートし、お口の健康を守るパートナーを見つけるお手伝いをします。
お口の小さな異変を見逃さず、健康な毎日を送るために、ぜひご活用ください。