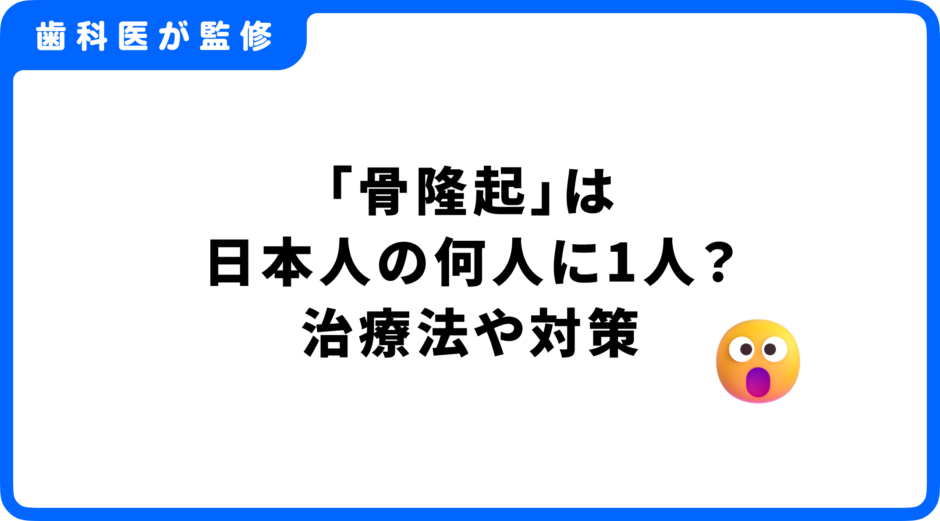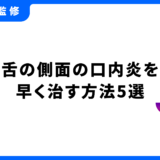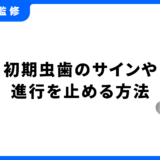「口の中にできたこの硬いコブ、一体何……?」
「骨隆起って、実際どのくらいの人がなるものなの? もしかして珍しい?」
口の中にできた原因不明のでっぱりに、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「骨隆起ができるのは何人に1人か」という疑問への回答はもちろん、以下の内容を丁寧に解説します。
- 骨隆起ができる理由
- 骨隆起を放置するリスク
- 骨隆起の治療は必要か
- 自分でできる骨隆起対策・予防法
結論からお伝えすると、骨隆起は決して珍しいものではなく、日本人の約3人に1人に見られる(有病率30-35%)と言われています。周りにも、骨隆起の症状がある人は大勢いるのです。
骨隆起についての基礎知識を詳しく押さえておきましょう。
骨隆起とは?口の中にできる硬いコブの正体
口の中にいつの間にか硬いコブのようなものができて、不安に感じていませんか?
それは「骨隆起(こつりゅうき)」かもしれません。
ここでは、骨隆起の正体や、骨隆起の起きやすい場所など、骨隆起の概要について解説します。
骨が異常に発育する「骨隆起」(外骨症)
口の中にできる硬いコブの多くは、骨が異常に発育した「骨隆起」の状態である可能性が高いです。
これは「外骨症(がいこつしょう)」とも呼ばれ、骨自体が部分的に盛り上がった状態を指します。病的な腫瘍(しゅよう)ではありません。
骨隆起のおもな特徴は以下の通りです。
| 硬さ | 指で触ると骨のように硬い。 |
| 形状 | 表面は滑らかで、コブのように丸く盛り上がっている。 |
| 色 | 周囲の歯茎と同じようなピンク色をしている。 |
| 成長 | ゆっくりと時間をかけて大きくなることがある。 |
骨隆起の多くは基本的に良性で、体に悪影響を及ぼすことはありません。しかし、その状態や大きさによっては、日常生活に支障をきたす可能性も考えられます。
まずは口の中の症状が骨隆起なのか、正しく判断する必要があります。
骨隆起がよく見られる3つの部位
骨隆起は、口の中の決まった部位にできやすいという特徴があり、およそ3つの場所に絞られます。骨隆起が現れる場所によって、以下の3つに分類されます。
下顎隆起(かがくりゅうき)
下の歯の内側、舌が触れる部分にできる骨の隆起です。左右対称に、奥歯にかけて複数個ボコボコとできることが多く、骨隆起の中では最も発生頻度が高いとされています。
口蓋隆起(こうがいりゅうき)
上あごの天井部分(こうがい)の真ん中にできる骨の隆起です。通常、隆起は1つで、左右対称のなだらかなコブ状をしています。
歯槽隆起(しそうりゅうき)
歯を支える歯槽骨が、歯茎の外側に盛り上がってできるものです。特に、犬歯や小臼歯のあたりによく見られます。
鏡で自分の口の中を観察し、上のいずれかに該当する硬い盛り上がりがないかチェックしてみましょう。
骨隆起の症状が見られる人の割合
「骨隆起があるのは自分だけ?」と心配になるかもしれませんが、骨隆起の発生は決して珍しいことではありません。
日本人における部位別の骨隆起発生率は、下顎隆起は約22〜26%、口蓋隆起は10〜25%程度という報告があり、欧米人と比較しても高い傾向にあります。
また、医学的な調査によれば、肉眼で見てはっきりとわかるような下顎隆起が見られる日本人は約22%でしたが、触診(指で触って診察すること)で認められるケースを含めると、その割合は約40%にものぼることがわかっています。
骨隆起の自覚症状がないまま過ごしている人も少なくないでしょう。
痛みなどがなくても、まずは自分の口の中に骨隆起があるかどうかを確認してみましょう。
骨隆起はなぜできるのか?代表的な4つの原因
骨隆起ができてしまう原因はいくつか考えられます。
多くは、顎の骨に過剰な力がかかったせいや遺伝的な要因など、複数の要素が絡み合って発生すると言われています。
本章では、骨隆起ができる代表的な4つの原因について詳しく見ていきましょう。
- 歯ぎしり・食いしばりによる顎の骨への負担
- 間接的なストレスによる顎への影響
- 噛み合わせ・遺伝的な要因
- 加齢・生活習慣の変化
1. 歯ぎしり・食いしばりによる顎の骨への負担
骨隆起ができる最大の原因は、歯ぎしりや食いしばりによる顎の骨への過剰な負担です。
睡眠中など無意識のうちに行われる歯ぎしりや食いしばりによって、食事の時とは比べ物にならないほどの強い力が歯や顎にかかります。
顎への強い圧力が継続的に加わることで、顎の骨が刺激から自らを守ろうとする作用により、硬く厚くなろうとします。骨へのこの機械的刺激が、結果として骨隆起という形で現れるのです。
特に、奥歯を強く噛みしめる癖のある人は、下顎や歯槽骨に隆起ができやすい傾向にあります。
2. 間接的なストレスによる顎への影響
ストレスが歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)を誘発すると、結果的に骨隆起の形成に影響を与える可能性があります。しかし、ストレス単体が骨隆起の原因であると証明されてはいません。
ストレスを感じると、無意識のうちに歯を食いしばったり、筋肉が緊張したりすることがあります。この緊張状態が続くと、顎周りの筋肉がこわばり、結果として顎の骨に過剰な負担をかけることになります。
また、ストレスは睡眠中の歯ぎしりを誘発あるいは悪化させることも知られています。
不規則な生活習慣や精神的なプレッシャーが、間接的に骨隆起の形成を促している可能性があるのです。
3. 噛み合わせ・遺伝的な要因
噛み合わせの悪さも、骨隆起の原因となり得ます。
特定の歯だけが強く当たるなど、噛み合わせのバランスが悪いと、一部の顎の骨に力が集中します。この慢性的な刺激が、骨の過剰な発育を促すことがあるのです。
また、骨隆起には遺伝的な要因と環境要因(咀嚼力、食習慣)の相互作用も関係していると考えられています。
親子で似通った場所に骨隆起が見られるケースから考えられるように、骨の形や硬さ、噛む力などの体質が受け継がれることで骨隆起ができやすくなる可能性は否定できません。
歯並びも遺伝の影響を受けるため、噛み合わせのバランスに影響を与え、骨隆起の間接的な原因となっている可能性も考えられます。
4. 加齢・生活習慣の変化
加齢に伴う身体の変化も、骨隆起の発生に関係しています。
年齢を重ねることで、長年にわたる噛み合わせの負担が蓄積され、骨が徐々に隆起してくることがあります。年齢を重ねるにつれて骨が変化し、隆起が大きくなる可能性もあります。
ただし、骨隆起の発生は加齢とともに増加するという報告に対して若年層(20〜40代)に多いとする報告もあるため、年齢が原因であるとは一概に言えません。
また、ホルモンバランスの変化が骨の代謝に影響を与えている可能性も指摘されています。さらに、硬いものを好んで食べる食生活や、スポーツで歯を食いしばる習慣なども、顎の骨に負担をかける要因となります。
若い頃には見られなかった骨隆起が中年以降になってから現れるのは、こうした長年の生活習慣の蓄積が変化となって現れた結果と言えるでしょう。
これって骨隆起?症状とセルフチェックリスト
口の中にできたコブが骨隆起なのか、それとも別の病気なのか、自分で判断するのは難しいものです。
ここでは、骨隆起の主な症状やセルフチェックポイントについて解説します。
骨隆起の主な症状
骨隆起の最も大きな特徴は、痛みやしびれといった症状は基本的にないことです。
多くの場合、舌で触った時の違和感や、鏡で見た時の見た目の変化で初めてその存在に気づきます。
以下のような状態であれば、骨隆起の可能性が高いと考えられます。
隆起が大きくなってくると、会話や食事の際に舌が当たって話しにくさを感じたり、食べ物がスムーズに飲み込めなかったり、何らかの違和感が生じることがあります。
表面の粘膜が薄く、口内炎になりやすいのが特徴
骨隆起がある部分の粘膜は、骨に押し上げられて薄くなっているため、非常にデリケートな状態です。
そのため、硬い食べ物が当たったり、歯ブラシが強く擦れたりするなどの些細な刺激で傷がつきやすく、口内炎を繰り返すことがあります。一度炎症が起きると、なかなか治りにくいのも特徴です。
口の中の同じ場所が頻繁に口内炎になる場合は、その下に骨隆起が隠れているかもしれません。
骨隆起でなくほかの病気の可能性も
口の中にできるコブは、すべてが骨隆起とは限りません。
口の中にコブができる症状は、口腔がんなどの悪性腫瘍である可能性も潜んでいます。
以下のような特徴が見られる場合は、自己判断せずすぐに歯科医院や口腔外科で医師の診療を受けましょう。
これらの症状がある場合、骨隆起以外の病気のサインかもしれません。
不安な場合は専門家に相談するのが早いです。まずはかかりつけの歯科医院で症状を診てもらいましょう。
骨隆起は放置しても大丈夫?考えられるリスク
骨隆起があることがわかったら「このまま放置して大丈夫なのだろうか?」と心配になりますよね。
ここでは、骨隆起を放置した場合に考えられるリスクについて解説します。
【前提】基本的には無害で治療は必要ないケースが多い
結論から言うと、骨隆起は骨の塊であり、腫瘍のように転移したり、命に関わるような病気に発展したりすることはありません。骨隆起の多くは無害であり、体に直接的な害を及ぼすことはないものです。
日常生活に特に問題がなければ急いで治療をする必要はなく、経過観察となるケースがほとんどです。
したがって、多くの場合は健康上の心配はいりませんが、生活上の不便やリスクが存在することは知っておきましょう。
入れ歯(義歯)の装着に支障が出る
将来的に入れ歯(義歯)を作製する際、骨隆起が問題となるケースがあります。
特に大きな骨隆起があると、入れ歯が安定せず痛みが出たり、うまく装着できなかったりする原因となります。
総入れ歯はもちろん、部分入れ歯であっても、骨隆起が邪魔をして設計通りに作れないことも。そのため、将来的に入れ歯が必要になった時のために、歯科医師から骨隆起の切除を勧められるケースがあります。
現在入れ歯を使用していて不具合を感じている方や、将来的に入れ歯を検討している方は、一度歯科医師に相談してみると良いでしょう。
食事がしにくく発音が不明瞭になる
下顎や上顎の骨隆起が大きくなると、舌の動きが制限され、日常生活に支障をきたす場合があります。
例えば、食事の際に食べ物がコブに当たって痛んだり、飲み込みにくさを感じたり。
舌の動きが妨げられることで、特定の音が発音しにくくなるなど、発音に影響が出るケースもあります。特に、サ行やタ行、ラ行などの発音が不明瞭になる傾向があります。
これらの症状は、生活の質(QOL)を低下させる要因となるため、気になる場合は骨隆起の治療を検討する必要があります。
口腔ケアがしづらく、虫歯や歯周病の遠因になる
骨隆起の周りは複雑な形態になりがちで歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすくなります。口の中を十分きれいにするのが難しいため、虫歯や歯周病のリスクを高める可能性を否定できません。
隆起した部分の歯茎は薄くデリケートなので、無理な磨き方をすると傷つけてしまうおそれもあります。
しかし、汚れを放置すると歯周病が進行し、最悪の場合には歯を失うことも。
骨隆起がある方は、セルフケアを特に丁寧に行い、歯科医院で定期的にプロフェッショナルケアを受けることが推奨されます。
骨隆起の治療法と自分でできる対策
骨隆起による痛みや不便を感じる場合、どのような治療法が検討できるのでしょうか。
ここでは、骨隆起の外科的な治療から、自分でできる対策や予防法まで詳しく解説します。
治療:切除手術
日常生活に支障をきたすような大きな骨隆起に対しては、外科的に切除する手術が選択されます。
この手術は一般的に「骨隆起切除術」と呼ばれ、歯科口腔外科で受けることができます。
切除手術の流れ
切除手術では、まず局所麻酔をした後、骨隆起の上の歯肉を切開して骨を露出させます。そして専用の器具を使い、盛り上がった骨を削ったり分割したりして取り除きます。最後に歯肉を縫合して完了です。
骨隆起の大きさにもよりますが、手術自体は30分から1時間程度で終わることがほとんどです。
手術後の注意点
外科手術後の経過と注意点について、事前に理解しておくと安心です。
手術中は局所麻酔が効いており、痛みを感じることはありませんが、術後麻酔が切れると痛みが出てきます。処方された痛み止めを服用し、対処しましょう。
術後、麻酔が完全に切れるまで食事は控えてください。
麻酔が切れた後も、手術した部位に刺激を与えないよう、硬いものや熱いもの、香辛料の強いものは避け、おかゆやスープ、ゼリーなど、柔らかく栄養のあるものを選びましょう。
個人差はありますが、術後数日間から1週間程度は腫れや痛みが続くことがあります。特に、手術当日から翌日にかけてがピークとなることが多いです。
手術後1〜2週間後に抜糸を行い、歯肉を縫合した糸を取り除きます。
ダウンタイムである1〜2週間程度は、激しい運動や飲酒、長時間の入浴は避け、安静に過ごすことが推奨されます。
対策:ナイトガード(マウスピース)で歯ぎしりを軽減
骨隆起の最大の原因である歯ぎしりや食いしばりの力。これらを軽減するため、ナイトガード(マウスピース)の装着が有効です。
睡眠中にナイトガードを装着することで、上下の歯が直接当たるのを防ぎ、歯や顎にかかる過剰な負担を和らげられます。
これにより、骨隆起の成長を抑制し、新たに隆起が発生するのを予防する効果が期待できます。
ナイトガードは歯科医院で作製でき、保険も適応されます。歯ぎしりを指摘されたことがある方や、朝起きた時に顎の疲れを感じる方は、一度歯科医師に相談してみることをおすすめします。
予防:生活習慣の見直し
骨隆起の予防や悪化を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことも必要です。具体的には以下の点に注意し、骨隆起を予防しましょう。
ストレスを溜めない
ストレスは食いしばりを引き起こし、間接的な骨隆起の原因になります。
趣味の時間を持つ、リラックスできる環境を整えるなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。
TCH(上下歯列接触癖)を治す
上下の歯を無意識に接触させてしまう癖を、TCH(上下歯列接触癖)と言います。
リラックスしている時は本来、上下の歯の間にわずかな隙間があります。いつの間にか上下の歯がくっついている癖があることに気づいたら、意識して歯を離すようにしましょう。
噛み合わせを整える(歯列矯正)
歯の噛み合わせが悪いと、特定の歯に負担が集中してしまい、骨隆起の原因になります。
定期的に歯科検診を受け、噛み合わせを適切に保ちましょう。また、噛み合わせや歯並びに問題がある場合は、歯列矯正を行って整えるのも効果的です。
食生活を改善する
硬いものを好んで食べる習慣がある方は、少し控えるようにしましょう。栄養バランスの整った健康的な食生活を意識することも大切です。
骨隆起に関するよくある質問
本章では、骨隆起についての具体的な疑問について、Q&A形式で回答します。
Q. 骨隆起は自然に小さくなったりなくなったりしますか?
A. いいえ。一度できてしまった骨隆起は、自然に小さくなったり消えてなくなったりすることは残念ながらありません。
骨隆起は、骨そのものが過剰に発育したものです。肌のターンオーバーのように新陳代謝で隆起がなくなったり、軟組織のように自然に吸収されたりすることはありません。
ただし、隆起の原因となっている歯ぎしりや食いしばりの力が弱まれば、成長のスピードを遅らせたり止めたりすることは期待できます。
骨隆起をこれ以上大きくさせないためにも、ナイトガードの使用や生活習慣の見直しなど、対策を行いましょう。
Q. 骨隆起の切除手術は痛いですか?
A. 手術は局所麻酔を効かせて行うため、手術中に痛みを感じることは基本的にありません。
麻酔が切れた後は、数日間痛みや腫れが出ることがありますが、ほとんどの場合、処方される痛み止めでコントロールできます。
Q. 骨隆起の切除手術にはどのくらい費用がかかりますか?
A. 保険適用で、骨隆起1つあたり5,000円~10,000円程度が目安です。
入れ歯が作れない、発音障害があるなど日常生活に支障をきたしている場合、骨隆起の切除手術は「病気の治療」とみなされ、健康保険が適用されます。
費用は切除する骨の大きさや数、場所によって異なりますが、3割負担の場合で、1箇所あたり5,000円~10,000円程度が一般的な目安となります。
加えて、初診料や再診料、レントゲン撮影費、薬代などがかかります。
Q. 骨隆起を自分で治す方法はありますか?
A. いいえ、骨隆起を自分で治す医学的な方法はありません。
骨隆起は硬い骨の塊ですので、マッサージで小さくしたり、何かを塗って溶かしたりすることは不可能です。
自分で無理に力を加えたり、強い刺激を与えたりするとむしろ、表面の薄い粘膜を傷つけ、痛みや炎症を引き起こす原因となりかねません。
自分でできるのは、骨隆起をこれ以上大きくさせないための「予防」のみです。
ナイトガードの使用やストレス管理、食生活の見直しなどに取り組み、顎への過剰な負担を減らすことを心がけましょう。
Q. 子供にも骨隆起はできますか?
A. 子供に骨隆起ができることは非常に稀です。
骨隆起は、長年の歯ぎしりや食いしばりといった、顎への持続的な負担が蓄積してできると考えられています。
そのため、骨の成長過程にある子供の顎に隆起が見られることはほとんどありません。
子供の口の中に硬いコブのようなものを見つけた場合、骨隆起ではなく、歯が生える過程での一時的な膨らみ(萌出性嚢胞など)や、他の病気の可能性が考えられます。
かかりつけの歯科医院や小児歯科で一度診てもらうことをおすすめします。
Q. 骨隆起とがん(悪性腫瘍)の見分け方を教えてください。
A. 表面の形状、硬さ、成長スピードなどが大きな違いだと言えますが、最終的には専門家に診断してもらうべきです。
あくまで一般的な目安としては、以下の違いが挙げられます。
| 項目 | 骨隆起 | がん(悪性腫瘍)などの疑い |
| 表面の形状 | 滑らかで、色は周囲と同じピンク色 | 表面がただれている、ザラザラしている、色がまだら |
| 形・境界 | 円形や楕円形で、境界がはっきりしている 境界は明瞭だが、肉眼で見るとボコボコしている | 形がいびつで、周囲との境界が不明瞭 |
| 硬さ | 全体的に骨のように硬い | 中心部は硬いが、周りにしこりがある |
| 成長スピード | 非常にゆっくり(数年単位) | 急に大きくなる(数週間~数ヶ月単位) |
| 痛み | 基本的にない(粘膜が傷ついた時を除く) | 強い痛みやしびれを伴うことがある |
これらの特徴はあくまで一例です。少しでも「いつもと違う」「何かおかしい」と感じたら、迷わず歯科や口腔外科を受診し、医師による正確な診断を受けてください。
歯肉がんの見分け方について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
まとめ:骨隆起で悩んだら、まずは信頼できる歯科医院へ相談を
骨隆起だけでなく、虫歯や歯周病などの口内トラブルは、自覚症状がないまま進行することが少なくありません。
定期的な歯科検診は病気の早期発見・早期治療につながり、お口全体の健康を守るためにとても大切です。
「骨隆起かもしれないけど、いきなり歯医者さんに行くのは少し勇気がいる…」
「治療が必要か、費用はどれくらいか、まずは話だけ聞いてみたい」
そんな方には、自宅からオンラインで気軽に歯科医師に相談できるサービス「mamoru」がおすすめです。
「mamoru」を使えば、
- このコブは本当に骨隆起?悪いものの可能性はない?
- もし切除するとしたら、費用はどれくらい?
- 私の場合は放置しても大丈夫そう?
といった具体的な悩みや不安を、歯科医師に直接相談することができます。
まずはオンラインで専門家の意見を聞き、今後の見通しや費用の不安を解消したうえで、納得して歯科医院選びに進む。そんなステップを踏んでみませんか。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。