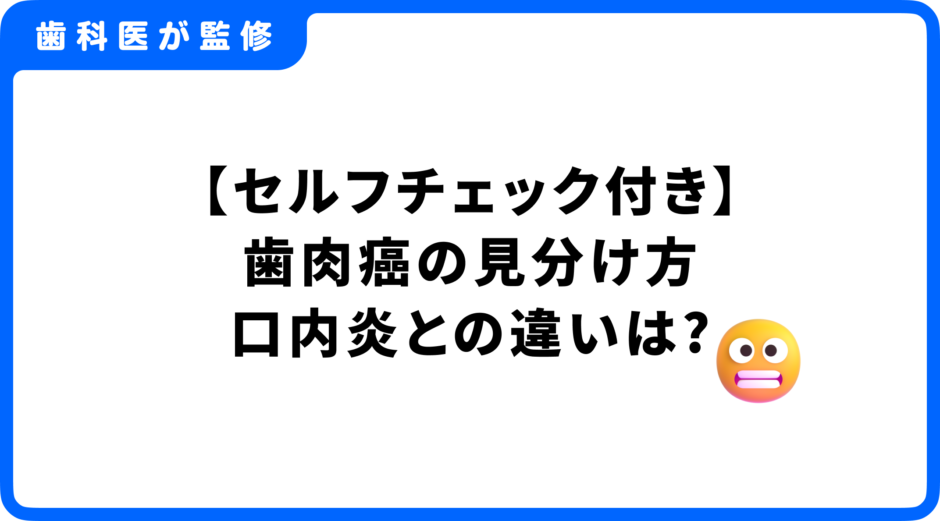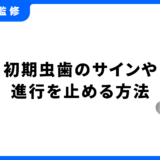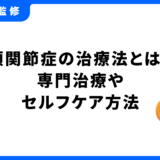「歯茎が腫れているけど、ただの歯周病?」
「長引く口内炎がなかなか治らない…もしかして癌?」
そんなお悩みを抱えていませんか?
歯肉癌(しにくがん)は口腔内にできる悪性腫瘍の一つです。初期には痛みがなく、口内炎や歯周病と見分けがつきにくいため、気づかないうちに癌が進行してしまう場合があります。
本記事では、歯肉癌などの口腔癌について、原因や症状、よくある質問など網羅的に解説します。
口腔癌の見分けに役立つセルフチェックもつけたので、癌かもしれないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
- 歯肉癌などの口腔癌の概要
- 歯肉癌のセルフチェック項目
- 口腔癌によくある症状
- 口腔癌のおもな原因
歯肉癌とは
歯肉癌(しにくがん)とは歯ぐきに発生する悪性腫瘍のことで、口腔癌の一種です。
歯肉癌の多くは「扁平上皮癌」と呼ばれるタイプで、粘膜上皮の細胞ががん化することで発生します。
初期には痛みがほとんどない場合が多く、口内炎や歯周病と似た症状を示すことが多いため、早い段階では見過ごされやすいのが特徴です。
たとえば、歯茎の腫れやしこり、出血、歯がグラグラする症状(歯の動揺)などは歯周病にも見られる症状ですが、2週間以上続く場合は歯肉癌の可能性が考えられます。
また、入れ歯(義歯)が合わなくなったり、違和感が強くなったりした場合も、歯肉癌が骨に広がり始めているケースがあります。
歯肉癌を早期発見できれば治療の選択肢は大きく広がるため、違和感を感じた時点で早めに歯科医院を受診してください。必要に応じて口腔外科やがん専門医療機関と連携し、精密検査を受けることが勧められます。
歯茎の異常に気づいたら、迷わず専門機関へ相談しましょう。
口腔癌の種類
口腔癌とは、舌や歯肉、口蓋(上あご)、口底(舌の下)など、口の中に発生するがんの総称です。
口腔癌の中でも最も多いのが「舌癌」で、次いで「歯肉癌」「口底癌」などが続きます。それぞれ発生部位によって症状や発見のタイミングは異なります。
| 癌の種類 | 特徴 |
| 舌癌 | 舌の側面にできやすく、しこりや痛みを伴うことが多い |
| 歯肉癌 | 歯周病や義歯の不調と間違われやすく、進行するまで気づかれにくい |
| 口底癌 | 舌の下の違和感や腫れとして現れ、嚥下障害や舌の動きにくさを伴うことがある |
そのほかにも、「頬粘膜癌」「硬口蓋癌(こうこうがいがん)」、「小帯部癌」など、口の中のどの部位にもがんは発生する可能性があります。局所的な症状に注意する必要があります。
がんの初期には痛みがないことも多いため、軽い異変でも早めに専門医に相談することが大切です。
歯肉癌などの口腔癌のセルフチェック
歯肉癌をはじめとする口腔癌は、早期の段階では自覚症状が少ないため、日頃からのセルフチェックが非常に重要です。
舌癌や歯肉癌の初期症状は口内炎や歯周病と見分けがつきにくく、「気のせいかな」と放置してしまうことで進行してしまうケースもあります。
口の中に気になる症状がある場合は、鏡を使って口の中をよく確認してみてください。癌の早期発見・早期治療につながるかもしれません。
以下に、歯肉癌やその他の口腔癌の兆候として注意すべきセルフチェック項目を11個紹介します。
【セルフチェック項目(11項目)】
- 2週間以上治らない口内炎や潰瘍がある
- 歯茎や頬の粘膜に硬いしこりや盛り上がりがある
- 歯のぐらつき(動揺)がある
- 入れ歯や詰め物が突然合わなくなった
- 舌の動きにくさ、片側だけのしびれや違和感がある
- 舌や歯茎、口腔内に白い膜(白板症)や赤い変色(紅板症)がある
- 出血しやすい部分があるが、はっきりした原因がわからない
- 話しづらさ、声の出しにくさ、ろれつが回らない感覚がある
- 食べ物や水を飲み込むときに引っかかる、むせる感じがある
- 強い口臭(腐敗臭)を感じる、または他人に指摘される
- 片側の顎や首周りに腫れやリンパのしこりがある
チェックリストのうち、1つでも当てはまる項目がある場合は、歯肉癌やその他の口腔疾患に関連する可能性があります。念のため早めに歯科医院や口腔外科に相談しましょう。
口腔癌によくある症状
口腔癌の初期症状はわかりにくいですが、進行するにつれて特有の症状が現れてきます。
多くの人が「口内炎だと思っていた」「歯周病だと思っていた」と軽く見てしまい、受診が遅れる傾向も。がんの早期発見が命を守る鍵となるため、口腔癌の初期症状を知っておくことはとても重要です。
本章では、口腔癌によくある症状について解説します。歯肉癌などの見分け方として、参考にしてください。
治らない口内炎や潰瘍
2週間以上治らない口内炎や潰瘍は、口腔癌の症状である可能性があります。
アフタ口内炎などの通常の口内炎なら、数日から1週間程度で自然治癒します。2週間以上長期化する潰瘍やただれには注意が必要です。
とくに、赤くただれた部分(紅板症)や白く膜が張ったような病変(白板症)は前癌病変として知られ、放置するとがん化するリスクが高まります。
また、潰瘍の縁が硬く触れる、出血しやすい場合なども要注意です。
歯茎の腫れや硬くなる感覚
歯茎が一部だけ腫れていたり、しこりのように硬く感じたりするのは、歯肉癌の初期症状かもしれません。炎症性の腫れとは異なり、弾力のない硬い腫れや盛り上がりが続く場合は注意が必要です。
歯ブラシなどの軽い刺激で出血しやすくなることも特徴で、歯周病との区別がつきにくい可能性があります。抗菌処置やクリーニングを行っても腫れが引かない場合は、がん性病変が疑われる状況です。
このような異常を感じた際は、口腔外科での精密検査(視診・触診・生検)を受けることが推奨されます。
歯茎の異常について詳しく知りたい人は以下の関連記事も参考にしてください。
▶関連記事:歯茎が白くぶよぶよするのはなぜ?考えられる原因と正しい対処法を解説
▶関連記事:歯茎に歯ブラシが当たると痛い!原因と今すぐできる対処法
原因がわからない歯のぐらつき
理由がないのに歯がグラグラする場合は、歯肉癌や顎骨への浸潤(がんの浸透)との関係が懸念されます。
通常、歯周病によって歯のぐらつき(動揺)が起こりますが、歯周ポケットが浅いのにぐらつきが大きい場合は要注意です。
がんが歯槽骨に浸潤すると、骨が破壊されて歯を支えられなくなります。さらに、痛みがないまま歯が自然脱落するケースも報告されています。
歯科医療者であってもがんと気づきにくいことがあるため、歯の動きに違和感を覚えたら、念のため画像検査やがん検査を受けることが大切です。
舌のしびれや違和感
口腔癌のサインとして、舌のしびれや、舌を動かしにくい感覚が現れることがあります。とくに舌癌や口底癌では、神経や筋肉への浸潤によって感覚異常や運動障害が起こることがあります。
症状として、以下のような違和感に注意してみてください。
少しの違和感は軽視されがちですが、がんによる神経圧迫や破壊の可能性も否定できません。明らかな痛みがなくても、片側だけの異常がある場合はがんが疑われます。
強い口臭(腐敗臭)
口の中から、通常の口臭とは異なる強烈な腐敗臭がする場合は、進行した口腔癌が原因である可能性があります。
強い口臭は、がん組織が壊死し、細菌とともに腐敗物質を発生させることにより起こります。
「どんなに歯磨きをしても口臭が取れない」「口の中からいつも変なにおいがする」という場合には、通常の虫歯や歯周病では説明できない症状が隠れているかも。
異常に強い口臭があるときには、歯科だけでなく耳鼻咽喉科や口腔外科での精査が必要です。
痛みのないしこり
しこり=痛いというイメージがあるかもしれませんが、口腔癌では「痛みのないしこり」が初期症状として現れることがあります。
とくに、舌・歯肉・頬粘膜などの粘膜下にできたしこりは、硬くて押しても痛くないのが特徴です。
がん性のしこりは周囲との境界が不明瞭で、粘膜との癒着や可動性の低下が見られ、動きにくいことがあります。これは腫瘍が周囲組織に浸潤している証拠であり、がんが進行している兆候です。
嚥下や発音の困難
口腔癌が進行すると、嚥下(飲み込み)や発音に障害が現れることがあります。これは、がんが舌や口底、咽頭周辺に広がり、筋肉や神経の動きを妨げるためです。
上記の症状は、がんによる構造的・機能的変化を反映している可能性があります。
これらは発見された時点である程度進行していることが多いため、すぐに病院を受診すべきです。
歯肉癌などの口腔癌のおもな原因
歯肉癌を含む口腔癌の原因は一つではなく、複数の要因が複雑に関係しています。がんのリスク要因を理解し、日常的に生活習慣の改善や定期検診の受診を心がけることが、口腔癌の予防につながります。
本章では、歯肉癌をはじめとする口腔癌の主な原因について解説します。
喫煙
喫煙は、口腔癌の最大の危険因子といわれています。
たばこの煙に含まれる数十種類もの発がん性物質が口の中の粘膜に直接接触することで、細胞の遺伝子異常を引き起こします。
歯肉や舌の粘膜は煙にさらされる時間が長いため、長年の喫煙は口腔癌の発症リスクを大幅に高めるとされています。また、喫煙者はがんだけでなく、歯周病や口臭、歯の着色などのリスクも同時に抱えている状態です。
加熱式たばこや電子たばこでも完全にリスクを排除することはできません。禁煙によって、口腔癌の発症リスクを下げることが明確に確認されているため、健康のためには早く禁煙することがとても重要です。
飲酒
過度の飲酒は口腔癌の発症リスクを高める要因のひとつです。
アルコール自体が発がん性を持つわけではありませんが、口腔粘膜を刺激してバリア機能を低下させ、発がん物質の浸透を促進するといわれています。
さらに、アルコールが体内で分解される際に生じる「アセトアルデヒド」は、明確な発がん物質に分類されています。
このアセトアルデヒドが口腔粘膜に長時間とどまると、細胞にダメージを与え、がん化を促進する可能性が高まるのです。
とくに、喫煙と飲酒の両方の習慣がある人は、相乗的にリスクが高くなります。
口腔癌を予防するには、生活習慣を見直し、健康的に過ごすことがとても大切です。
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染
HPV(ヒトパピローマウイルス)も、近年注目されている口腔癌のリスク因子です。なかでもHPV16型は、中咽頭癌や舌癌、口底癌などに関与していることが分かっています。
このウイルスは性行為や口腔接触によって感染し、粘膜に長期にわたって潜伏しながら細胞のがん化を促すと考えられています。
とくに若年層におけるHPV関連の口腔癌の発症率が上昇しており、社会的にも予防の意識が求められています。
HPVワクチンの接種が予防に有効であるとされ、口腔癌予防の一環として接種が促進されることが期待されています。
物理的刺激
合わない入れ歯や尖った歯による長期間の刺激も、歯肉癌などの口腔癌の引き金になることがあります。
入れ歯や尖った歯などによる口腔粘膜への物理的な刺激が繰り返されると、細胞の修復過程で異常が起き、前癌病変や癌へと進行するおそれがあるのです。
たとえば、慢性的に頬の内側を噛んでしまう癖や、虫歯を放置してできた鋭利な歯の角が当たる場合など、一見些細な刺激でもがんのリスクになります。
とくに高齢者には、義歯の不適合が原因で歯茎に炎症や潰瘍が生じ、症状が長引くことでがん化するケースが見られます。口腔内の装置や歯並びに異常がある場合は、歯科医院で早めに調整してもらいましょう。
口腔衛生不良
口の中が不潔な状態が続くことも、口腔癌のリスクを高める可能性があります。
歯垢や歯石の蓄積、虫歯や歯周病の放置により、慢性的な炎症が粘膜に与えるダメージが積み重なります。
炎症が続くと、粘膜の細胞が頻繁に修復を繰り返すことになり、その過程で細胞の異常分裂が起こりやすくなるため、がん化のリスクが上がるのです。
また、口腔カンジダなどの真菌感染も免疫力が低下した環境で発生しやすく、これが前癌病変の引き金となることもあります。
日々の歯磨きに加え、歯科でのクリーニングや専門的な口腔ケアを定期的に受けることが、がん予防につながるでしょう。
歯肉癌に関するよくある質問
本章では、歯肉癌や口腔癌に関するよくある質問に回答します。
口内炎と口腔がんの見分け方は?
口内炎と口腔がんは初期症状が似ていますが、治癒のスピードや見た目の違いで見分けられる場合があります。
通常の口内炎は、食事やストレスによる一過性の炎症で、1〜2週間程度で自然に治癒します。
一方、口腔がんは2週間以上経っても治らない潰瘍やただれ、色調の変化(白・赤)が持続し、しこりや盛り上がりを伴うことがあります。痛みがなくても進行していることがあるのが特徴です。
口内炎だと思っていても、症状が長引いたり、見た目に違和感があったりする場合は、口腔癌の可能性を疑いましょう。
歯肉癌の初期症状の見分け方は?
歯肉癌の初期症状は、痛みのない歯茎の異常として現れることが多いです。とくに多いのが、一部の歯茎が硬く盛り上がる、出血しやすい、歯がグラつくなどの症状です。
歯茎の炎症のように見えても、抗生物質やクリーニングで改善しない場合は要注意。歯肉の色調変化やしこりがあり、押しても痛みがない場合はがん性の病変の可能性もあります。
がんの兆候を見分けるには、継続して観察することと、専門医による診断が不可欠です。
自己判断せずに早めに歯科医院を受診してください。
歯肉癌の進行スピードはどれくらい?
歯肉癌の進行スピードには、免疫状態や生活習慣などの個人差がありますが、扁平上皮癌であることが多いため、比較的ゆっくりと進行する傾向にあります。
とはいえ、発見が遅れれば半年〜1年以内で顎の骨や周囲のリンパ節へ浸潤・転移するケースもあります。
歯肉癌の初期段階では見た目の変化や痛みが少なく、「気づいたときにはかなり進行していた」という例も珍しくありません。とくに、喫煙や飲酒の習慣がある人の癌は進行が早いと言われています。
癌の進行を止めるには、早期の発見と適切な治療が何より重要です。
口腔癌の前兆と言われている病気や症状は?
口腔癌の前兆となる「前癌病変」が存在し、それががんへと進行することがあります。
とくに注意すべきなのは以下のような病変です。
白い膜状の病変。がん化率は5〜10%。
赤くただれた病変。がん化率は白板症より高い。
慢性的な炎症性疾患で、稀にがん化する。
合わない入れ歯・歯の尖りなどによる持続的な刺激ががんの引き金になる可能性がある。
これらの病変には痛みがない場合も多いため、歯科医院での定期検診が早期発見の手がかりになります。見た目に異常がなくても、慢性的な違和感があれば専門医に相談しましょう。
歯肉癌などの口腔癌が疑われたら病院では何をする?
歯肉癌などの口腔癌が疑われる場合、病院では段階的な精密検査が行われます。まずは視診と触診で粘膜の状態やしこりの有無を確認し、必要に応じて以下の検査を実施します。
- 口腔内写真の記録
- X線・CT・MRIなどの画像検査(骨や深部の浸潤を確認)
- 細胞診・組織生検(病変部の一部を採取し、がん細胞の有無を確認)
- 血液検査やリンパ節の触診
がんと確定された場合は、病期(ステージ)分類をもとに治療計画が立案されます。外科的切除や放射線治療、抗がん剤治療などを組み合わせた治療が始まるでしょう。
がんでも早期に見つかれば、予後も比較的良好です。不安があれば早めに病院を受診してください。
まとめ
歯肉癌は、歯周病や口内炎と見分けがつきにくい初期症状を持つため、見逃されやすいがんの一つです。
しかし、2週間以上治らない潰瘍やしこり、原因不明の歯のぐらつきなど、特徴的なサインを知っておけば、早めにがんに気づけるかもしれません。
特に、喫煙や飲酒の習慣、慢性的な刺激、口の中の不衛生などのリスク要因に心当たりがある方は、日頃から意識的にがんに備える必要があります。
口腔癌は早期発見・早期治療が重要です。「口の中の違和感がなんとなく気になる」「これは普通じゃないかも」と思ったときこそ、歯科医院や口腔外科の専門医に早めに相談してください。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。