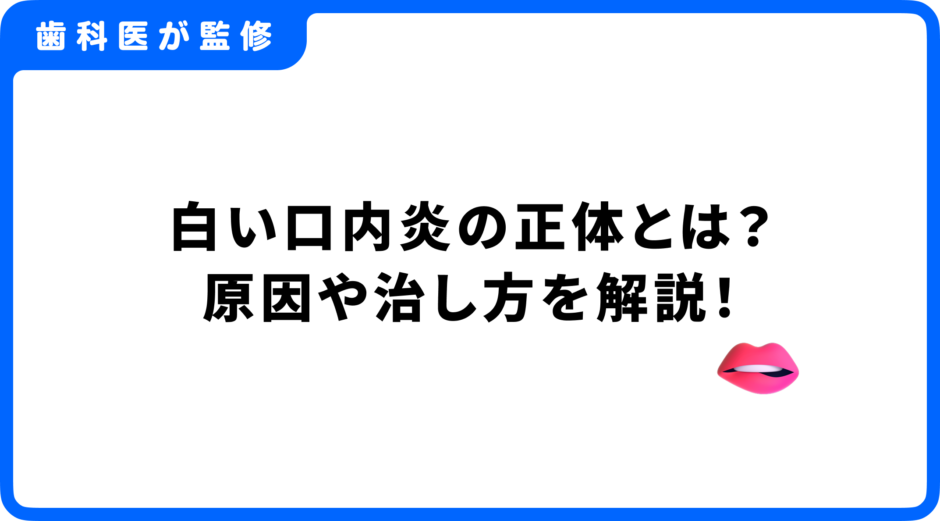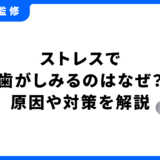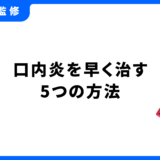口の中にできた、白い口内炎。
気になってつい触ってしまったり、食事のたびにしみたりと、できれば早く治したいものですよね。
この記事では、白い口内炎の種類や原因をはじめ、早く治すための対処法や市販薬の選び方を、歯科の専門知識をもとにやさしく解説します。
再発を防ぐためのポイントや、病院を受診すべきタイミングについてもあわせてご紹介します。
▶関連記事:唇にできものができて痛い!痛みの原因と対処法、予防策まで解説
白い口内炎の種類と特徴
白い口内炎は、口腔内の粘膜に白っぽい潰瘍やできものができている状態を指します。
とくに歯ぐきや頬の内側、舌の側面などに発生しやすく、多くの場合痛みます。
一見して、よくある口内炎に似た症状でも、感染・アレルギー・がんなど多様な疾患の可能性もあるため、注意が必要です。病院の受診や特別な治療が必要なケースもあります。
ここでは、白い口内炎の症状が見られる4種類の疾患をわかりやすく解説します。
アフタ性口内炎
アフタ性口内炎は、日本人に最も多く見られる白い口内炎です。直径2〜10mmほどの白〜灰白色の潰瘍(かいよう)が、頬や舌、歯ぐきなどの粘膜に現れます。
食事中や会話中に痛みを感じることが多く厄介ですが、1〜2週間で自然治癒します。
アフタ性口内炎の主な原因は、免疫力の低下や、歯並びや清掃不良による口腔内の刺激です。
再発を繰り返す場合は、生活習慣や食生活の見直し、矯正治療の検討が必要と言えるでしょう。
痛みが強く改善が見られなければ、歯科や医療機関の受診をおすすめします。
ウイルス性口内炎(ヘルペスなど)との違い
ウイルス性口内炎は、単純ヘルペスウイルスやコクサッキーウイルスなどの感染が原因で発症します。アフタ性口内炎とは全く異なるもので、水疱(水ぶくれ)や高熱を伴うことがあります。
とくにヘルペス性口内炎は乳幼児に多く見られる口内炎です。ただし、ストレスや体調不良によって大人でも発症するケースがあります。
・歯茎/のど/舌など口内の広範囲にわたるびらん(表皮の欠損)や潰瘍
・全身症状(高熱・だるさ)を伴いやすい
・他者へうつる可能性がある
ウイルス性口内炎の場合、自然治癒や市販薬での対応は難しいため、医療機関の早期な受診をおすすめします。
誤った治療により悪化・再発を招くこともあるため、自己判断は避けましょう。
カンジダ性口内炎
カンジダという真菌(カビ)が原因で起こる感染症で、口内炎を引き起こします。
口の中の粘膜表面に白い苔状の膜が広がり、こすると出血したり、白い膜状のものがとれたりする場合があります。
免疫力の低下や、抗生物質の長期使用、入れ歯や義歯の不衛生管理などが発症の要因です。
慢性化や悪化の可能性があるため、カンジダ性口内炎と思われる症状が現れた場合は早めに病院を受診しましょう。
白板症(はくばんしょう)
白板症は、舌や歯肉、頬の裏の粘膜などに、擦っても取れない白い斑点ができる病変です。
白い斑点が発生する原因は不明とされています。
喫煙やアルコールの影響や、慢性的な口内刺激が関連していることが多いと言われます。
進行すれば、口腔がんなどがん化するリスクも。白板症の症状が見られる場合、必ず病院を受診してください。
ニコチン性口内炎
ニコチン性口内炎は、長年の喫煙によって口蓋(上あご)に白いできものができます。
一般的に痛みはありませんが、しみたり、ざらつきを感じたりする場合があります。
禁煙すれば数週間で治る場合がほとんどですが、長期的には口腔がんなどの悪性腫瘍に変わるリスクがあるため注意が必要です。
ニコチン性口内炎は自覚症状が出にくいうえ、見た目での判断が難しいため、歯科医院や病院での検査・診断を受けると安心でしょう。
白い口内炎の主な原因とは?
白い口内炎は一般的に、複数の要因が重なって発生します。
とくにアフタ性口内炎は、免疫力や栄養状態、外部刺激など、さまざまな角度から原因を考察する必要があります。
ここでは、口内炎を発症させる主な原因を3つ解説します。
免疫力の低下と栄養不足(ビタミンB群の不足など)
免疫機能の低下は、白い口内炎を引き起こす代表的な内部要因のひとつです。
身体が弱っているときは、口腔内の粘膜もダメージを受けやすくなります。
免疫力が低下していると、口の中に小さい刺激があっただけで炎症や潰瘍が発生し、口内炎になってしまうのです。
とくに次のような状況では、口内炎が発生しやすくなります。
- 感染症罹患後の病み上がり
- 睡眠不足や精神的ストレスが蓄積しているとき
- 激しい運動や過労により体力が消耗しているとき
- 慢性的な病気の治療中
さらに、粘膜の健康を保つうえで欠かせないビタミン群や鉄分などの栄養不足も一因です。
ビタミンB2、B6、B12、C、葉酸、鉄、亜鉛などの栄養素が欠乏すると、白い口内炎が繰り返し現れやすい傾向にあります。
口腔内への刺激(入れ歯・歯磨き・金属アレルギーなど)
日常的に起こる物理的刺激も、白い口内炎を引き起こす原因です。
わずかな摩擦や圧迫により粘膜が傷つくと、炎症や潰瘍になる場合があります。
代表的な外的刺激には、以下のようなものがあります。
- 入れ歯・義歯が粘膜に擦れる
- 詰め物や被せ物の金属が接触し続ける
- 歯ブラシの毛先が硬すぎる/力を入れすぎる
- 食事中に頬や舌を誤って噛む
- 香辛料やアルコールなど刺激の強い飲食物による化学的刺激
口内炎が同じ場所に繰り返しできる場合、慢性的な接触刺激が背景にある可能性が高いです。
また、金属によるアレルギー反応により、アレルギー性の口内炎や扁平苔癬(へんぺいたいせん:かゆみを伴う発疹)など、がんに繋がる病変が起こるケースもあります。
ストレス・睡眠不足・喫煙など生活習慣の影響
白い口内炎の発生には、毎日の生活習慣も密接に関わっています。
とくに、ストレスや睡眠不足、喫煙などは、免疫力や粘膜の防御機能を低下させることがわかっています。
・長期間続く精神的・肉体的ストレス
・睡眠時間の不足や質の低い睡眠
・喫煙
・飲酒やカフェイン摂取
・食生活の乱れや食事時間の不規則化
とくにストレスと喫煙は、唾液分泌の減少や粘膜の乾燥を引き起こし、細菌の増殖や口腔環境の悪化につながります。
喫煙は、血流を悪化させて粘膜の修復力を低下させる悪影響も。
アルコールやカフェインの摂取は、脱水や口内の乾燥を引き起こし、口内炎の原因となる場合があります。
白い口内炎の治し方|早く治すには
白い口内炎は、時間が経てば自然に治る場合もありますが、食事や会話の時に痛むので、早く治したいですよね。
口内炎を放置していると、治りかけても再発を繰り返したり、他の病気を見落としたりするリスクもあります。
症状に応じてケアし、口内炎の正しい治し方を知っておきましょう。
▶関連記事:口内炎を早く治す5つの方法|原因から市販薬の活用方法、予防法まで徹底解説
▶関連記事:口内炎の治し方・裏ワザを徹底解説!|治りを早めるセルフケアと歯科での治療法
正しく応急処置をする
白い口内炎ができた直後は、以下のポイントを押さえて応急処置をしましょう。
初期段階での正しいケアが、症状の悪化や再発の予防にもつながります。
・できもの(潰瘍)には触れない、こすらない
・清潔なうがいをこまめに行い、細菌の増殖を防ぐ
中でも、患部に余計な刺激を与えないよう注意することを最優先にします。
口の中は常に、食べ物による刺激や唾液、細菌にさらされている状態です。
少しの刺激でも痛みが増し、治癒が遅れてしまいます。
とくにアフタ性口内炎などは、口内炎の表面が敏感になっているため、食事や会話、歯磨きなど日常的な動作でも症状が悪化することがあります。
できる範囲内で、患部の刺激を遠ざけましょう。
症状別に正しく市販薬を活用する
市販薬は、症状が軽い段階やすぐに医療機関に行けない場合のセルフケアとして有効です。
ただし、市販薬が全ての口内炎に効くわけではありません。症状や進行具合によって適した薬を選ぶ必要があります。
市販薬には、スプレーやジェル、内服薬などのタイプがあります。
使いやすさや患部への届きやすさを考慮して選びましょう。
痛みが強い:口腔用の軟膏(ケナログ、アフタゾロンなど)
炎症を抑えたい:うがい薬(アズレン・グリチルリチン酸など)
口内の細菌対策:殺菌成分配合のスプレーやジェル
ビタミン補給:ビタミンB群・Cを含むサプリメントやドリンク剤
市販薬の使用に不安がある場合は、薬剤師や医師に相談するのが望ましいでしょう。
ビタミン不足を解消する|ビタミン群・鉄分の役割
口内炎の改善に栄養は欠かせません。中でもビタミン群(ビタミンB群・ビタミンA・ビタミンD・ビタミンCなど)や、鉄分、亜鉛といった栄養素は、粘膜の修復や免疫機能維持のため、とても重要です。
これらの栄養素が不足すると、口の中の粘膜が弱くなり、炎症に対する抵抗力が低下します。
また、口内炎の治りが遅くなり、再発の頻度が高くなる傾向があります。
・粘膜のただれや口内炎の治癒遅延
・口内炎の再発
・倦怠感/口角炎/舌のひび割れなどの併発症状
ビタミンB2/B6/B12:粘膜細胞の生成と修復を助ける
ビタミンC:炎症の抑制とコラーゲン生成に関与
鉄分・葉酸:血流と組織再生に必要
食事だけでは十分な栄養を摂取しきれない場合、サプリメントで栄養を補ってもよいでしょう。
生活習慣を見直して自然治癒力を高める
体が本来持っている「治す力」を最大限に引き出すには、生活習慣の見直しが不可欠です。
とくに、免疫力や粘膜の修復に関わる悪習慣があると、口内炎の治りが遅れ、慢性化しやすくなります。
睡眠やストレスの管理はもちろん、日常的な口の中のケアや乾燥予防も必要です。
・十分な睡眠時間(目安:6〜8時間)を確保する
・ストレスを軽減する時間や方法を取り入れる
・喫煙や過度の飲酒を控える
・こまめに水を飲み、口腔の乾燥を防ぐ
毎日の小さな意識の積み重ねが、口内炎の予防・治療につながります。
痛みを抑えるための食事・口腔ケアを行う
白い口内炎のつらさは、なんといっても「食べると痛い」こと。
炎症部分が食べ物に触れると強い刺激を受け、痛みが悪化したり、食事が億劫になって栄養不足になったり、悪循環に陥る場合もあります。
口内炎の悪化を避けるためには、刺激の少ない食事を選ぶと望ましいです。
また、口の中を優しくケアする意識を持つことが重要です。
・おかゆ、スープ、ヨーグルト、豆腐などの柔らかい食べ物を中心に
・熱すぎず冷たすぎない温度
・ビタミン・たんぱく質を含む食品をバランスよく摂取
・辛いもの、酸っぱいもの、揚げ物、アルコール類の摂取
・硬いせんべい、スナックなど粘膜を刺激する食品の摂取
・強い歯磨きやうがい薬の使用
口内炎で食べにくい時期でも、必要な栄養素を摂る工夫をして、なるべく早く治しましょう。
再発・悪化を防ぐ、口内炎の予防法
白い口内炎は一度治っても、体調や生活環境の変化によって再発することも多いです。
とくにアフタ性口内炎やヘルペス性口内炎、カンジダ性口内炎などは、ストレス・免疫力の低下・栄養不足など、複数の要因が絡む再発性疾患として知られています。
ここでは、口内炎を「繰り返さない」「悪化させない」ために、日常生活の中で実践できる3つの予防法を紹介します。
正しいケアで口の中を清潔に保つ
口の中を常に清潔に保つことで、細菌やウイルスの増殖を防ぎ、炎症を予防します。
逆に言えば、小さな刺激や不衛生な状態が原因で、口内炎が発生しやすくなる環境に変わってしまいます。口の中はとてもデリケートなのです。
歯磨きやうがいなどの基本的なケアをきちんと行いましょう。
・1日2〜3回の歯磨き(朝・就寝前+食後)
・やわらかめの歯ブラシで、歯ぐきや粘膜を傷つけないように優しく磨く
・フロスや歯間ブラシで歯の間の汚れも除去
・うがい薬を併用して細菌やウイルスを除去
・入れ歯・マウスピースなどは毎日洗浄する
また、唾液の分泌を促すことも意外に重要です。
唾液は「天然の口腔洗浄液」と言われ、細菌の増殖を抑える抗菌作用を持ちます。
食事はよく噛んで食べ、できるだけリラックスして過ごしましょう。
口の周りの体操やマッサージも効果的です。
バランスの良い食事と十分な水分補給
栄養と水分補給は、口の中の健康を保つためにとても重要です。
ビタミンやミネラルの不足は、粘膜の再生能力を低下させ、口内炎の発生・再発リスクを高める要因になります。
とくに注意したいのが、ビタミンB群の不足や鉄分・亜鉛などのミネラルの欠乏。
これらは、細胞の代謝や免疫力の維持に必要不可欠な栄養素です。
ビタミンB2/B6:レバー、卵、納豆、乳製品、魚介類
ビタミンC:ブロッコリー、いちご、柑橘類、ピーマン
鉄分:赤身肉、あさり、ひじき、大豆製品
亜鉛:牡蠣、かぼちゃの種、牛肉、ナッツ類
加えて、水分不足による口の中の乾燥も細菌の増殖を助長する要因です。
とくに高齢者や喫煙者は、口の中が乾きやすくなるため注意が必要です。
・こまめな水分摂取(1日1.5~2Lを目安に)
・喉が渇く前に飲む習慣をつける
・カフェイン飲料やアルコールの摂りすぎは控える
健康な食生活と水分管理は、口内炎を予防する体質を作ります。
歯科医院での定期検診を受ける|「mamoru」が通院をサポート
定期的な歯科受診は、口内炎の予防だけでなく、口腔がんや白板症といった重大な疾患の早期発見にもつながります。
口内炎が頻繁にできる方は、一度きちんと検査を受けて、根本的な原因や予防策を知ることも大切です。
しかし、「忙しくて受診のタイミングを逃してしまう」「どこの医院に行けばいいかわからない」という人もいるでしょう。
そんなときは、歯科通院をサポートするサービスを活用してみてください。
たとえば、「mamoru」では以下のようなサポートが受けられます。
・近くの歯科医院をスムーズに検索・予約できる
・症状に合った専門医を見つけやすい
・通院履歴の一元管理やリマインド通知で受診忘れを防止
このようなツールを活用すれば、「我慢せずに相談する」習慣ができ、口内炎や病気を早期に治療できます。
不安なときこそ、専門家の診断が不可欠です。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。
白い口内炎に似た病気に要注意
口内炎だと思っていたら、実は別の病気だったというケースも珍しくありません。
とくに白板症や口腔がんなどの疾患は、初期には自覚症状が少なく、アフタ性口内炎と区別がつきにくいことがあります。
繰り返す口内炎や治りにくいできものは、軽視せず、慎重に観察する姿勢が重要です。
口腔がん・舌がんなどの重篤な疾患
白い粘膜異常が見られる病気の中には、口腔がんやその前段階とされる白板症(はくばんしょう)など、進行すると命に関わる疾患が含まれます。
いずれも早期発見が何より重要ですが、初期は痛みがないことも多く、気づかず放置してしまうケースも少なくありません。
白板症:擦っても取れない白い斑点や膜が粘膜に生じる
口腔がん(舌がん・歯ぐきがんなど):硬く盛り上がった潰瘍や不規則な白斑
ニコチン性口内炎:喫煙者に多く、口に白くざらついた変化が現れる
・2週間以上治らない白斑や潰瘍がある
・出血しやすい・硬く盛り上がっている
・舌/歯ぐき/頬の内側などに異常がある
・痛みがなくても色や形が明らかにおかしい
これらの病気と思われる症状に気づいたら、なるべく早めに専門の医療機関で検査を受けましょう。
早期であれば比較的高い確率で治療が可能ですが、進行すると外科手術や放射線治療が必要になることもあります。
自己判断せず歯科・医療機関の受診を
口内炎は珍しくないため、自己判断で放置してしまいがちです。
しかし、実際には歯科や医療機関での診察が必要な場合もあります。
・白いできものが2週間以上治らない
・同じ場所に繰り返し口内炎ができる
・痛みがどんどん強くなっている
・患部が硬くなっている、またはしこりのように触れる
・唇/歯ぐき/舌などに異常な出血・腫れがある
カンジダ性口内炎や白板症などの疾患は、自分で見ただけでは判別が難しいうえ、放置することで悪化するおそれもあります。
とくに高齢者や喫煙者、口の中に義歯や金属がある方、栄養不足の方などは、より注意深く経過を観察すべきでしょう。
病院に行こうか迷ったら行くことを推奨します。「mamoru」などの通院支援サービスを活用すれば、地域の歯科医院をスムーズに検索・予約できます。
「おかしいな」と感じたら、早めに医師の診察を受けることが、健康を守る第一歩です。
まとめ|白い口内炎には早めの対処を
白い口内炎には、アフタ性口内炎をはじめ、カンジダ性・ウイルス性・白板症など、多様な種類があります。
原因も、栄養不足、生活習慣の乱れ、ウイルスや細菌の感染などさまざまです。
一見すると軽いできものに見えても、がんなどの重篤な疾患の予兆である場合があるため、注意が必要です。
とくに2週間以上治らない白斑や潰瘍は、口腔がんなどの可能性もあるため、放置せずに専門家の診察を受けましょう。
日々の生活習慣の積み重ねが、口内炎の予防に繋がります。
口内炎ができてしまったら、 体からのサインとして受け止め、早めに治せるように生活習慣の改善を心がけましょう。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。