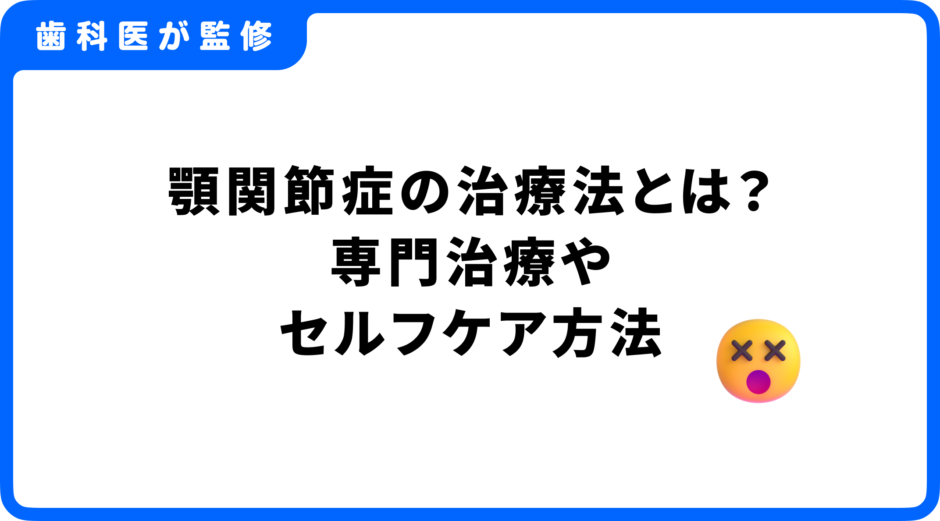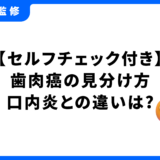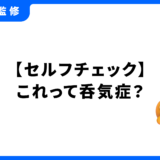「口を開けるとカクッと音がする」
「アゴが痛くて食事がしづらい」
「口が大きく開かない」
こんな症状に心当たりはありませんか?
それは、顎関節症(がくかんせつしょう)のサインかもしれません。
顎関節症は、虫歯・歯周病と並ぶ疾患の一つで、現代人に増えている身近なトラブルです。
顎関節症を放っておくと慢性化し、一部の研究では、違和感や生活の質の低下と関連すると示唆されています。ただし、直接的因果関係は明確ではありません。
本記事では、
- 顎関節症の原因や症状
- 歯科で受けられる治療法やマウスピース療法
- 日常生活でできるセルフケア
まで、歯科医療の視点からわかりやすく解説します。
顎関節症と思われる症状に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
顎関節症とはどんな病気?
顎関節症(がくかんせつしょう)とは、アゴの関節や筋肉に異常が起こることで、口の開閉や噛み合わせに問題が生じる疾患です。特に20〜40代の女性に多いと報告されています。
顎関節症が発症する背景には、生活習慣やストレスなど複数の因子が関与しており、放置すると慢性痛や咬合異常などの深刻な問題に発展するリスクがあります。
本章ではまず、症状や原因など、顎関節症の概要を押さえましょう。
顎関節症は身近な疾患
顎関節症は、虫歯・歯周病に次いで頻度の高い疾患です。実際、日本顎関節学会の報告によれば、10人に1人が何らかの顎関節症状を経験しているとされています(参照)。
顎関節症は、「関節の異常」「筋肉の緊張」「噛み合わせの不調」など、複数の要因が組み合わさって発症するため、単一の治療では改善が難しいこともあるのが特徴です。
食事や会話、睡眠などにも支障をきたす場合があり、日常生活への影響も小さくありません。そのため、アゴの違和感を軽視せず、歯科医師へ相談することが推奨されます。
顎関節症のおもな症状
顎関節症の症状は多様ですが、代表的な症状は以下のとおりです。
顎関節症では、複数の症状が同時に現れることも多いと言えます。
例えば、「朝起きるとアゴがだるい」「口を大きく開けると音がする」といった軽度の異変も、顎関節症の初期症状である可能性があります。
また、頭痛や肩こり、耳鳴りなどの全身症状と関係するケースもあるため、単なる「アゴの病気」と断定するのは禁物です。
顎関節症の原因
顎関節症は1つの明確な原因によって発症する病気ではありません。複数の因子(リスクファクター)が重なって生じる「多因子性疾患」です。
顎関節症のおもな原因として、以下が挙げられます。
特に、無意識の習慣や生活の乱れが関節や筋肉に長期的な負担をかけることが多いとされます。
また、成長期における歯列や下顎の発達異常、ホルモンバランスも、顎関節症の発症に影響していると考えられています。
こうしたリスク因子を知っておき、治療方法の検討に役立てましょう。
顎関節症の分類
顎関節症は、その症状や発症メカニズムによって5つの型(Ⅰ〜Ⅴ型)に分類されます。これらの分類は、日本顎関節学会の診断基準(参考)に基づいており、治療法を検討する上で重要な指標となります。
Ⅰ型(咀嚼筋障害型)
咀嚼に関わる筋肉に異常があるタイプで、アゴを動かすと筋肉が痛み、押すと鈍痛があるのが特徴です。
長時間の会話や食事後に痛みが出る場合が多く、マッサージや運動療法、ストレッチが有効とされます。
Ⅱ型(関節包・靱帯障害型)
顎関節を包む関節包や靱帯に炎症が起きた状態です。口を開けた時に鋭い痛みが出ることがあり、外傷や過度な開口動作が原因となることがあります。
痛みを軽減するために、咀嚼の負担を減らすセルフケアが推奨されます。
Ⅲ型(関節円板障害型)
関節のクッションとなる関節円板(かんせつえんばん)がズレたり、変形したりするタイプの顎関節症です。
「カクッ」という関節音が特徴で、円板が元の位置に戻るタイプ(復位性)と戻らないタイプ(非復位性)に分かれます。スプリント療法や矯正治療が選択される場合があります。
Ⅳ型(変形性関節症型)
関節軟骨の摩耗や骨の変形が進行した状態です。中高年に多く、関節の雑音(ゴリゴリ音)や慢性的な開口障害がみられます。
この型の顎関節症は構造的な変化を伴うため、治療期間が長くなる場合があります。
Ⅴ型(その他)
Ⅰ〜Ⅳ型のいずれにも該当しない、神経性や心因性要因、全身疾患と関連するケースが該当します。たとえば、線維筋痛症や顎関節以外の病気が関与している場合です。
歯科単独では判断が難しく、医科との連携も視野に入れた診療が必要となります。
顎関節症の治療法
顎関節症の治療は、症状の程度や原因に応じて段階的に進めるのが一般的です。始めは保存的療法(マウスピース・運動療法・理学療法)を中心に行い、改善が見られない場合に外科的治療を検討します。
患者ごとに原因や症状の型が異なるため、歯科医院での的確な診断が重要なのです。
本章では、歯科医院で受けられる代表的な治療法をご紹介します。
歯科医院で受けられる治療法一覧
歯科医院では、顎関節症の診断後に次のような保存的療法を中心とした治療法が選択されます。
| 治療法 | 内容 | 適応 |
| スプリント療法 | マウスピース型装置を装着し、関節や筋肉の負担を軽減する | 歯ぎしり・噛み合わせに異常がある患者の症状を改善 |
| 運動療法 | 関節や筋肉を正しく動かす訓練により、開口障害を改善する | 開口制限・関節可動域の減少 |
| 理学療法 | 温熱・超音波・低周波などによるリハビリ | 筋肉の緊張や炎症の軽減 |
| 咬合調整 | 噛み合わせの高さや位置を微調整する | 噛み合わせの不調和による症状 |
上記の治療法は、痛みを根本から改善するのではなく、再発を防ぐための管理目的に行うものです。
進行度が高い場合や、保存療法で改善しない場合は、さらに外科的治療が検討されます。
運動療法
運動療法は、顎関節や周囲の筋肉をスムーズに動かす力を取り戻すためのリハビリです。
特に、「口を開けづらい」「アゴがまっすぐ動かない」という症状の見られる「開口障害」に対して効果的です。患者自身が自宅で継続的に行えるセルフケアとしても推奨されています。
たとえば、
- 指を使ってゆっくり口を開く「開口訓練」
- アゴをまっすぐに動かす「前後左右の動きの訓練」
などがあり、関節や筋肉へ過剰な負荷をかけないようにしながら可動域を改善します。
ただし、正しい運動方法について、歯科医師や専門スタッフから指導を受けることが前提です。誤った運動を行うと逆に関節を痛めるリスクがあるため、専門医による治療の一環として行いましょう。
理学療法
理学療法は、物理的な刺激を加えることで筋肉や関節の状態を整える治療法です。歯科領域では、炎症を抑えたり、筋肉の緊張を和らげたりする目的で行われます。
理学療法の主な手法として、以下が挙げられます。
- 温熱療法(ホットパック):
血流を促進して痛みを緩和する - 超音波療法:
深部の組織まで振動で刺激し、治癒を促す - 低周波療法(電気刺激):
筋肉の緊張緩和やリラクゼーション効果
理学療法は一部の研究で有効性が示されており、補助的に用いられるものです。特に咀嚼筋や側頭筋の緊張が強いⅠ型の顎関節症において効果が高いと言われています。
歯科医院によっては、理学療法士と連携し、歯科とリハビリが融合したアプローチを行います。
外科的療法
保存療法で改善が見られない重度の顎関節症や、関節円板の高度な変形・逸脱がある場合には、外科的治療(手術)が検討されます。
外科的治療の手段として、代表的なものは以下の通りです。
- 関節洗浄療法(関節腔洗浄):
関節内に生理食塩水を注入して炎症物質を洗い流す方法 - 関節鏡視下手術:
小さなカメラと器具を用いて関節内の病変に処置する手術 - 開放手術:
顎関節そのものに直接アプローチする大規模な手術
手術が必要になるのはごく一部のケースであり、多くは保存療法で改善が期待できます。
外科的治療にはリスクやダウンタイムが伴うため、医師による慎重な検査と判断が不可欠です。
外科手術を受ける際は、日本顎関節学会認定の専門医が在籍するクリニックや大学病院の口腔外科を選ぶと安心です。
スプリント療法とは?
マウスピースやスプリント療法は、顎関節症の治療において最も広く行われている保存的療法のひとつです。
本章では、スプリント療法の基本と装着時の注意点、歯列矯正との併用について紹介します。
スプリント療法の仕組みと目的
スプリント療法とは、アゴの関節や筋肉への負荷を軽減するために「スプリント」と呼ばれる透明な装置(マウスピース)を装着する治療法です。
一部の研究で、痛みや開口障害の軽減に効果があると報告されています。
基本的には夜間就寝時に使用することが多く、無意識の歯ぎしり・食いしばりを抑える目的があります。
患者ごとに異なる症状・噛み合わせに適合するように型取りを行い、作製・調整されるため、既製品ではなく歯科医院でのオーダーメイドが基本です。
スプリント療法では、定期的に装置の調整(リライニング)や診察が必要です。長期的な使用により、かえって咬合異常(噛み合わせの異常)を起こすリスクもあるため、歯科医師の治療方針にしたがうのが前提です。
マウスピース装着の効果と注意点
マウスピースの装着は、顎関節症の痛みや開口障害の緩和に高い効果が期待できると言われています。
特に、夜間の無意識の歯ぎしりや咬筋(頬の筋肉)の過活動によって、顎関節症の症状が悪化しているケースでは有効です。
ただし、使用方法を誤ると逆に悪化を招く可能性もあります。
装着期間は症状によって異なり、1カ月〜半年以上の継続使用が必要な場合もあります。
定期的に調整を受けることで、スプリント療法の効果が最大限に発揮されるのです。
スプリント療法と矯正治療の併用について
スプリント療法と矯正治療は、併用が可能なケースと注意が必要なケースがあります。
顎関節症の背景に「噛み合わせ(咬合)のズレ」がある場合、スプリントだけでは根本的な改善が難しいことがあります。
その場合、矯正治療を併用することで、噛み合わせと関節の長期的な安定性が得られた例も報告されています。
ただし、矯正治療中は歯が動くため、スプリントの効果は発揮されにくくなることがあります。そのため、治療の進行状況に応じてマウスピースを変更したり、治療の順序を柔軟に調整したりすることが大切です。
スプリントは一時的な症状緩和装置、矯正治療は構造的な原因へのアプローチと位置づけられます。それぞれの目的を明確にしながら併用するのが理想です。
スプリント療法と矯正治療を併用するケースでは、顎関節症の診療経験が豊富な歯科医師や咬合専門医・矯正専門医との連携が推奨されます。
日常生活でできる顎関節症の予防・改善方法
顎関節症は生活習慣との関係が深いため、毎日の行動を見直すことで症状の予防や軽減が期待できます。顎関節症の症状を軽減するには、歯科での治療に加え、自宅でできるケアや意識づけが重要です。
ここでは、姿勢や習慣の改善、ストレスコントロールなど、日常生活でできるセルフケアのポイントを紹介します。
姿勢や食習慣・運動習慣を見直す
姿勢や噛みグセは、アゴの位置や関節への負担に直接影響を与えます。長時間のデスクワークやスマホ操作により、無意識のうちに前傾姿勢やアゴの偏りが習慣化することがあります。
下顎(かがく)の位置や動きに特に影響するのは頭部のバランスです。正しい姿勢を保つことで関節と筋肉への負担を軽減し、自然に改善を期待できます。
アゴに違和感があるときは、食事内容も一時的に「柔らかめ」に変更すると良いかもしれません。炎症や痛みが落ち着く可能性があります。
歯ぎしり・食いしばり対策のためにマッサージを行う
歯ぎしりや食いしばりは、顎関節症の主要な原因のひとつです。特に、夜間の無意識なブラキシズム(口の動きのクセ)により、筋肉や関節に持続的な負担がかかってしまうことがあります。
ブラキシズム対策として、筋肉の緊張を和らげるマッサージや温熱ケアが有効です。
これらのマッサージを1回5〜10分程度毎日継続することで、筋緊張が軽減され、開口障害や痛みの改善を期待できます。
ただし、顎の痛みが強いときは無理に触らず、まずは歯科での診察を受けるようにしてください。マッサージはあくまで「補助的なセルフケア」であり、医師の指導のもとで行うことを推奨します。
ストレスや睡眠の質を改善する
ストレスや不眠も顎関節症の発症・悪化に関係しています。精神的な緊張や不安は、無意識の食いしばりや筋肉のこわばりを引き起こす原因となります。
特に睡眠中の歯ぎしり・くいしばりは、ストレス発散行動の一種とも考えられており、精神的ストレスのケアが症状改善に寄与することが報告されています。
また、睡眠の質が向上することで筋肉の回復が進み、自律神経のバランスも整います。結果的に顎関節への負担が軽減されるかもしれません。
顎関節症を放置するとどうなる?
顎関節症の初期段階では、軽度の違和感や異音だけである場合も多いため、つい放置してしまいがちです。
しかし、適切な治療を受けずに放置すると、症状が進行し、日常生活に深刻な影響を与える可能性があります。
ここでは、顎関節症を放置するリスクや起こり得る合併症について、具体的に解説します。
顎関節症が重症化する
顎関節症を放置すると、重症化して関節の状態が悪化し、治療が難しくなる場合があります。
初期の「クリック音」や「軽い開けづらさ」は、保存療法で比較的改善しやすい段階です。しかし、治療せずに長期間放置すると、以下のような症状が現れることがあります。
- 開口障害の進行:
指1本分も口を開けられない状態になる - 関節円板の変形・逸脱固定:
顎が元の位置に戻らず手術適応になることも - 骨の変形(変形性関節症):
アゴの形状や噛み合わせに影響する
このように重症化すると、治療は長期化し、場合によっては外科的介入が必要になるケースも。
「痛くないから大丈夫」と思っても、音が鳴る・動きが不自然などの兆候は放置しないようにしましょう。
慢性痛や咬合異常を引き起こす
顎関節症の慢性化は、アゴだけでなく全身の健康に影響を及ぼします。
慢性痛に移行した顎関節症では、咬合異常(噛み合わせのズレ)が進行し、さらに次のような問題を引き起こします。
咬合異常はさらに歯並びの変化や虫歯・歯周病リスクの増加にもつながるため、顎関節症が「歯科全体の健康問題」に広がる可能性は否定できません。
特に、若年層での顎関節症の放置は将来的な咬合・骨格発達にも影響するため、違和感を感じた段階で早めに対応するのがカギとなります。
顎関節症の治療に関するよくある質問
ここでは、顎関節症について多く寄せられる質問についてわかりやすく回答します。
顎関節症は自然治癒しますか?
軽度の顎関節症は、一時的な生活習慣の見直しで症状が軽快する場合があります。
たとえば、「一時的にアゴがカクカク鳴る」「少し疲れた時に違和感が出る」などの症状は、筋肉の緊張やストレスによる一過性のものである場合が多いでしょう。
ただし、以下のような場合には症状の軽快の見込みが低く、放置はリスクを伴います。
- 開口障害が数日以上続いている
- 強い痛みがある
- 関節音が激しくなる・頻度が増える
- 噛み合わせに違和感がある
特に、関節円板の異常や骨の変形を伴うケースであれば、放置により治療が複雑化するおそれがあります。自然に治ると決めつけず、症状が続く場合は歯科に相談しましょう。
顎関節症の治療にかかる費用はどれくらいですか?
顎関節症の治療費は、受ける治療内容や保険の適用範囲によって異なります。
【一般的な費用の目安(保険適用の場合)】
| 項目 | 費用相場(3割負担) |
| 初診・検査 | 約1,500〜3,000円 |
| スプリント療法 | 約5,000〜15,000円(装置代+診察料) |
| 理学療法・調整 | 1回500〜1,500円程度 |
治療が長期にわたる場合や、装置の再製作が必要な場合には追加費用が発生します。
矯正治療や外科治療を行う場合は自由診療扱いとなる場合が多く、費用は数十万円に及ぶケースも。
初診時に治療計画と見積もりをよく確認し、デンタルローンの利用や分割払いについても検討することをおすすめします。
顎関節症を治療するには何科にかかるべきですか?
顎関節症の診療は、基本的に「歯科」または「口腔外科」の診療科で対応可能です。
- 歯科(一般歯科・顎関節専門医):スプリント療法・咬合調整・生活指導など
- 口腔外科:外科的処置や関節円板障害への高度な診断が必要な場合
- 耳鼻咽喉科・整形外科:関節の鑑別診断が必要なとき
中でも、日本顎関節学会の専門医が在籍するクリニックでは、専門的かつ包括的な診療が受けられるため安心です。
「mamoru」などの歯科検索・予約サービスを使えば、専門性の高い歯科医院をスムーズに見つけることができます。
顎関節症の時にやってはいけないことはありますか?
顎関節症の症状がある時には、関節や筋肉への負担を増やす行動を避けることが大切です。
これらの行動は、関節のズレや炎症の悪化、円板の変形を引き起こすリスクがあります。また、自己流マッサージやセルフ矯正も危険度が高いと言えます。
少しでも異常を感じたら、必ず歯科医師に相談のうえ、正しいケア方法を実践してください。
まとめ|顎関節症は早めの対応が大切
顎関節症を放置すると、痛みや噛み合わせの不調、全身の不調へとつながる可能性があります。初期の違和感のうちに治療を始めることで、多くの場合は保存的な方法で症状の改善が見込めます。
日常生活の姿勢やストレス、食習慣なども発症や悪化に関係するため、セルフケアも非常に重要です。歯科医院での専門的な診療を受けながら、ゆっくり治療を進めましょう。
アゴに不安を感じたら、我慢せず早めに歯科医院で相談しましょう。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。