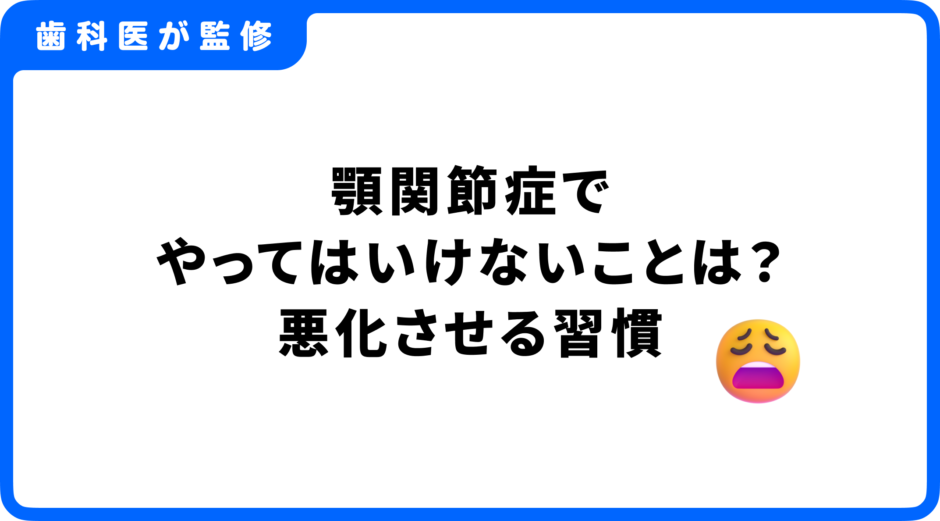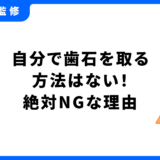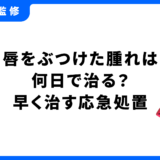口を開けるとカクカク音がする、食事中に顎が痛む、大きく口を開けられない……。
そんな顎関節症のつらい症状は、無意識の癖や習慣によってさらに悪化しているかもしれません。
症状を和らげようと自己流で顎をマッサージしたり、無理に口を開ける練習をしたりしていませんか?
良かれと思っての行動が、顎の関節や筋肉にさらなる負担をかけ、症状を長引かせている可能性があります。
この記事では、歯科専門家の視点から、顎関節症について以下内容を徹底解説。
- 顎関節症の人が絶対にやってはいけないこと
- 顎関節症を悪化させる理由
- 症状を緩和するセルフケア方法
- 専門医に相談すべきタイミング
顎の悩みを解決に導く情報を網羅しました。顎関節症が良くなりますように。
顎関節症で絶対にやってはいけないことリスト
顎関節症の症状を改善するためには、無意識のうちに顎の関節や筋肉に負担をかける「やってはいけない行動」をやめる必要があります。
結論としては、以下のNG行動を避けることが、症状緩和への第一歩となります。
- 硬い食べ物やガムを頻繁に食べる
- 無理に大きく口を開けようとする
- 痛くない方の顎でばかり食べ物を噛む
- 頬杖をつく・うつ伏せで寝る
- 歯を食いしばる・歯ぎしりをする
- 自己流で強いマッサージやストレッチをする
以下に、なぜNGなのか詳しい理由をあわせて解説します。自分の生活習慣に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
1. 硬い食べ物やガムを頻繁に食べる
フランスパン、スルメ、ナッツのような硬い食べ物や、長時間ガムを噛む習慣は、顎関節症の方が避けるべき代表的な行動です。
硬い食べ物やガムは、顎の関節や噛むための筋肉(咀嚼筋)に過大な負担をかけ、炎症や痛みを悪化させる直接的な原因となります。
顎関節症の症状が落ち着くまでは、意識的に柔らかい食事を選び、顎を休ませることが重要です。
2. 無理に大きく口を開けようとする
口が開きにくいからといって、指で無理やりこじ開けようとしたり、あくびを我慢せずに思い切り口を開けたりするのもNGです。
関節円板(顎関節にあるクッション)がずれている場合、さらなる状態悪化や、関節や靭帯を痛める原因となる可能性があります。
リハビリとして開口訓練を行う場合もありますが、専門家の指導のもとで行うのが一般的です。 自己判断で無理な力を加えるのは避けましょう。
3. 痛くない方の顎でばかり食べ物を噛む
顎が痛むと、無意識のうちに痛くない方の顎でばかり食べ物を噛んでしまうことがあります。 しかし、これも症状を悪化させる原因になります。
片側だけで噛む癖がつくと、顎全体のバランスが崩れ、負担が偏ってしまいます。 痛くない方の顎に余計な負荷がかかり、結果的に両側の顎関節に問題を引き起こす可能性があります。
できる範囲で、左右均等に噛むように意識することが大切です。
4. 頬杖をつく・うつ伏せで寝る
頬杖をつく姿勢や、うつ伏せで寝る習慣も、顎関節にとって好ましくありません。
頬杖やうつ伏せの姿勢は、片側の顎関節に持続的に圧力をかけることになります。
アンバランスな力が関節の位置をずらしたり、周囲の筋肉を緊張させたりして、顎関節症の症状の誘引や悪化の原因となります。
デスクワーク中や就寝時の姿勢にも注意が必要です。
5. 歯を食いしばる・歯ぎしりをする
日中、集中している時や緊張している時に無意識に歯を食いしばる癖(TCH:Tooth Contacting Habit)や夜間の歯ぎしりは、顎関節症の大きな原因の一つです。
本来、上下の歯が接触しているのは食事中のわずかな時間だけです。 持続的に強い力がかかると、顎関節や咀嚼筋に大きな負担がかかり、痛みや疲労感、さらには歯の摩耗を引き起こします。
意識的に上下の歯を離す習慣をつけましょう。場合によっては、歯科医院でマウスピース(スプリント)を作製するのも対策として有効です。
6. 自己流で強いマッサージやストレッチをする
顎の痛みやこりを和らげようと、自己流で顎周りを強く揉んだり、無理なストレッチをしたりするのも避けるべきです。
炎症が起きている部位を強く刺激すると、かえって炎症を悪化させてしまう可能性があります。 また、間違った方法でのストレッチは、関節や筋肉を痛める危険性も否定できません。
マッサージやストレッチ自体はセルフケアとして有効ですが、必ず専門家の指導を受け、正しい方法で優しく行うようにしましょう。
なぜ顎関節症になる?3つの主な原因
顎関節症が単一の原因で起こることは稀で、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症する場合がほとんどです。
多くの場合、顎関節やその周りの筋肉に負担がかかる生活習慣の積み重ねが、発症の引き金になります。
ここでは、顎関節症を引き起こす代表的な3つの原因について解説します。
1. 噛み合わせの不調和
歯並びが悪い、あるいは過去の歯科治療で入れた被せ物の高さが合っていない、といった噛み合わせの不調和は、顎関節症の原因の一つです。
噛み合わせがずれていると、顎がスムーズに動かせなかったり、特定の歯や顎関節に過度な負担がかかったりします。
この状態が長く続くと、顎の関節や筋肉にストレスが蓄積され、痛みや口の開きにくさといった症状が現れることがあります。
場合によっては、歯列矯正を検討してみても。歯列矯正についてはこちらの記事も参考にしてください。
2. 歯ぎしり・食いしばり(TCH)
日中、集中している時や緊張している時に無意識に歯を食いしばる癖や、夜間の歯ぎしりは、顎関節症の最大の原因と言っても過言ではありません。
このような上下の歯を不必要に接触させる癖を、TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)と呼びます。
本来、上下の歯が接触しているのは食事中のわずかな時間だけです。 持続的に強い力がかかると、顎関節や咀嚼筋に大きな負担がかかり、痛みや疲労感、さらには歯の摩耗を引き起こします。
3. ストレスや生活習慣の乱れ
精神的なストレスも、顎関節症と深く関係しています。
体はストレスを感じると無意識のうちに緊張するため、筋肉がこわばります。 特に、首や肩、顎周りの筋肉が緊張しやすく、これが食いしばりや歯ぎしりを誘発する原因となります。
また、睡眠不足や不規則な食生活といった生活習慣の乱れも、体のバランスを崩し、顎関節症の症状を悪化させる一因と考えられています。
顎関節症の症状を和らげる「やるべきセルフケア」
顎関節症の症状を悪化させるNG行動をやめるだけでも効果が見込めますが、さらに症状を和らげるため、セルフケアを試してみましょう。
顎への負担を減らし、筋肉の緊張をほぐすセルフケアを日常生活に取り入れれば、症状を改善できるかもしれません。
ここでは、今日からすぐに実践できる3つの有効なセルフケアをご紹介します。
顎に負担をかけない食べ物・食事を選ぶ
フランスパンのような硬い食べ物や、ガムのように長時間噛み続ける必要があるものは避けましょう。
痛みが強い時期は、顎の関節や筋肉をできるだけ休ませることが大切です。
以下の例のように、あまり噛まなくても食べられる柔らかい食事がおすすめです。おかゆ、スープ、豆腐、ヨーグルト、プリンといった、
食材を細かく切ったり、長く煮込んだりするなど、調理方法を工夫することによっても、顎への負担を減らせます。
正しいマッサージとストレッチで筋肉の緊張をほぐす
顎周りの筋肉の緊張は、痛みの大きな原因です。 正しいマッサージで、こり固まった筋肉を優しくほぐしてあげましょう。
頬骨の下あたりや、エラの周りにある、噛むと盛り上がる筋肉(咬筋)に人差し指と中指を当てます。 「痛気持ちいい」と感じるくらいの優しい力で、ゆっくりと円を描くようにマッサージします。
無理に強い力で押したり、長時間続けたりすると逆効果になるため、1回あたり数分程度に留めましょう。
ストレッチも有効ですが、自己流で行うと関節を痛める危険性があるため、必ず歯科医師や理学療法士の指導のもとで行ってください。
ストレス管理と姿勢の改善など生活習慣を見直す
顎関節症は、日々の生活習慣と深く関わっています。顎関節症の原因となり得る習慣を改善するのはとても効果的です。
例えば、ストレスは無意識の食いしばりを引き起こします。 趣味の時間を作ったり、ゆっくり入浴したり、自分なりのリラックス方法を見つけて心身の緊張を解きほぐすことが大切です。
猫背になったり頬杖をついたり、姿勢が悪いと顎の位置がずれ、関節に負担がかかります。 デスクワーク中は特に背筋を伸ばして正しい姿勢を意識しましょう。
また、就寝時はや片方の頭を下にして横向きに寝るのは避け、仰向けで寝るのが理想です。
生活習慣の小さな積み重ねが、顎関節症の症状改善につながります。
改善しなければ病院へ。顎関節症だと何科を受診すべき?
セルフケアだけで症状が改善しない場合や症状が悪化する場合は、専門家による診断と治療を受けましょう。
顎関節症の裏側には、セルフケアでは解決できない噛み合わせの問題や、より専門的な治療を必要とする原因が隠れている可能性があります。
つらい症状を我慢し続ける必要はありません。以下内容を参考に、病院にかかることも検討してみてください。
病院を受診する目安
以下の症状に一つでも当てはまる場合は、セルフケアだけで様子を見ずに、一度、医療機関を受診することをおすすめします。
- 強い痛みが出ている
- 以前よりも痛みが強くなっている
- 口がほとんど開かず、指が2本も入らない
- 口の開け閉めで毎回ひっかかりを感じる
- 何もしていない時でも顎に痛みがある
まずは歯科・口腔外科を受診する
顎関節症の症状で病院に行く場合、最初に相談すべきなのは歯科または口腔外科です。
まずは、かかりつけの歯科医院に相談するのが良いでしょう。 一般的な歯科医院でも、顎関節症の基本的な診察や、マウスピース治療に対応しているところは多いです。
より専門的な検査や治療が必要と判断された場合には、大学病院の口腔外科を紹介してもらえます。
歯科医院で行われる専門的な治療法
歯科医院では、問診やレントゲン撮影、顎の動きの検査などを行い、症状や原因を診断した上で、症状に合わせた専門的な治療が行われます。
代表的な治療法が「スプリント療法」です。 これは、歯型に合わせて作製したマウスピース(スプリント)を、主に就寝中に装着する治療法です。
マウスピースを装着することで、歯ぎしりや食いしばりから顎関節や筋肉にかかる負担を軽減し、顎をリラックスした状態に導きます。
顎関節症の治療法について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
顎関節症に関するよくある質問(Q&A)
顎関節症の治療を検討する上で、多くの人が抱く疑問にお答えします。
Q1. 顎が鳴るだけなのですが、放置しても大丈夫ですか?
A1. 痛みがなく、口を問題なく開けられる場合は、急いで治療が必要なケースは少ないです。 しかし、放置して良いとは一概には言えません。
顎の音には種類があります。「カクッ」というクリック音であれば、顎関節にあるクッション(関節円板)が少しずれているだけの場合が多く、経過観察となることがあります。
ただし、音が「ジャリジャリ」「ミシミシ」といった砂が擦れるような音(クレピタス音)に変わった場合や、痛みを伴い始めた場合は、関節の骨が変形している可能性も考えられます。
早めの病院受診をおすすめします。
Q2. マウスピース(スプリント)は市販のものではダメですか?
A2. 市販のマウスピースは絶対に使用しないでください。
市販のマウスピースは、自分の歯型に合わせて作られたものではないため、顎関節症の治療には使えません。
マウスピースの形やサイズが合わないと、噛み合わせを不安定にさせ、顎の関節や筋肉に負担をかけて症状を悪化させる危険性があります。
歯科医院で作製するマウスピース(スプリント)は、専門家が噛み合わせを精密に診断した上で作る医療機器です。
必ず 歯科医院で自分に合ったものを作製してもらってください。
Q3. 整体やマッサージで顎関節症は治りますか?
A3. 症状の緩和には役立ちますが、根本的な治療にはなりません。
整体やマッサージは、顎周りの筋肉の緊張をほぐして血行を促進することで、痛みを和らげる効果が期待できます。 これは有効な対症療法の一つです。
しかし、顎関節症の原因が噛み合わせの不調和や顎の関節自体にある場合、整体やマッサージではその根本原因を解決することはできません。
歯科医院での専門的な診断と治療を基本とし、その補助として整体やマッサージを取り入れるのが望ましいでしょう。
まとめ:やってはいけない行動は控え、正しいケアと専門的治療を
本記事では、顎関節症の人がやってはいけないことから、症状を和らげるセルフケア、そして専門的な治療法まで詳しく解説しました。
結論として、つらい症状を改善するためには、まず顎に負担をかけるNG行動をやめることが最も重要です。
「歯科まもる予約」で顎関節症を相談できる医院を見つけよう
セルフケアで症状が改善しない場合、我慢せずに専門家へ相談しましょう。
あなたの顎の悩みに寄り添い、最適な治療法を一緒に考えてくれる歯科医院探しをサポートするのが、予防歯科サービス「歯科まもる予約」です。
全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかります。
つらい症状を一人で抱え込まず、まずは信頼できる歯科医師に相談することから始めてみませんか。