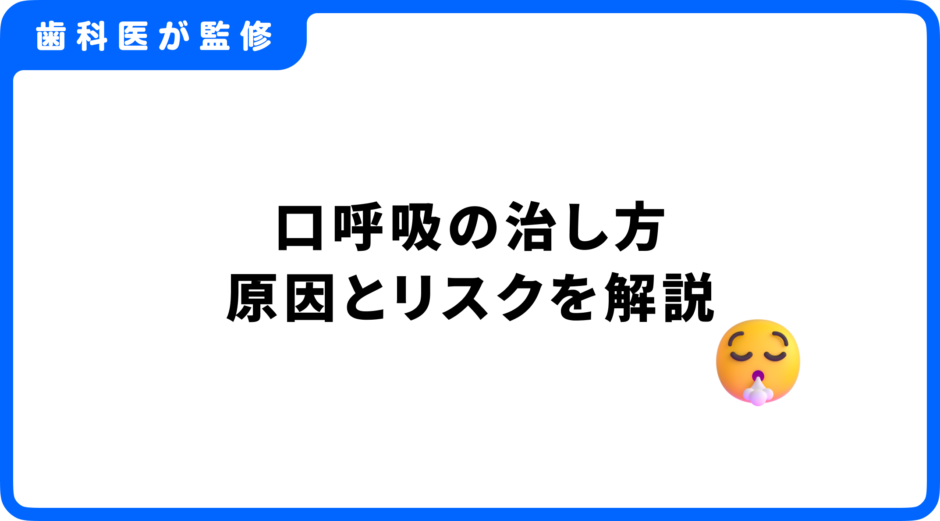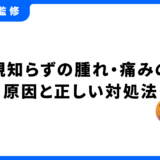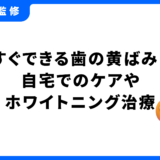「朝起きると喉が痛い」
「いびきを指摘された」
「子どもの歯並びが気になる」
もしかすると、いずれも口呼吸が原因かもしれません。
口呼吸をただの癖として放っておくのは危険です。口呼吸は、虫歯や歯周病、出っ歯や顔のゆがみなど、さまざまな不調や発育の問題につながります。見逃せない健康リスクといえるでしょう。
本記事では、歯科医療の視点から、口呼吸の原因や治し方を網羅的に解説します。
口呼吸のリスクを理解し、今日から実践してみましょう。
子どもの口呼吸が気になる方や、自身の健康が気になる方は必見です。
口呼吸は危ない?口呼吸の弊害やリスク
口呼吸は、全身の健康や口内環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
口呼吸の悪影響は多方面にわたるため、正しく理解し、注意する必要があります。
ここでは、口呼吸のリスクを6つ解説します。
・歯並びや骨格に影響する
・睡眠の質が下がる
・睡眠時無呼吸症候群のリスクがある
・子どもの成長や発達に悪影響が出る
・虫歯や歯周病になりやすくなる
・口臭が強くなる
歯並びや骨格に影響する
口呼吸は、顔の骨格の成長に悪影響を与える可能性があります。また、歯並びの乱れの一因でもあります。
本来、舌は上あごに接しており、上顎の発育を内側から支える「天然の矯正力」として働いています。
しかし、口呼吸が習慣化している人は舌が下に落ちやすく、上あごの成長が不十分になります。
その結果、出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)になったり、歯並びが狭くなる一因となる可能性があります。
また、呼吸するために口が常に開いていると、口輪筋(こうりんきん:口の周りを囲んでいる表情筋)や頬筋などの周囲の筋肉バランスが崩れます。
これにより、顔貌の歪みや下顎の後退など、骨格的問題も引き起こす可能性があります。
子どもの場合、成長とともに症状が固定化する前に、口呼吸を早めに改善することが肝心です。
睡眠の質が下がる
口呼吸は、睡眠の質を大きく低下させる原因になります。
鼻呼吸には、吸った空気を加湿・加温して異物を除去する「フィルター作用」がありますが、口呼吸ではこの機能が働きません。
乾燥した冷たい空気が直接喉に届くため、就寝中の喉の不快感や炎症、覚醒頻度の増加を引き起こします。
さらに、口呼吸によって空気の流れが不安定になるため、呼吸が浅くなります。
一部の研究では、酸素摂取量の変化が報告されています。熟睡を妨げる可能性も否定できません。
朝起きても疲れが取れない、日中眠気が強いなどの症状がある方は、睡眠の質が落ちているサインです。
口呼吸の癖がある場合、口呼吸を改善すれば睡眠の質を高められるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群のリスクがある
口呼吸は「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」のリスク要因の一つです。
口を開いたまま仰向けで寝ると、舌根(舌の奥)が喉に落ち込み、気道をふさいでしまうことがあります。
これにより、呼吸が断続的に止まる無呼吸状態が発生します。
SASは高血圧・心疾患・脳卒中などの重大な疾患と関係しているため、放置は危険です。
大きないびきや日中の強い眠気がある方は、耳鼻咽喉科などの受診をおすすめします。
歯科では、専用のマウスピース(スリープスプリント)を使った治療などによって、改善を目指します。
子どもの成長や発達に悪影響が出る
子どもの口呼吸は、全身の成長を阻害し、学習・集中力にも悪影響を及ぼす可能性があります。
口呼吸は、鼻呼吸に比べて酸素の吸収効率が悪いのが特徴です。
慢性的な口呼吸によって、酸素供給不足による疲労や注意力の低下、免疫力の低下が起こりやすくなります。
さらに、顎の変形や発音障害、顔貌の非対称化など、成長期特有のリスクも大きいため注意が必要です。
口呼吸している状態に早めに気づき、歯科や耳鼻科での機能訓練や原因治療を始めましょう。
子どもの健やかな成長への第一歩となるはずです。
虫歯や歯周病になりやすくなる
口呼吸によって口の中が乾くと、唾液の働きが低下し、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
唾液には、細菌の繁殖を抑え、食べかすを洗い流す「自浄作用」があります。
口呼吸によって口を開いたままだと、唾液の分泌が減少し、細菌が繁殖しやすい環境になってしまうのです。
特に歯周病は歯を失う大きな原因であり、糖尿病や心血管疾患などの全身疾患とも関連しています。
身体への悪影響は重大です。
口の乾燥や、虫歯になりやすいことが気になる方は、口呼吸が関与している可能性を疑いましょう。
口臭が強くなる
口呼吸によって唾液が減少すると、細菌が増殖し、口臭が強くなる傾向があります。
多くの場合、口臭の原因は、口内の細菌がタンパク質を分解することで発生する「揮発性硫黄化合物」です。
口の中が乾燥すると細菌が活動しやすくなり、においの元となるガスを発生させやすくなります。
さらに口臭は、舌の表面にたまる「舌苔(ぜったい)」の増加や、歯周病とも関連しています。
「最近口臭が気になる」と感じる方は、呼吸の仕方を見直すことが第一歩です。
口呼吸チェックリスト
口呼吸をしているかどうかは、日常の小さなサインからはかることができます。
子どもが口呼吸をしているかどうかも、気をつけて見ているとわかります。
気づかずに口呼吸を続けていると、虫歯・歯並び・睡眠障害など多くの健康トラブルを引き起こすため、早期に気づくことが大切です。
以下は、口呼吸かどうかの診断に役立つチェックリストです。
・口を閉じているつもりがつい開いてしまう
・集中しているときやスマホ操作中に口が開いてしまう
・朝起きると喉の乾燥や痛みを感じる
・寝ている間にいびきをかいている
・唇の乾燥やひび割れが気になる
・食べるときにクチャクチャ音がする
・鼻がつまって息がしづらい
・舌が上あごにくっついていない
・歯医者で「出っ歯」と診断されたことがある
・口臭が気になることがある
上記のリストのうち、あてはまる項目が多いほど、口呼吸が癖になっている可能性があります。
歯科医院や耳鼻咽喉科への受診を検討しましょう。
口呼吸は自覚するのが難しいと言われます。
チェックリストを参考に、口呼吸をしていると感じたら、早めに鼻呼吸へ移行することを目指してください。
口呼吸の原因【起きている時編】
口呼吸の原因について知っておきましょう。
本記事では、起きている時と寝ている時に分けて、口呼吸の原因を解説します。
まずは起きている時の口呼吸について、考えられる原因を紹介します。
・口周りの筋力が弱い
・舌の位置が正しくない
・姿勢が悪い
・無意識に口が開いている
口周りの筋力が弱い
口を閉じるための筋肉(口輪筋や頬筋)が弱いと、自然に口が開いてしまい、口呼吸の癖がつく原因になります。
特にやわらかい食べ物中心の食生活や、表情の少ない生活が続くと、筋肉の機能が低下しがちです。
口周りの筋力の低下は、口呼吸だけでなく、歯並びの悪化や出っ歯の一因にもなります。
舌の位置が正しくない
舌は本来、上あごにぴったりとついている状態が正常です。
しかし、口呼吸の人は舌が下に落ちた状態になっており、上顎を支える力が働かず、口が開きやすくなります。
この状態が続くと、口呼吸がますます癖として定着してしまいます。
姿勢が悪い
猫背や前傾姿勢になると気道が圧迫され、口呼吸しやすくなります。
スマホやゲーム中などにうつむいた姿勢では、顎が下がり、自然と口が開く形になります。
慢性的に姿勢が悪い状態で生活していると、自然と口呼吸しやすい状態になってしまいます。
意識して姿勢を正すことが大切です。
無意識に口が開いている
リラックスしているときや集中しているとき、無意識に口が開いてしまう場合は注意が必要です。
無意識に口が開いてしまう癖は、筋力の低下や習慣的な呼吸の仕方が影響していることが多く、自然に鼻呼吸へ移行できなくなっている可能性があります。
意識的に口を閉じるようにし、鼻呼吸への移行を目指しましょう。
口呼吸の原因【寝ている時編】
就寝中は気づかないうちに、さまざまな身体的要因によって口呼吸になってしまっていると考えられます。
寝ている時の口呼吸の原因を解説します。
・鼻が詰まっている
・睡眠時無呼吸症候群がある
・出っ歯や顎の形に問題がある
・仰向けで寝ている
鼻が詰まっている
鼻づまりは、寝ている間の口呼吸の大きな原因です。
アレルギー性鼻炎や風邪などで鼻の通りが悪くなると、鼻呼吸がうまくできず、無意識に口で空気を取り入れようとします。
特に、季節性アレルギーやハウスダストによる鼻づまりは慢性化しやすく、睡眠中の乾燥やいびきの原因にもなります。
鼻が詰まりやすい方は、耳鼻咽喉科での検査やアレルギー治療が有効です。
睡眠時無呼吸症候群がある
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、口呼吸と深く関わっています。
睡眠時無呼吸症候群の症状が起こると、睡眠中に気道がふさがれ、呼吸が数秒から数十秒止まる状態が繰り返されるのです。
仰向けで寝ている場合などに、舌が落ち込んで気道をふさいでしまうと、自然と口が開いて口呼吸が誘発されます。
就寝中のいびきや日中の強い眠気がある場合は、専門医による治療や、歯科でのスリープスプリント治療が勧められます。
出っ歯や顎の形に問題がある
上顎前突(出っ歯)や小さな顎など、骨格の形が口呼吸の原因になることがあります。
顎が後退していたり、歯の並びが前方に出ていたりすると、口が自然に閉じづらくなり、就寝中に開いたままの状態が続きます。
子どもの場合、成長期に骨格や歯並びなどの形が固定化する前に、早期の矯正治療を行うと効果的です。
歯の噛み合わせが悪いと感じたら、歯科に相談しましょう。
仰向けで寝ている
仰向けの姿勢で寝ることが、口呼吸を悪化させている可能性があります。
仰向けだと、舌や顎が重力で下がって気道をふさぐ形になりやすいため、口で呼吸しようとする場合があります。
また、枕の高さが合っていないと首の角度が悪くなり、さらに鼻呼吸がしにくくなる人も。
寝具や枕を見直して、口呼吸が気になる場合は横向き寝への習慣づけも試してみてください。
個人差はありますが、睡眠中の口呼吸対策として効果的です。
口呼吸の治し方10選
口呼吸は、複数の方法を組み合わせて段階的に改善していくことが重要です。
ここでは、口呼吸を治すための実践的な方法を10個ご紹介します。
鼻呼吸を意識して行う
口呼吸を改善する第一の方法は、「鼻で呼吸する」という基本習慣を意識的に身につけることです。
日中は、作業中や移動中などいつでも「鼻で呼吸できているか」をこまめに意識しましょう。
始めは難しく感じても、意識し続けることで無意識下でも自然に鼻呼吸ができるようになってきます。
特に子どもの場合は、保護者が声かけすると意識づけしやすくなります。
家庭内で「鼻呼吸習慣」について話す時間をとるのが効果的です。
口周りの筋肉を鍛える
口輪筋や頬筋などの筋肉を鍛える運動に取り組むのも効果的です。
口周りの筋肉が弱くなると、無意識に口が開いて口呼吸を誘発してしまいます。
口輪筋や頬筋の筋肉を鍛える運動の例として、以下が挙げられます。
- あ・い・う・べー体操
- ストローを吸う
- 風船を膨らませる
口周りの筋肉を鍛えるには、口を使った遊びや運動が効果的です。
さらに、硬めの食材をしっかり噛む食習慣も、筋肉を維持するために有効です。
日常の食事や会話の中で口元を動かすことを心がけるだけでも、表情にハリが出て、自然な口元が保たれるようになります。
舌を正しい位置に置く練習をする
舌の正しい位置である「上あごの前歯の裏側」あたりに軽くつける練習をしましょう。
この位置に舌が安定していることで、上顎が正しく発達して気道を確保しやすくなり、口も自然に閉じるようになります。
舌のトレーニングには、上あごの前歯の裏側に舌を当てて5秒キープ×10回などの簡単な練習が効果的です。
歯科医院や矯正歯科では、正しい舌の使い方を指導するプログラム(MFT)も用意されています。
「舌が落ちているかも」という人は、プログラムの受講も検討してみてください。
歯並びや噛み合わせを矯正する
歯列や骨格に問題がある場合、歯列矯正により噛み合わせや顎のバランスを整えることが有効です。
歯列矯正は、見た目の改善だけでなく、舌や口唇の機能を本来の状態に戻す役割も果たします。
特に子どもの場合、歯列矯正によって骨格ごと整えることが可能なため、早期の治療が推奨されます。
出っ歯や開咬(奥歯は噛み合うが前歯が噛み合わない状態)の症状がある場合は、口呼吸の改善のためにも、歯科医師に相談しましょう。
MFT(口腔筋機能療法)を受ける
MFT(Myofunctional Therapy:口腔筋機能療法)は、舌や口唇、頬の筋肉を正しく使えるようにする訓練です。
舌の癖や飲み込み方、発音の誤りなど、口腔機能の低下による口呼吸を根本的に改善するための治療法として注目されています。
歯科医院や矯正歯科で、患者一人ひとりに合ったプログラムを受けられます。
専門的な指導によって、口呼吸の癖の改善を目指せるのが特徴です。
MFTは、小児矯正の補助としても活用されており、治療後の後戻り防止にもつながります。
鼻の病気を治療する
鼻に異常があると、物理的に鼻呼吸ができず、口呼吸にならざるを得ない状態になります。
口呼吸を改善するために、治療した方がいい鼻の病気の例は以下の通りです。
- アレルギー性鼻炎
- 慢性副鼻腔炎
- 鼻中隔弯曲症(びちゅうかくわんきょくしょう)
鼻の病気を治療するには、耳鼻咽喉科の診療が必要です。
抗アレルギー薬や点鼻薬、場合によっては手術などの根本治療によって、鼻の通気性が改善し、自然と鼻呼吸がしやすくなります。
「口呼吸をやめたいけど鼻が通らない」という人は、まずは鼻の疾患がないか耳鼻科で確認してもらいましょう。
口閉じテープを使う
寝ている間に口が開いてしまう人には、市販の「口閉じテープ」の使用が効果的です。
これは、睡眠中に物理的に口を閉じた状態に保つことで、鼻呼吸を促す補助具です。
貼り方は簡単で、就寝前に唇の中央に優しく貼るだけです。
毎日口閉じテープを貼って寝れば、鼻呼吸習慣の定着が期待できます。
ただし、鼻づまりがある人や皮膚が弱い方、子どもは注意が必要なため、使用前に医師と相談しましょう。
寝具を見直す
枕やマットレスなどの寝具を見直すのも一つの方法です。
枕の高さやマットレスの硬さが合っていないと、気道が圧迫されて口呼吸を間接的に誘発しやすくなります。
仰向け寝の際に舌が落ちやすくなるのも、枕の高さや寝る姿勢に原因があるかもしれません。
推奨されるのは、横向き寝をサポートする形状の枕や、首と肩の自然なカーブを保てる寝具です。
質のよい睡眠と呼吸習慣を支えるためにも、寝具が自分に合っているかを定期的に見直しましょう。
医療機関に相談する
なかなか口呼吸が改善しない場合には、歯科や耳鼻科の受診が必要です。
歯科ではMFT(口腔筋機能療法)や歯列矯正、耳鼻科ではアレルギー治療や鼻づまり治療を受けられます。
口呼吸を「治したい」と思ったその時が改善のチャンス。医療機関を頼ることも考えてみてください。
まとめ
口呼吸は、歯並びの乱れや虫歯、口臭、睡眠障害など、さまざまな健康リスクを引き起こします。
口呼吸の原因は、筋力低下や姿勢、鼻の疾患など多岐にわたります。
まずは自身が鼻呼吸できているかの状態を知り、改善のためにできることから始めましょう。
日常の意識づけやトレーニングに加え、歯科や耳鼻咽喉科での治療を受けることで、根本的な改善を期待できます。
口呼吸に悩んでいる場合は、早めに対策を行い、将来の健康を守りましょう。
歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。