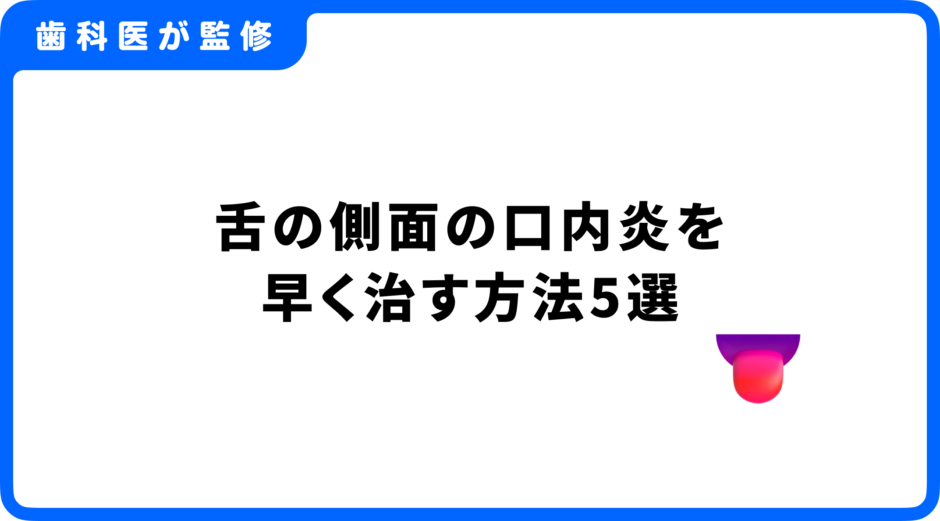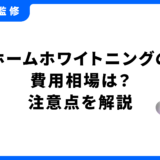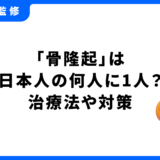「しゃべるたびにズキッ!」「食事をするのが怖いくらい痛い…」
舌の側面にできた口内炎は、歯に当たるたびに激しい痛みが走り、日常生活に大きな支障をきたしますよね。
一刻も早く、このつらい痛みから解放されたいと強く願っているのではないでしょうか。
結論として、即効性を求めるなら「口内炎に直接貼る・塗るタイプの市販薬」を使い、同時に「ビタミンB群の摂取」と「徹底した口腔ケア」を実践するのが最も効果的です。
この記事では、痛い舌の口内炎を1日でも早く治すための具体的な方法を、専門家の視点から徹底的に解説します。
- 舌の側面の口内炎を早く治す方法
- 舌の側面に口内炎ができやすい理由
- 症状に合わせた市販薬の正しい選び方
- 口内炎を予防する生活習慣
- 危険な口内炎との見分け方
舌の側面の口内炎を早く治す方法5選
話すたびに、食べるたびに歯が当たって激しく痛む、舌の側面の口内炎。
一刻も早くこのつらさから解放されたいですよね。
結論として、痛い舌の口内炎を1日でも早く治すためには、これから紹介する5つのセルフケアを組み合わせて実践することが最も効果的です。
市販薬で外から直接アプローチしつつ、食事や生活習慣を見直して体の内側から治癒力を高めていきましょう。
1. 貼る・塗るタイプの市販薬を使う
つらい痛みを今すぐなんとかしたい、そして早く治したいなら、市販薬の活用が最も即効性が期待できる方法です。
薬局やドラッグストアで購入できる口内炎治療薬には、炎症を鎮める成分や、痛みの原因となる刺激から患部を物理的に保護する成分が含まれています。
特に、舌の側面にできた口内炎には、以下のタイプがおすすめです。
| 貼るパッチタイプ | 患部に直接貼り付けて、歯や食べ物との接触をガードして、痛みの軽減に役立ちます。痛みが強く、話したり食べたりするのがつらい方に最適です。 |
| 塗る軟膏タイプ | 患部に直接塗布し、炎症を抑えます。就寝前に塗ると、薬の成分がじっくりと浸透しやすくなります。 |
どの薬を選べばよいか迷った場合は、薬剤師に相談し、ご自身の症状に合ったものを選びましょう。
2. 粘膜の修復を助けるビタミンB群を摂取する
口内炎の回復を体の内側からサポートするために、皮膚や粘膜の健康を維持する働きのある「ビタミンB群」を積極的に摂取することが非常に大切です。
特に、ビタミンB2やビタミンB6は、傷ついた舌の粘膜の修復を助け、口内炎の治りを早める効果が期待できます。これらの栄養素は、以下のような食品に多く含まれています。
・レバー(豚・牛・鶏)
・うなぎ
・卵
・納豆
・乳製品(牛乳、ヨーグルト)
・バナナ
・マグロ、カツオ など
毎日の食事で十分な量を摂るのが難しい場合は、サプリメントやビタミン剤を補助的に活用するのもおすすめです。
3. うがい薬で口腔内を殺菌・消毒する
口の中が不衛生な状態だと、細菌が繁殖して口内炎の治りが遅くなったり、症状が悪化したりする原因になります。
殺菌成分の入ったうがい薬で口の中を清潔に保つことは、回復を早めるための基本です。
うがいによって口腔内の細菌を減らすことで、口内炎の二次感染を防ぎ、健やかな口内環境を整えることができます。
市販のうがい薬を選ぶ際は、
- ポビドンヨード
- グルコン酸クロルヘキシジン
- セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)
などの殺菌・消毒成分が含まれているものが効果的です。
ただし、刺激が強く感じられることもあるため、ノンアルコールタイプや、しみにくいものを選ぶと良いでしょう。
毎食後や就寝前の歯磨きと合わせて、うがいを習慣にしましょう。
4. 刺激物・熱いものを避け、患部を守る
口内炎ができているときは、患部への余計な刺激を避けることが、痛みを和らげ、治癒を早めるための鉄則です。
舌の側面は特に歯に当たりやすく、ただでさえ刺激を受けやすい場所です。食事の際は、以下の刺激物を避けるように意識しましょう。
これらの食品は、患部の炎症を悪化させ、激しい痛みを引き起こす原因となります。口内炎が治るまでは、おかゆやスープ、ゼリーなど、口当たりが優しく、栄養のある食事がおすすめです。
5. 免疫力を高めるため、十分な睡眠をとる
口内炎は、体の免疫力が低下しているサインでもあります。
薬や食事に気をつけても、体が疲れていては、なかなか治癒に向かいません。
十分な睡眠と休養をとり、体の抵抗力を高めることが、口内炎を根本から治すための鍵となります。
睡眠不足や疲労、ストレスは、免疫機能を低下させ、口内炎の治りを遅らせる大きな原因です。
できるだけ毎日6〜8時間の睡眠時間を確保し、心身ともにリラックスする時間を設けましょう。
体をしっかりと休ませて免疫力を回復させることが、つらい口内炎を早く治すための近道なのです。
舌の側面に口内炎ができるのはなぜ?考えられる原因
「どうしていつも舌の横にばかり口内炎ができるのだろう?」と、不思議に思ったことはありませんか?
実は、舌の側面は口内炎ができやすい、いくつかの明確な原因が重なりやすい場所なのです。
ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。
1. 歯が当たる・噛んでしまうなどの物理的な刺激
舌の側面に口内炎ができる最大の原因は、歯との接触による継続的な「物理的な刺激」です。
舌は会話や食事で常に動いており、その側面は歯列に最も近い場所にあります。そのため、
- 尖っている歯や、欠けた詰め物がある
- 歯並びが悪く、特定の歯が舌に当たりやすい
- 合わない入れ歯や矯正装置がこすれる
- 食事中に誤って舌を噛んでしまった
といったことが引き金となり、舌の粘膜に小さな傷ができます。
この傷に細菌が入り込むことで炎症が起き、痛みを伴う口内炎へと発展してしまうのです。
特に同じ場所に繰り返しできる場合は、歯が原因となっている可能性が高いと言えます。
2. ストレスや疲労による免疫力の低下
仕事や人間関係による精神的なストレスや、睡眠不足などの肉体的な疲労が溜まると、体の免疫力が低下します。
これも口内炎を引き起こす大きな原因の一つです。
免疫力が低下すると、普段なら抑え込めている口腔内の常在菌の活動が活発になり、少しの刺激でも炎症を起こしやすい状態になります。
つまり、体の抵抗力が落ちていると、普段なら問題にならないような歯の接触でさえも、口内炎に繋がりやすくなってしまうのです。
忙しい時期や、疲れが溜まっているときに口内炎ができやすいのは、このためです。
3. ビタミンB群不足などの栄養バランスの乱れ
皮膚や粘膜の健康を維持する栄養素の不足も、口内炎の直接的な原因となります。
特に、「ビタミンB群」は、粘膜のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つために不可欠な成分です。
外食が多かったり、偏った食事をしていたりして栄養バランスが乱れ、ビタミンB2やビタミンB6などが不足すると、舌の粘膜が弱くなり、荒れやすくなります。
このような状態が長期間続くと、口内炎ができやすくなってしまうのです。
バランスの取れた食事は、口内炎の予防・改善の基本となります。
4. 口の中の乾燥や不衛生による細菌の繁殖
唾液には、口の中を洗い流し、細菌の繁殖を抑える「自浄作用」があります。
しかし、ストレスや薬の副作用、口呼吸などで唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥した状態(ドライマウス)になると、この作用が十分に働かなくなります。
その結果、口の中で細菌が繁殖しやすくなり、小さな傷からも口内炎が発生・悪化しやすくなります。
また、歯磨きが不十分で口の中が不衛生な場合も同様に、細菌が増えやすい環境となり、口内炎のリスクを高めてしまいます。
5. 舌がんなど他の病気である可能性
ほとんどの口内炎は1~2週間で自然に治りますが、中には舌がんなどの重大な病気の初期症状である可能性もゼロではありません。
以下のような特徴がある場合は、自己判断で放置せず、すぐに専門の医療機関を受診してください。
| 期間 | 2週間以上たっても治らない、または大きくなっている |
| 硬さ | 患部やその周囲に硬い「しこり」がある |
| 形・色 | 境界がはっきりせず、まだらに赤くなったり白くなったりしている |
| 痛み | 初期段階では痛みがほとんどない場合もある |
これらは「ただの口内炎」との大きな違いです。
少しでも「おかしいな」と感じたら、まずは歯科・口腔外科や耳鼻咽喉科で確認してもらうことが非常に大切です。
症状別|おすすめ市販薬の選び方と正しい使い方
舌の側面にできた口内炎を早く治すには、市販薬の活用が非常に効果的です。
しかし、薬には様々なタイプがあり、ご自身の症状や口内炎の状態に合わせて最適なものを選ぶことが、効果を最大限に引き出すための鍵となります。
ここでは、症状別におすすめの市販薬タイプと、その正しい使い方を解説します。
即効性重視なら「貼るパッチタイプ」
「歯が当たるたびに激痛が走る」「痛くて食事もままならない」という方には、患部に直接貼り付けて保護する「パッチタイプ」が最もおすすめです。
パッチが患部を物理的に覆うことで、歯や食べ物、飲み物などのあらゆる刺激から口内炎をしっかりガード。
貼った瞬間からつらい痛みが和らぐ、高い即効性が最大の魅力です。
また、有効成分が患部に密着し続けるため、薬の効果が持続しやすいというメリットもあります。
早く治すというより、物理的な痛みを軽減するものです。
1. 患部の唾液をティッシュなどで軽く拭き取る。
2. パッチをシートから剥がし、患部に直接貼り付ける。
3. 指で数秒間軽く押さえて、しっかりと密着させる。
1つだけできた、はっきりとした大きさの口内炎に特に効果的です。
広範囲にできた・塗りにくい場所には「スプレータイプ」
「口内炎が複数できている」「舌の奥の方など、指で薬を塗りにくい場所にある」という場合には、シュッと吹きかけるだけで使える「スプレータイプ」が便利です。
スプレータイプなら、指で直接患部に触れる必要がないため衛生的で、塗るときの痛みもありません。
広範囲に薬液を届かせることができ、届きにくい場所にも簡単にアプローチできるのが大きなメリットです。
メントールなどが配合され、清涼感のある使い心地のものも多くあります。
1. 容器のノズルを患部に向ける。
2. 息を止め、1〜2プッシュ吹きかける。
3. 塗布後、薬液が浸透するように2〜3分は飲食やうがいを控える。
手軽にケアをしたい方や、軟膏のベタつきが苦手な方にもおすすめです。
根本から治すなら「ビタミン剤配合の飲み薬」
「口内炎が繰り返しできる」「体の内側からしっかり治したい」という方には、ビタミン剤が配合された「飲み薬」でのケアが栄養欠乏に対する根本的な解決に繋がります。
飲み薬は、口内炎の原因となりやすい栄養不足を体の中から改善するアプローチです。
皮膚や粘膜の健康維持に不可欠なビタミンB2やビタミンB6などを補給することで、傷ついた粘膜の修復を促し、口内炎ができにくい丈夫な口内環境へと導きます。
1. 製品に記載されている用法・用量を守り、水またはぬるま湯で服用する。
2. ビタミンB群のサプリメントは、栄養欠乏に起因する口内炎の改善に有効です。
直接的な痛み止め効果はありませんが、パッチやスプレーなどの外用薬と併用することで、より効果的に口内炎を治療することができます。
こんな症状はすぐ病院へ!受診すべき危険なサイン
ほとんどの口内炎は自然に治る良性のものですが、中には注意すべき「危険なサイン」が隠れていることもあります。
セルフケアを続けても改善しない、あるいはいつもと様子が違うと感じたら、それは体からの重要なSOSサインかもしれません。
以下のような症状が見られる場合は、自己判断で様子を見ずに、速やかに専門の医療機関を受診してください。
2週間以上経っても治らない・大きくなっている
通常の口内炎(アフタ性口内炎)は、長くても1~2週間で自然に治癒に向かいます。
もし、市販薬を使ったり、生活習慣に気をつけたりしても、2週間以上全く治る気配がない、あるいは以前より明らかに大きくなっている場合は注意が必要です。
単なる炎症ではなく、腫瘍(しゅよう)など、別の病気の可能性が考えられます。
特に、治ったり再発したりを同じ場所で繰り返す場合も、継続的な刺激が原因で悪いものに変化するリスクが潜んでいるため、一度専門家による診察を受けることを強くお勧めします。
しこりがある・患部の境界が不明瞭
患部やその周りを舌で触ったり、指で軽く触れてみたりしてください。
その際に、明らかに硬い「しこり」のようなものを感じる場合は、危険なサインである可能性が非常に高いです。
一般的な口内炎は、表面がへこんだ柔らかい潰瘍(かいよう)です。
しかし、悪性腫瘍(がん)の場合、その病変の内部や周囲に硬いしこりを伴うことが多くあります。
また、口内炎の形も重要な判断材料です。
- 通常の口内炎: 円形または楕円形で、境界がはっきりしている。
- 危険なサイン: 境界がギザギザして不明瞭、まだらに赤や白の部分が混じっている。
このような見た目の異常に気づいたら、決して放置しないでください。
痛みが激しく、食事や水分補給も困難
口内炎は痛みを伴うものですが、その痛みのレベルが尋常ではなく、日常生活に深刻な支障をきたしている場合も、受診の目安となります。
例えば、
- 痛みのために食事が全く喉を通らない
- 水を飲むことさえつらく、脱水症状が心配される
- 痛みがどんどん強くなり、夜も眠れない
といった状態は、単なる口内炎の症状としては重度です。
我慢していると、栄養不足や脱水によってさらに体の抵抗力が落ち、回復を遅らせる悪循環に陥ってしまいます。
痛みの原因を特定し、適切な処置を受けるためにも、すぐに病院へ行きましょう。
▶関連記事:舌の付け根が痛いのはなぜ?原因や病気・自宅でできる対処法を歯科医が解説
病院は何科を受診すればいい?
「すぐに病院へ」と言われても、何科に行けばよいか迷いますよね。
舌の側面の口内炎で受診すべき診療科は、主に以下の2つです。
| 歯科・口腔外科 | まず第一に検討すべき診療科です。歯科医師、特に口腔外科の専門医は、口の中にできるあらゆる病気の専門家です。口内炎の診察はもちろん、原因となっている可能性のある歯の鋭利な部分や、不適合な詰め物・入れ歯など、口全体の環境を総合的にチェックしてくれます。 |
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科も、鼻や喉と合わせて、舌を含む口の中を専門領域としています。近所に口腔外科がない場合や、かかりつけの耳鼻咽喉科がある場合は、こちらを受診しても問題ありません。 |
どちらを受診すればよいか迷った場合は、まずはかかりつけの歯科医院に相談するのがスムーズでしょう。
そこで専門的な検査が必要だと判断されれば、適切な高次医療機関(大学病院など)を紹介してもらえます。
舌の側面の口内炎を予防する生活習慣
一度治っても、何度も繰り返してしまうのが口内炎のやっかいなところ。つらい痛みに悩まされないためには、普段から予防を意識した生活を送ることが何よりも大切です。
今日から実践できる、口内炎の主な予防策は以下の通りです。これらの健康的な生活習慣は、口内炎だけでなく、全身の健康維持にも繋がります。
口腔内を清潔に保つ
毎日の丁寧な歯磨きや、うがいを習慣にし、細菌が繁殖しにくい環境を維持しましょう。
栄養バランスの取れた食事
特に、粘膜の健康をサポートするビタミンB群(レバー、卵、納豆など)を日々の食事に積極的に取り入れましょう。
十分な睡眠とストレス管理
体の免疫力を高く保つため、心身ともにしっかりと休養をとることが大切です。
定期的な歯科検診
自分では気づかないうちに、口内炎の原因となる歯噛み合わせの変化や、合わない詰め物ができているかもしれません。定期的に歯科医院でチェックしてもらい、口内トラブルの種を早期に摘み取っておきましょう。
舌の側面にできる口内炎に関するよくある質問
ここでは、舌の側面にできる口内炎に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
Q. 舌の口内炎はキスなどで他の人にうつりますか?
A. 最も一般的な「アフタ性口内炎」は、うつりません。しかし、ウイルス性の口内炎はうつる可能性があります。
口内炎にはいくつかの種類があり、うつるものとうつらないものがあります。
- うつらない口内炎(アフタ性口内炎)
- うつる口内炎(ウイルス性口内炎)
ストレスや疲労、栄養不足などが原因でできる、白く円形の一般的な口内炎です。これは他人に感染することはありません。
ヘルペスウイルスなどが原因でできる口内炎です。水ぶくれのような見た目が特徴で、患部に接触することで感染する可能性があります。
ご自身の口内炎の種類がはっきりしない場合は、念のためキスや食器の共有などを避け、一度医療機関で診てもらうと安心です。
Q. はちみつや塩水でうがいをするのは効果がありますか?
A. 限定的な効果は期待できますが、治療の基本は医薬品の使用です。
はちみつには殺菌作用や抗炎症作用が、塩水には殺菌作用や粘膜を引き締める効果があるとされ、古くから民間療法として知られています。
これらでうがいをすることで、一時的に痛みが和らいだり、口の中がすっきりしたりする効果は期待できるかもしれません。
しかし、これらは医薬品ではなく、治療効果が科学的に証明されているわけではありません。
あくまでセルフケアの補助的な手段と捉え、つらい症状がある場合は、薬局で専用の医薬品を購入するか、医療機関を受診することを基本としましょう。
※1歳未満の乳児には、乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、はちみつを絶対に与えないでください。
Q. どうしても痛いとき、すぐに痛みを和らげる方法はありますか?
A. 局所麻酔成分の入った市販薬を使うか、患部を冷やすのが効果的です。
我慢できないほどの強い痛みがある場合、以下の方法で一時的に痛みを抑えることができます。
- 局所麻酔成分配合の市販薬を使う
- 患部を冷やす
軟膏やスプレータイプの中には、歯科治療でも使われる「リドカイン」などの局所麻酔成分が含まれているものがあります。患部の感覚を一時的に麻痺させ、つらい痛みを速やかに緩和します。
氷を口に含んだり、冷たい水を口に含んだりして、患部を直接冷やすことで、神経の感覚を鈍らせて痛みを和らげることができます。
ただし、これらはあくまで対症療法です。痛みの根本的な原因である炎症を抑えるため、抗炎症成分の入った薬での治療も並行して行いましょう。
Q. 口内炎が治りかけのサイン(治る前兆)はありますか?
A. 痛みの軽減と、見た目の変化で判断できます。
口内炎が快方に向かっているサインは、主に以下の通りです。
- 痛みが和らぐ
- 白かった部分が小さくなる
- 周りの赤みが引く
- くぼみが浅くなる
何もしなくてもズキズキしていた痛みがなくなり、歯や食べ物が触れたときの痛みも少しずつ弱くなります。
口内炎の中心部にあった、白くえぐれたような潰瘍(かいよう)の部分が、徐々に小さくなっていきます。
潰瘍の周りを囲んでいた、炎症による赤みがだんだんと薄れていきます。
患部のくぼみが浅くなり、新しいピンク色の粘膜が再生してきて、表面が平らになってきたら、治癒はもうすぐです。
これらのサインが見られたら、治りかけの証拠です。油断せず、完治するまで口腔内を清潔に保ちましょう。
まとめ|つらい舌の口内炎はセルフケアと専門家への相談で早く治そう
この記事では、痛い舌の側面の口内炎を1日でも早く治すための具体的なセルフケアから、その原因、危険なサインの見分け方まで、詳しく解説してきました。
つらい症状を乗り切るには、市販薬などを活用した「外からのケア」と、生活習慣を見直す「内からのケア」の両輪が非常に重要です。
どの薬がいいか迷ったら「mamoru」で薬剤師にオンライン相談
「口内炎の薬って種類が多くて、どれが自分に合うのかわからない…」
「病院に行くほどではないけど、この症状について専門家の意見を聞いてみたい」
そのようにお考えの方には、ご自宅からオンラインで気軽に薬剤師に相談できるサービス「mamoru」がおすすめです。
「mamoru」を使えば、
- 私のこの痛みに一番効く市販薬はどれ?
- 今飲んでいる薬との飲み合わせは大丈夫?
- この症状は、セルフケアで様子を見てもいい範囲?
といった、あなたが抱えるお薬に関する具体的な疑問や不安を、チャット形式で専門家に直接相談することができます。
わざわざ薬局に足を運ばなくても、スマホ一つで専門家のアドバイスが受けられる。
つらい口内炎と賢く付き合うための、新しい選択肢として。ぜひ「mamoru」の活用をご検討ください。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。