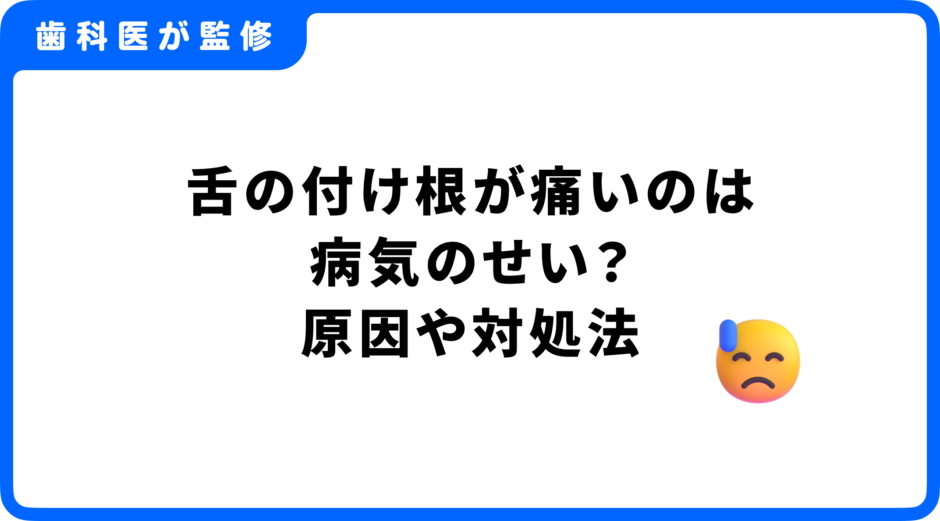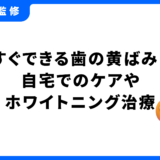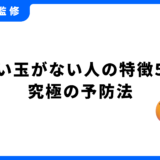「舌の付け根がズキズキ痛む……これって大丈夫?」
食事や会話のときにふと感じる舌の違和感や痛み。
舌の付け根に痛みがあると、「口内炎かも」「悪い病気だったらどうしよう?」と不安に思う人もいるでしょう。
実際、舌の付け根の痛みがある場合、軽度の炎症から神経痛、感染症、さらに口腔がんや舌がんの初期症状が懸念されます。
原因もさまざまです。
本記事では、舌の付け根の痛みについて、歯科医療の視点から詳しく解説します。
- 舌の付け根が痛くなる原因
- 舌の付け根が痛む場合に考えられる病気
- 自宅でできる対処法
- 病院を受診すべきタイミング
- 病院で受けられる治療
不安を感じたときこそ、正しい判断が大切です。舌の痛みに悩む方は、ぜひ参考にしてください。
▶関連記事:舌の側面の口内炎が痛い!原因は?薬局で買える市販薬と治らない時の対処法
舌の付け根が痛い場合に考えられる病気と原因
舌の付け根が痛む場合、口腔内の粘膜炎症や神経疾患、感染症、悪性腫瘍など、病気が潜んでいる可能性があります。
治療法や対処法は原因によって異なるため、症状の特徴や持続期間、全身の状態をよく観察し、原因を見極めることが重要です。
ここでは、舌の付け根が痛い場合に考えられる主な病気とその原因について解説します。
口内炎(アフタ性・ウイルス性)
口内炎は、舌の付け根が痛む大きな原因の一つです。
舌の付け根に白っぽい潰瘍や赤いただれができ、食事や会話のたびにヒリヒリと痛むのが特徴です。
アフタ性口内炎の場合、単発または複数の口内炎が発生しますが、多くは1週間ほどで自然に治ります。
一方、ウイルス性口内炎には発熱や水疱を伴うケースがあり、再発する場合もあるため注意が必要です。
以下、舌の付け根に口内炎ができる主な原因を解説します。
免疫低下
ストレスや睡眠不足、栄養不足などによる免疫力の低下は、口内炎の発症リスクを高めます。
口腔内の粘膜が弱ることで細菌やウイルスが侵入しやすくなり、潰瘍や炎症を引き起こす一因となります。
ビタミンや鉄・亜鉛の不足に注意が必要です。
外傷
誤って噛んでしまったり、矯正器具などが擦れたりして舌の付け根が傷ついた場合、細菌が繁殖して炎症を起こし、口内炎となる場合があります。
矯正器具や差し歯、詰め物などが擦れる場合は、口の中が傷つく原因となるため、歯科医院で調整してもらうことをおすすめします。
口内炎の治し方について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
舌炎・舌乳頭炎
舌炎や舌乳頭炎になると、舌の付け根にヒリヒリした痛みや腫れが生じ、舌表面が赤くなり、ぶつぶつと盛り上がることがあります。
軽症であっても、味覚異常や話しにくさを感じ、日常生活に支障をきたす可能性があります。
以下は、舌炎や舌乳頭炎の主な原因です。
味蕾や舌乳頭の炎症
舌表面を覆う突起状の舌乳頭(ぜつにゅうとう)や味蕾(味を感じる器官)が、熱いもの・粗く硬い食材・刺激の強い調味料などで炎症を起こすと、舌に痛みが生じます。
口が乾燥して唾液が減少していると、粘膜の防御力が下がり、炎症を起こしやすくなります。
義歯や刺激物
入れ歯や矯正器具、銀歯の縁などが舌に慢性的な刺激を与えることで、炎症や潰瘍を生じやすくなります。
また、香辛料やアルコールなどの刺激物の過剰摂取も粘膜にダメージを与える要因です。
舌咽神経痛(ぜついんしんけいつう)
舌咽神経痛(ぜついんしんけいつう)は、舌の付け根から喉、耳の奥まで、鋭い痛みが突然広がって感じられるのが特徴です。
非常にまれな病気であり、100万人に数人程度の割合しかいないと言われています。
会話や飲食時、あくびなどの日常的な動作で誘発されます。
痛みは数秒から数十秒で治まりますが、発作的に繰り返すため、生活に支障をきたす場合もあります。
以下、舌咽神経痛の主な原因を解説します。
動脈による舌咽神経の圧迫
近接する血管(とくに動脈)により、舌咽神経が物理的に圧迫されると、神経が過敏化し、激しい神経性の痛みを生じます。
このようなケースでは、薬物治療や、脳外科的な手術による処置が必要な場合があります。
扁桃炎・咽頭炎・風邪に伴う痛み
風邪のような体調不良と同時に、喉の奥から舌の根元あたりが痛む場合は、咽頭部の炎症が舌へと波及している可能性があります。
発熱や咳、倦怠感を伴うときは、感染症への対処が必要です。
以下、風邪症状の主な原因を解説します。
免疫力の低下
風邪や扁桃炎などの感染症は、免疫力が低下している際にウイルスや細菌が侵入・増殖することで発症します。
その結果、喉の周囲組織へ炎症が波及し、舌の付け根が痛む可能性があるのです。
口腔がん・舌がん
舌のしこりやただれ、出血、潰瘍などが2週間以上治らない場合、口腔がんや舌がんの可能性が否定できません。
口腔がん・舌がんの初期症状は軽い痛みがある程度なので、見過ごされやすいと言われます。
舌の側面や付け根の異変に気づいた時点で、早めに病院を受診しておくと安心です。
口腔がんや舌がんの原因について2つ紹介します。
口の中への慢性的な刺激
尖った歯や合わない義歯などによって物理的刺激が繰り返されると、慢性的に粘膜が傷ついている状態になります。
物理的刺激が長期間続くと、細胞ががん化するリスクが高まると言われているため注意が必要です。
飲酒や喫煙
アルコールやタバコの摂取は、口腔内粘膜に発がん物質が直接影響を与えます。
さらに、粘膜の修復能力を低下させ、がん化リスクを高める要因となります。
とくに飲酒と喫煙の両方を習慣化している人は、がんのリスクが高いため注意が必要です。
口腔カンジダ症
白い苔状の膜が舌の付け根から口の中まで広がっている場合、カンジダという真菌(カビ)の感染が疑われます。
ヒリヒリする痛みや味覚の低下、赤みなどの症状が特徴で、高齢者や基礎疾患がある方に多いと言われています。
口腔カンジダ症の原因は以下の通りです。
抗生物質の服用
抗生物質の使用により、口の中の善玉常在菌が減少し、カンジダ菌が過剰に増殖することがあります。
長期服用後にカンジダの症状が出た場合は、抗生物質の影響である可能性が高いでしょう。
免疫低下
免疫力が低下していると、カンジダ菌による日和見感染(普段は悪さをしない菌が暴れる状態)を起こしやすくなります。
がん治療中や糖尿病の方、慢性的に栄養不良の方はとくに注意しましょう。
舌痛症(神経性)
検査では異常が見つからないのに、舌の付け根や側面に慢性的な痛みや違和感が続く状態を舌痛症(神経性)と言います。
ピリピリ・ヒリヒリとした痛みが特徴的で、一日の中でも痛みに波がある傾向です。
舌痛症(神経性)の原因は以下に解説します。
ストレスやうつ傾向
ストレスが続くことで自律神経や感覚神経のバランスが乱れ、感受性が過敏になっていると、舌に痛みを感じやすくなります。
うつ傾向や不安障害を併発することがあり、心理的要因が大きい疾患といえます。
更年期
女性の更年期には、ホルモンバランスの変化により、口腔内の知覚異常が起こりやすくなるとされています。
女性ホルモンの減少は、痛みや味覚障害、舌の不快感を引き起こす一因です。
舌の付け根が痛い場合に自宅でできる対処法
舌の付け根に痛みを感じる場合、自宅での初期対処を行いましょう。
症状が軽度で他に明らかな異常がなければ、そのまま完治する可能性もあります。
炎症の悪化を防ぎ、回復を促すためには、患部への刺激を避けて安静を保つこと、栄養・衛生・休養を整えることが基本です。
以下に、自宅で無理なく取り組めるセルフケアの方法を紹介します。
患部を刺激から守る
舌の付け根が痛いときは、とにかく患部を刺激から守ることが最優先です。
口の中は、食事や会話などで活発に動いているため、舌を完全に安静にすることは難しいでしょう。
しかし、濃い味付けや熱すぎる食事・硬い食べ物などは極力控えることで、粘膜への負担を減らすことは可能です。
また、歯ブラシやデンタルフロスによるケアを行う際にも、舌を不用意にこすらないよう注意しましょう。
義歯や矯正器具が当たって擦れている場合、歯科医院で調整してもらってください。
就寝時に口が乾きやすい人は、口呼吸の傾向がないかを見直してみましょう。
口呼吸を改善するだけで、口内炎や舌の付け根の痛みも、治りやすくなります。
痛みのある患部周辺を安静に保つように意識するのが重要です。
無意識に舌を噛んでしまうクセがある人は注意しましょう。
これだけでも、炎症の悪化を防ぎ、早期回復を期待できます。
刺激が少なめのバランスの良い食事を摂る
口腔粘膜の修復には、食生活の見直しが重要です。
舌の付け根が痛いときは、温かくやわらかい、刺激の少ない食品を選ぶようにしましょう。
逆に、舌の付け根が痛む際に避けるべき食事は以下の通りです。
患部を刺激してしまう食べ物はできるだけ避けましょう。
さらに、粘膜の回復や免疫維持には、ビタミンB群(特にB2・B6・B12)やビタミンCを始めとするビタミンや、鉄、亜鉛などの栄養素が不可欠です。
例えば以下のような食品が効果的です。
これらの栄養を意識的に取り入れつつ、できるだけ栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
食生活の偏りは、再発や慢性化のリスクを高める可能性があります。
市販の口内炎治療薬を使用する
軽度の舌の痛みに対しては、市販薬で症状を緩和することも可能です。
口内炎用の治療薬には、さまざまなタイプがあります。
- ステロイドを含む軟膏タイプ
- 抗炎症作用のある貼り薬
- 粘膜保護成分を含むスプレー など
なかでも、有効成分「トリアムシノロンアセトニド」や「アズレンスルホン酸ナトリウム」などを含む製品は、炎症を抑える効果が期待でき、痛みの軽減につながります。
口の中にも塗りやすいジェルタイプや、食事中に患部を保護できるフィルム型もあります。
ただし、市販薬の長期間の使用は避けるべきでしょう。
市販のステロイド入り口内炎薬は、短期間の使用であれば痛みや炎症を抑えるのに有効ですが、長期使用は粘膜を弱める可能性があるため、使用期間や用量は遵守してください。
また、妊娠中・持病のある方は、薬剤師に相談して利用することが推奨されます。
1週間以上痛みが改善しない場合や痛みが強くなる場合は、早めに病院を受診しましょう。
うがい薬や抗菌作用のあるケア製品を活用する
炎症の拡大を防ぐためには、口の中の衛生管理が非常に重要です。
痛みがあっても、食後や就寝前には必ずうがいをし、口内の細菌繁殖を防ぎましょう。
水だけのうがいでも効果はありますが、抗炎症・抗菌作用のある洗口液やうがい薬を活用するとより高い効果が期待できます。
例えば、グルコン酸クロルヘキシジン・セチルピリジニウム塩化物などを含む製品は、歯科医院でも使用される安全性の高いうがい薬です。
ただし、アルコール含有タイプは刺激が強いため、粘膜が弱っているときはノンアルコールタイプを使ってください。
また、うがいの後は、保湿効果のある口腔ジェルや保湿スプレーで粘膜を乾燥から守りましょう。
口の中のクリーニングと患部の保護を行うことが、回復を早めるポイントになります。
睡眠・休養を十分にとる
舌の痛みの原因が免疫力の低下や体調不良によるものである場合、最も効果的な対処法は「しっかり休むこと」です。
睡眠不足や、生活リズムが乱れてストレスが多い状態は、全身の体調悪化や粘膜の不調を起こす大きな要因となります。
粘膜の再生は睡眠中に最も進むといわれています。6〜8時間の質の高い睡眠を確保することで、舌の痛みの回復は早まるでしょう。
睡眠・休息時には舌を動かさずに済むため、患部を自然に安静にできるメリットもあります。
ストレスが強い方は、軽い運動・入浴・深呼吸・趣味の時間を取るなど、心身のケアも積極的に行ってみてください。
体も心も回復する時間を意識的につくることで、口の中のトラブルの予防につながります。
舌の付け根が痛い場合に病院で行う治療
舌の付け根の痛みが続く場合は、歯科や耳鼻咽喉科などの医療機関での診察と治療が必要です。
原因となる疾患によって治療方針が異なるため、まずは医師による診断を受けましょう。
ここでは、病院で受けられる主な治療内容を紹介します。
症状や原因に応じた薬物療法
医療機関ではまず、舌の痛みの原因となっている疾患に応じた薬物療法を行います。
たとえば、細菌感染や扁桃炎が原因である場合には、抗生物質を処方して感染の拡大を防ぎます。
カンジダ症であれば抗真菌薬が、神経性の痛みに対しては鎮痛補助薬や抗けいれん薬、漢方薬などが処方されるのが一般的です。
原因が明確でない舌痛症の場合には、自律神経に作用する薬や心身のバランスを整える補助薬が検討されるケースもあります。
いずれも自己判断では入手・使用できない薬です。
ステロイドや鎮痛剤の処方
炎症による痛みが強い場合には、ステロイド薬や鎮痛剤が用いられます。
ステロイドには強い抗炎症作用があり、短期間の使用であれば粘膜の腫れや痛みを速やかに抑えられます。
患部に直接塗布する軟膏やパッチ、うがい薬の形で処方されることが多いです。
炎症に限らず、神経性の痛みに対しても、痛みをやわらげるための鎮痛薬(アセトアミノフェン・ロキソプロフェンなど)、神経障害性疼痛治療薬(リリカ)が併用される場合があります。
なお、ステロイドの長期使用には副作用のリスクがあるため、指示された期間・用量を必ず守ることが大切です。
舌がんの場合は外科・放射線・化学療法
舌の付け根の痛みの背景に口腔がん(舌がん)が潜んでいた場合は、口腔外科やがん専門病院での精密検査と専門的な治療が必要となります。
舌がんの治療は主に以下の3つに分類されます。
| 外科手術 | がん組織の切除。早期であれば機能温存(身体の機能を残すこと)が可能。 |
| 放射線治療 | がん細胞を局所的に破壊する。 |
| 化学療法(抗がん剤) | 進行がんや再発防止を目的に全身投与。 |
初期の舌がんは痛みが少なく、「治らないできもの」や「しこり」として見つかることが多いと言われます。
2週間以上症状に変化がない場合、早めに病院を受診してください。
舌がんは早期に発見すれば予後が良好ながんでもあるため、異常を感じたら迷わず検査を受けましょう。
舌の付け根が痛い場合に通院すべき症状は?
舌の痛みは多くの場合、軽度の炎症や体調不良によって起こる一時的なものです。自宅でのケアによって改善するでしょう。
しかし中には、病気のサインや慢性化の兆候が隠れている場合もあります。
「いつまで経過観察でいいのか」「どの症状が危険なのか」を知っておくと安心です。
ここでは、医療機関の受診が推奨される基準について解説します。
痛みが1週間以上続く・悪化する
舌の付け根の痛みが1週間以上続く場合、黄色信号です。
さらに、痛みが徐々に強くなっていたり、日常生活に支障が出たりしている場合は、ただの炎症以上の病気が関係している可能性があります。
一定でなく波がある痛みや、ピリピリ・ズキズキといった神経性の症状がある場合は、舌咽神経痛などの疾患が隠れているかもしれません。
また、口腔がんなどの初期症状も「治りにくい痛み」として現れることがあるため、早期治療できるかが予後を左右するかも。
1週間待っても痛みが引かない場合、病院を受診しましょう
しこり・出血・ただれなどの異常がある
舌の付け根に痛み以外の異常がある場合、早急に病院を受診すべきでしょう。
具体的には、以下のような異常に注意します。
- しこりがある
- 出血している
- 粘膜がただれている
- 白い斑点や赤い腫れが消えない
これらは単なる炎症ではなく、前がん病変や悪性腫瘍の可能性があります。
歯科・口腔外科・耳鼻咽喉科などでの精密検査を推奨します。
医療機関では、触診・視診・細胞診(擦過細胞診)・画像診断や生検などを行い、悪性の症状がないかを確認します。
できものや異常が気になる場合、「自然に消えるだろう」と様子を見ず、早めに病院を受診しておくのが安心です。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。
全身症状(発熱・倦怠感など)を伴う
舌の付け根の痛みに加えて、発熱・寒気・倦怠感・関節痛・リンパ節の腫れなど全身症状が出ている場合は、感染症や全身性疾患である可能性が高くなります。
舌の付け根の痛みと全身症状を伴う代表的な疾患として、以下が警戒されます。
- 扁桃炎
- 咽頭炎
- インフルエンザ
- ウイルス性口内炎(ヘルペス) など
これらの疾患にかかった場合は、抗菌薬や抗ウイルス薬による治療が必要です。
また、鉄欠乏性貧血やビタミンB12欠乏、自己免疫性疾患などが舌の粘膜に症状を出すケースもあります。
これらの疾患は、血液検査や全身の診察を行わないと判断できないため、口腔内の症状だけに目を向けていると見逃しがちです。
体のだるさや食欲不振など、いつもと違う調子の悪さを感じたら、早めに病院を受診して原因を見極めましょう。
舌の付け根が痛い場合の注意点
舌の痛みに対処する際、間違った処置をするとかえって症状を悪化させてしまうことがあります。
口腔粘膜はデリケートで、刺激に対して非常に敏感です。誤ったケアを続けると、慢性化や別の病気を引き起こすリスクもあります。
ここでは、舌の付け根が痛いときの注意点を具体的に解説します。
自己判断で市販薬を長期使用しない
市販薬は便利な一方、使用方法を誤ると回復を遅らせる原因になることがあります。
口内炎用のステロイド軟膏や鎮痛スプレーは、一時的な症状緩和には有効です。
しかし長期的に使用すると、粘膜の自然治癒を妨げ、感染のリスクを高める場合があります。
また、喉の痛みの原因が感染症や神経痛、腫瘍などだった場合、市販薬では根本的な治療ができません。
薬によって一時的に痛みが軽減したとしても、本来の病気の進行が隠れてしまうおそれがあります。
薬を使い続けているのに症状が改善しない場合は、自己判断での薬の使用を中止し、医師の診察を受けましょう。
過剰なうがいや歯磨きによる刺激に注意
口腔内を清潔に保つことは大切ですが、過剰なうがいや歯磨きは逆効果かもしれません。
痛みがあるからといって、ブクブクと強いうがいを頻繁にしたり、舌や粘膜をゴシゴシ強く磨いてしまうと、かえって粘膜を傷つけ、炎症を悪化させてしまうおそれがあります。
また、アルコール成分の強いうがい薬や発泡性の高い歯磨き粉を多用すると、乾燥や刺激によって痛みが増すケースも。
とくに舌の付け根は敏感なので、過剰な物理的刺激は痛みの長期化を招くことがあります。
正しいケアのポイントは次の通りです。
- うがいは1日2〜3回、ぬるま湯または刺激の少ない洗口液で行う
- 舌をブラッシングする際は、柔らかい専用ブラシを軽く当てる程度にする
- 歯磨きはやさしく、時間をかけすぎない
清潔を意識するあまり、かえって炎症を長引かせてしまわないよう、粘膜に優しいケアを心がけましょう。
舌の付け根の痛みに関するよくある質問
ここでは、舌の付け根の痛みに関するよくある質問に回答します。
舌の付け根の片側だけ痛いのはなぜですか?
舌の付け根の片側だけに痛みがある場合、神経や筋肉、器具の接触による刺激が関与している可能性があります。
たとえば、片側の歯並びや銀歯・入れ歯が舌の付け根に当たっていると、局所的な炎症を起こすことがあります。
また、「舌咽神経痛」など、片側の神経にだけ異常が生じる疾患があります。
特に、食事や会話のたびに決まった側だけが刺すように痛む、電気が走るような痛みがある場合、神経痛の可能性が否定できません。
耳鼻咽喉科や神経内科で診てもらうとよいでしょう。
また、片側の粘膜にのみしこりや出血、潰瘍などがある場合は、舌がんなどの早期症状である可能性も。
自己判断せず、医療機関へ相談するのが安心です
舌の付け根が痛い原因はストレスですか?
ストレスは舌の痛みの引き金になることがあります。
とくに「舌痛症(ぜっつうしょう)」という疾患では、明らかな傷や炎症がないにもかかわらず、舌の付け根や側面にヒリヒリ・ピリピリする慢性的な痛みが出現します。
この症状は、ストレスや自律神経の乱れ、ホルモンバランスの変化(特に更年期)が関係していることが多いと言われ、検査では異常が見つからないのが特徴です。
そのため「気のせい」と思われがちですが、病的状態であることに変わりはありません。
舌痛症の治療には、心身のストレス軽減、漢方薬、ビタミン補給などが検討されます。
「異常がないのに舌の付け根がずっと痛い」と感じる方は、歯科や心療内科での相談も視野に入れてみてください。
舌の付け根が痛い場合にコロナの可能性はありますか?
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に関連して、舌や口の中に異常が現れる場合があります。
とくにコロナウイルスの感染初期には、味覚障害や舌のピリピリ感、乾燥感、舌の痛みなどが現れることも。
舌の付け根やのどの違和感でコロナに気づいたという例も多数あります。
ただし、舌の付け根が痛いという症状だけでは、コロナであると特定はできません。
発熱・咳・全身のだるさなど、その他の全身症状の有無も重要な判断材料になります。
舌の痛みに加えて「味がしない」「のどがヒリヒリする」「咳や発熱がある」などの症状がある場合、医療機関または発熱外来での相談・検査をおすすめします。
また、コロナ回復後もしばらく痛みや違和感が続く「後遺症(ロングCOVID)」の一環として、舌の痛みが出るケースも報告されています。
必要に応じて専門外来の受診を検討しましょう。
まとめ
舌の付け根が痛いという症状には、さまざまな病気が隠れている可能性があります。
単なる口内炎や一時的な不調によるものから、神経の異常や感染症、まれに口腔がんまで。
自己判断による長期間の放置は禁物です。
舌の付け根に痛みを感じたら、患部への刺激を避け、食事と休養に注意しながら市販薬でケアするなどの処置を行いましょう。
1週間以上症状が続く場合や、悪化や異常な変化に気づいた場合には、必ず歯科や医療機関での診察を受けましょう。
日ごろから歯科医師の指導に基づいた予防に取り組み、口腔内の定期検診を受けるのも大切です。
通いやすい予防歯科を検索できる「mamoru」などのサービスもぜひご活用ください。
すぐに歯科医院で診てもらいたい方は、全国の歯科クリニックからあなたにピッタリの歯科が見つかる「歯科まもる予約」もご利用ください。